錯聴(auditory illusion) 柏野牧夫
マスキング可能性の法則 連続聴効果
視覚と同様に、錯聴(auditory illusion)がある。イリュージョンフォーラムのデモで錯視と錯聴をあれこれ比べられる。
私たちが知覚している音の世界は、耳に入ってくる音そのものではないということ。日常の環境で、安定して効率よく音を聞き取るための数々の巧妙なしくみ。 裏を返せば、「耳」だけでは音は聞こえないということ。耳は聴覚システムの入り口、その後に続く脳での膨大な情報処理が支えている。錯聴を詳しく分析すれば、脳での音の処理メカニズムについての手がかりが得られる。
なぜ一般には錯視ほど知られていないのか。音に対する関心は人類の文化発祥以来とも言え、あえて錯聴と名付けなくとも、知覚特性を巧妙に利用した音の提示法はさまざまな分野で開発され、利用されてきた。バロック音楽では複数の旋律が同時に奏でられているように錯覚させる手法(音の流れの分凝)が使われた。オーディオも、限られた2チャンネルによる音の提示によって、あたかもその場で演奏されているような感覚をいかにして生じさせるかという錯覚の探求といえる。
研究は、1960年代から70年代にかけて第一次黄金期。連続聴効果や音階の錯覚、反復の変形などは、 この時代に発見された。
1990年代には、このような現象をより定量的に把握したり、計算モデルで説明したりしようという試みが盛んになった。
2000年代に入ると、 聴覚に関わる脳のメカニズムを解明する研究の中で、錯聴も格好の素材として取り上げられるようになった。
関連記事
-

-
『カシュガール』滞在記 マカートニ夫人著 金子民雄訳
とかく甘いムードの漂うシルクロードの世界しか知らない人には、こうした動乱の世界は全く想像を超えるも
-
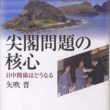
-
『尖閣諸島の核心』矢吹晋 鳩山由紀夫、野中務氏、田中角栄も尖閣問題棚上げ論を発言
屋島が源平の合戦の舞台にならなければ観光客は誰も関心を持たない。尖閣諸島も血を流してまで得るもの
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-

-
日本銀行「失敗の本質」原真人
黒田日銀はなぜ「誤算」の連続なのか?「異次元緩和」は真珠湾攻撃、「マイナス金利」はインパール作戦
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 視覚 知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避、色盲メガネ
◎松井冬子 博士論文「知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避」 生まれ
-

-
『「日本の伝統」の正体』
現在、「伝統」と呼ばれている習慣の多くが明治時代以降に定着したと聞いたら驚く人も多いかもしれない
-

-
意識あるロボットの出現とホスピタリティー論の終焉
かねがね、観光学研究で字句「ホスピタリティー」が使用されていることに大きな疑問を感じていた。意識
-
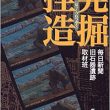
-
『発掘捏造』毎日新聞旧石器遺跡取材班
もう20年も前の事であるが、毎日新聞取材班の熱意により旧石器遺跡の捏造事件が発覚した。その結果、
-

-
ニクァラグア手話 聴覚障害の子どもたちが手話を作り出すまで
https://youtu.be/qG2HjmG0JGk https://www.bbc
-

-
『中国はなぜ軍拡を続けるのか』阿南友亮著
第40回サントリー学芸賞(政治・経済部門)受賞!第30回アジア・太平洋賞特別賞受賞! 何

