『ファストフードが世界を食いつくす』エリック・シュローサ―著2001年
ただ一つの言葉で言い表すと、画一性
トーマス・フリードマンは自著の『レクサスとオリーブの木』の中で、“黄金のM型アーチ理論”として「マクドナルドのある国同士は戦争を行わないだろう」と予言したが、1999年にアメリカ合衆国のセルビア爆撃によって破られている。
2004年には、マクドナルドに代表されるファーストフード業界の健康破壊をテーマに「1か月間、3食マクドナルドのハンバーガーだけを食べて過ごしたらどうなるか」監督が自らを人体実験となった、ドキュメンタリー映画『スーパーサイズ・ミー』が公開され、第77回アカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。2011年には、550超の団体が対し、肥満の抑制のためにロナルド・マクドナルドの引退を要請している[36]。 パンフレットには「企業批判のメッセージのために作られたものではない」と書かれており、監督自身も「この食文化への警鐘。貧困家庭はファストフードに頼りがち。マクドナルドを選んだのは彼らが一番大きいから」としている。来日した際、ドキュメンタリー映画監督の森達也は、「アメリカンライフ(価値観)を他者に押し付けるアメリカを風刺している。アメリカの実存そのものへの批判、メタファーが隠されていると受け取った」と語ると、監督は肯定している[4]。 マクドナルドは、メニューに食材の生産地や食物アレルギー対応[37]を細かく明記している。またシェフでイギリス人としては初めて、かつ歴代最年少でミシュランガイド三ツ星を獲得したマルコ・ピエール・ホワイトは「商品には一貫性があり、価格に対してその品質は優れている。アイルランド産など徹底した品質管理を行なっているにも関わらず、この事実はあまり知られていない。」と意見している。 2011年には、専門家らはマクドナルドに対して、子供を対象とした飲食品に高カロリー、高脂肪、多い砂糖、高塩分のジャンクフードの販売中止、おまけをつける販売の中止、ロナルド・マクドナルドを引退させることを要請している。
書評群
一見ファストフード界へのバッシング本かと思いきや、
その起源やアメリカ経済から見た歴史に始まり
経営戦略の問題までじっくりとレポートされており、
その上で問題点を提示するという作りになっています。
マクドナルド社のハンバーガーの材料の不衛生さなどについての言及もありますが、
それよりも劣悪な労働環境問題、企業の政治介入の歴史などの説明に
じっくりページが割かれています。
克明に著者がインタビューや取材を行い、参考文献を揃えただけに
文章が膨大なものとなり、読みきるのが辛い印象もありますし、
アメリカの馴染みの無い地名や会社名に「対岸の火事」的な印象を受けるかもしれませんが
是非、ファストフードという文化がもたらす消費者だけでない、
様々な方面への悪影響の実情をひとりでも多くの方に
知って欲しい、また考えて欲しいと思います。 使われている肉の中身からずさんな労働管理の実態まで、著者の徹底的な取材によってファストフード業界の闇の部分が鋭く描き出される。
読み始めて、”Fast Food Nation” という原題に対してずいぶん大袈裟な日本語タイトル付けたなぁ、と感じていましたが、途中から納得します。アメリカのビジネス・プラクティスがグローバル・スタンダードになりつつあるのは企業会計だけではありません。
訳者は“訳者あとがき”で「これは義憤の書である。」と書かれていますが、小生は極めて事実を明確かつ詳細に報告することで読者に対し、知的に選択肢を与えているスタイルに好感を持ちました。同時に、それぞれの食の現場で何が起こっているのかを決してセンセーショナルには書かず、どういうビジネス上の、あるいは、行政上の理由があって、そのようなことが敢行されているのかなどを克明にルポしています。
前半のマクドナルド社とディズニー社との関係に関する部分はブランド・マーケティングの良き参考書とみなされるべきであろう。 この本は読み進めるほど過激な内容になっていく。圧巻は、自ら食肉処理工場を訪ねて見た牛の解体現場のシーンだ。作業員が牛の腹に腕を突っ込んで素手で腎臓をもぎ取るなど、過酷な作業の実態が描かれている。また、ここで処理された肉の安全性に問題があると厳しく非難している。すべて事実かうかがい知ることはできないが、普段食べているファストフードへの認識を改めさせられるのは確かだ。
アメリカ的世界均質産業=グローバリズムの象徴、ファーストフード業界の闇を暴いた本書はその内容のあまりのエグさにかなりの反響があったらしい。不法労働者を最低賃金で雇用し、人の口に入る食物に関して安全対策を極力怠る?という手法でひたすら利益のみを追及する。面白いのは、その人間性を無視した画一的なシステムが、アメリカ人(とくに共和党)が最も嫌う共産主義体制に酷似しているという点だ。
糞もミソも一緒の劣悪な環境の食肉工場から出荷される細菌まみれの食肉を食わされる消費者にとってはたまったものではない。自分で食えないモノを人に食わすなと言いたいところだが、共和党に多額の献金をしている大企業にとって都合の悪い法律が民主党から出されると、すぐさまその共和党政府によってつぶされるというおかしな状況がずっと続いているのがアメリカの現況なのだ。自由競争を金科玉条のように唱えるグローバリズム産業の台頭によって、O−157やサルモネラ菌によって汚染された食肉を食わされ、劣悪な職場環境でコキ使われるのが、結局我々消費者(特に低所得者層)であることがこの本を読むととてもよくわかる。
クラシックやオペラなどと同様に本来は<文化>であるべき食物に、製造業と同じ原理を持ち込む自体そもそも間違っているような気がする。ファーストフードに代表される大量生産システムが、未来につなげるべき資産や資源を猛スピードでただ食いつぶしているだけだということを、アメリカ人やアメリカのマネをして見せかけの競争に奔走している日本人たちもそろそろ気づかなければならない段階にきている。
関連記事
-

-
7月21日 第二回観光ウェアラブル委員会を開催して
満倉靖恵慶応大学理工学部准教授と㈱ナビタイムジャパン野津直樹氏に講演を頂いた。 満倉先生は「脳
-
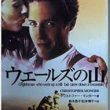
-
観光資源創作と『ウェールズの山』
観光政策が注目されている。そのことはありがたいのであるが、マスコミ、コンサルが寄ってたかって財政資金
-

-
保護中: 米国コロナ最前線と合衆国の本質(5) ~メディアが拍車をかける「全く異なる事実認識」:アメリカのメディア統合による政治経済と大統領支持地域のディープストーリー
印刷用ページ 2020.07.08 米国コロナ最前線と合衆国の本質(5) ~メ
-

-
Quora なぜ日本海側の人口は少ないのですか?
工業化が進んで、人々が東京、名古屋、大阪に流れてしまったからです。 昔は多かったんですよ、日
-

-
『意識はいつ生まれるのか』(ルチェッロ・マッスィミーニ ジュリオ・トノーニ著花本知子訳)を読んで再び観光を考える際のメモ書き
観光・人流とは人を移動させる力であると考える仮説を立てている立場から、『識はいつ生まれるのか』(ルチ
-

-
2018年3月14日 CATVで クリミナル・マインド 国際捜査班 死神のささやき を見て
自画自賛のインバウンド宣伝が多い中、クリミナルマインド国際捜査班の第4話は日本がテーマ。高視聴率を誇
-

-
箱根について 藤田観光元会長の森本昌憲氏の話を聞いた結果のメモ書き ジャパンナウセミナー
2017年10月13日ジャパンナウ観光情報協会の観光立国セミナーで森本氏の話を聞く。日本ホテル・レス
-

-
書評 AIの進化が新たな局面を迎えた:GTP-3の衝撃
米国コロナ最前線と合衆国の本質(10)~AIの劇的な進展と政治利用の恐怖~ https://
-

-
ホロポーテ―ションとレッド・ツーリズム、ポリティカル・ツーリズム
Holoportationが紹介されていた。動画のアドレスは下記のとおりである。 https://
