『脳の誕生』大隅典子 Amazon書評
http:// www.pnas.org/content/supp1/2004/05/13/0402680101.DC1
見つからなかった。
鳥類の脳は空間的制御、哺乳類の脳は時間的制御により、それぞれ特異的なニューロンを誕生させた
内容(「BOOK」データベースより)
私たちの脳は、たった1個の受精卵という細胞から、どのように出来上がったのだろう。本書は、四次元でダイナミックに生まれていく脳のドラマを解説する初の入門書である。神経組織やニューロンが作られ、脳の枠組みが出来上がる「発生」ステージ、ニューロンが突起を伸ばし繋ぎ合わされて大人の脳に成熟していく「発達」ステージ、地球史・生物史の視点からヒトの脳へ至る道筋をたどる「進化」ステージ―以上三部構成で、30週、20年、10億年の各スケールに立ち、脳という小宇宙が形作られる壮大なメカニズムを追う!
他の生物と比較した場合のヒトの大きな特徴の一つは、大きくて複雑な脳を持っていることであろう。ヒトの脳には約800億から1000億個もの神経細胞(ニューロン)が存在すると見積もられており、それらがシナプスという構造を介して複雑なネットワークを形成することで高度な精神、神経活動を常時行っている。本書は、元々1個の受精卵が分裂を繰り返す過程でどのように脳が形成されていくか(発生)、また形成された後に環境からの刺激などによって神経の配線がどのように作られていくのか(発達)について解説している。発生の過程で将来脳や脊髄になる部分が「管」として出来、それらが多くのタンパク質の働きで区画化され、大脳や小脳といった特徴的な脳の構造になっていく過程は非常にダイナミックである。また、誕生前後に構造的には完成した後、ニューロンの配線が次々と形成される一方、配線の形成が出来なかったニューロンは死滅し、また一旦形成されたシナプスも環境からの刺激を受けて強化されるだけではなく整理(「刈り込み」と呼ばれる)されるものもあり、出生後の環境や刺激の種類や質といったものが脳の発達にいかに重要であるかを改めて認識させられる。
一般的に「脳の誕生」ということをテーマとする場合話はここまでであるが、本書の類書との違いは脳の誕生を進化という非常に長い時間スケールでも解説していることである。勿論、脳のような柔らかい組織は化石として残らないので、現生の生物の神経や脳組織の違いなどを基にヒトへ至る進化の道筋を説明しているが、これによりヒトの脳の特徴といったものをより複合的に理解できる。特に、神経組織を持った多細胞生物に特徴的なはずのシナプス構造に存在する分子(タンパク質)が、単細胞生物(クラミドモナス)や多細胞生物でも神経系を持たないカイメンなどに既に備わっているという話は非常に印象に残った。生物は進化の過程で獲得した遺伝子(その産物であるタンパク質)を本来の目的以外にも活用することで多様で複雑な生物種を生み出していった典型例の一つと言えるのかもしれない。
かなり多くの情報が盛り込まれているので、生物学の基礎知識がない読者には少し理解しにくい部分もあるように思われるが、それでも脳の発生や構造に関する現在の知見を取り上げるには新書としては限界があるようである。それでもヒトの脳がいかに複雑かつ精妙に作られているかは十分感じることはできる。より詳しく知るための入門書としては有用な本であると思われる。
関連記事
-

-
1932年12月16日『白木屋の大火始末記』
関東大震災の始末が終了したころ 地下三階地上七階建てデパートの4階から出火 クリスマスツリーの豆電
-
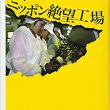
-
『ルポ ニッポン絶望工場』井出康博著
日本で働く外国人労働者の質は、年を追うごとに劣化している。 すべては、日本という国の魅力が根本のと
-

-
現代では観光資源の戦艦大和は戦前は知られていなかった? 歴史は後から作られる例
『太平洋戦争の大誤解』p.183 日本人も戦前はほとんど知らなかった。戦後アメリカの報道統制
-
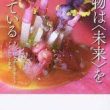
-
保護中: 『植物は未来を知っている』ステファノ・マンクーゾ 、動物が必要な栄養を見つけるために「移動」することを選択。他方、植物は動かないことを選び、生存に必要なエネルギーを太陽から手に入れるこにしました。それでは、動かない植物のその適応力を少しピックアップ
『植物は<未来>を知っている――9つの能力から芽生えるテクノロジー革命』(ステファノ・マンクーゾ著、
-

-
フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで
観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる
-

-
井伏鱒二著『駅前旅館』
新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は
-

-
『支那四億のお客様』カール・クロ―著
毎朝散歩コースになっている一か所に商業会館ビルというのがある。この本を出版したのが倉本長治氏のよう
-

-
保阪正康氏の講演録と西浦進氏の著作物等を読んで
日中韓の観光政策研究を進める上で、現在問題になっている「歴史認識」問題を調べざるを得ない。従って、戦
-
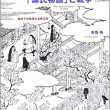
-
『「源氏物語」と戦争』有働裕 教科書に採用されたのは意外に遅く、1938年。なぜ戦争に向かうこの時期に、退廃的とも言える源氏物語が教科書に採用されたのか
アマゾン書評 源氏物語といえば、枕草子と並んで国語教科書に必ず登場する古典である。
-
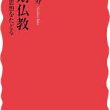
-
『初期仏教』 馬場紀寿著
初期仏教は全能の神を否定 神々も迷える存在であるので、祈りの対象とならない
- PREV
- Quora 古代日本語の発音
- NEXT
- 電子出版事始め『人流・観光学概論』
