電子出版事始め『人流・観光学概論』
公開日:
:
観光学評論等
大学のテキストで使用するつもりであった『人流・観光学概論』、ウィネットの好意で、校正済みのPDFを送ってもらい、自ら電子出版することにした。
PDFそのものは、人流観光研究所HPの著作物の欄及びジャパンナウ観光情報協会HPからダウンロードできるようにしてある。
そのままでは、読みにくいと思い、Amazonのkindleにアップすることを試みた。kindleなら、ページをめくるように読むことができる。Kindleのプレビューアーでは、日本語のPDFを受け付けないので、kindleのComic Creatorで作成したところ、簡単に受け付けてくれた。文章だけならwordもプレビューアで作成できるのであるが、図表があり、これをマニュアルをもとに作るとなると、馴れが必要であり、そのため、代行サービスのページが用意されている。代行を利用してコストをかけるのもばかばかしく思い、試しにComic Creatorを使ってみたらうまくいった。英語等であれば、こんなことはしなくて済んだわけで、日本語文化にはマイナスである。
無料でもいいのであるが、手続きが面倒なようで、1ドルにした。書籍コードは不要である。国際的であるから日本の書籍コードなど無意味なのであろう。その分コストが抑えられる。国会図書館への献本は、私の場合は日本法にも従わないといけないのであろうが、これから考えることにしてある。電子出版が主流になると、この点も問題になるであろう。
国会図書館への納本は、HPをみたら、制度が記述されていた。納本のページがあり、さっそく納本手続きをとった。こちらから送信した情報に基づき、国会図書館のほうから、人流観光研究所のHPを訪問し、ダウンロードするようである。
関連記事
-

-
観光行動学研究に必要なこと インタラクションの認識科学の理解
ミラーニューロンを考えると、進化の過程で人間が人間をみて心を想定するように進化したとおもっていたか
-
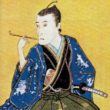
-
『眼の神殿 「美術」受容史ノート』北澤憲昭著 ブリュッケ2010年 読書メモ
標記図書の存在を知りさっそく図書館から借りてきて拾い読みした。 観光資源の文化資源、自然資源という
-

-
『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.h
-

-
観光資源としての「隠れキリシタン」 五体投地、カーバ神殿、アーミッシュとの比較
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産登録された。江戸時代の禁教期にひそかに信仰を続け
-

-
学士会報第20回関西茶話会「新興感染症の脅威と現代世界」光山正雄
感染症は今も世界の人々の死因第一位 歴史上の重大感染症 ①ペスト 14世紀 欧州で大流行 当時の
-

-
「旅館の諸相とその変遷について」「近代ホテルにおける「和風」の変遷とその諸相」を読んで
溝尾良隆立教大学名誉教授が中心となっている観光研究者の集まりが7月8日池袋で開催された。コロナ後の久
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-

-
ウェアラブルデバイスを用いた観光調査の実証実験
動画 https://youtu.be/Sq4M3nvX6Io 10月29日にg-コンテン
-

-
『仕事の中の曖昧な不安』玄田有史著 2001年発行
書評ではなく、経歴に関心がいってしまった。学習院大学教授から東京大学社研准教授に就任とあることに目
- PREV
- 『脳の誕生』大隅典子 Amazon書評
- NEXT
- ウェストファリア神話
