CNN、BBC等をみていて
公開日:
:
観光学評論等
誤解を恐れず表現すれば、今まで地方のテレビ番組、特にNHKを除く民放を見ていて、東京のニュースが地方に垂れ流されているという印象を強く持っていた。
そのうえで、一定の時間帯で、地方ネタが流されるのであるが、他地域から来た者にとって、興味のない暇ネタにしか思えなかった。学校新聞の延長にうつったのである。
地域のものだけ日本人受けているというネタであり、そこには、無理やり作った地元のプライドという印象が強く出て、普遍性に欠けるものがあった。
今そのことを、東京のキー局を見ていてあらためて思うようになっている。ほとんど地上波のテレビを見なくなったが、それでも時折ネット等で飛び込んでくる。
しかし、話題が、自動運転車、ライドシェアや観光といった私の専門に限らず、北朝鮮等の問題でも、グローバルな話題が飛び込んでくるCNN、BBC等比較すると、
これまで地方もローカル局に抱いていた印象を、当局のキー局に抱くようになってきた。
おそらく、朝日新聞、NHKといった日本のメディアが国際化してゆかなければ、この問題は解決しないのであろうが、朝日等が国際化すれば、日本のメデャアといえるかという問題にもなる。
中国と異なって、日本を中心とした社会が、日本語を使う日本人以外の存在があまりに少なかった。日本のメディアも日本語バリアで仲間内で競争していればよかった。しかし、、情報や物流、人流の世界でこれだけグローバル化してゆけば、メディアもそうはゆかないであろう。産経新聞等の存在も、ネットのニッチな世界での生き残りでしかなくなり、マスメディアとしての存在は、国産で一つ残れるか否かということになるのであろう。NHKワールドも、日本のニュースの英語翻訳版から脱局しなければならない。
このことは、観光宣伝においても同じであり、外国人誘致の掛け声は一段と大きくなっているが、その宣伝は学校放送の域を出ることができないのも、国産国際メディアが存在しないことに起因するのかもしれない。
関連記事
-

-
『訓読と漢語の歴史』福島直恭著 観光とツーリズム
「歴史として記述」と「歴史を記述」するの違い なぜ昔の日本人は、中国語の文章や詩を翻訳する
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
-

-
観光学が収斂してゆくと思われる脳科学の動向(メモ)
◎ 観光学が対象としなければならない「感情」、「意識」とは何か ①評価をする「意識」とは何か
-

-
「観光をめぐる地殻変動」-観光立国政策と観光学ー石森秀三 を読んで
学士會会報2016年ⅳに石森秀三氏の表題記事が出ていた。論調はいつものとおりであり驚かなかったが、感
-

-
日本の観光ビジネスが二流どまりである理由
日本の観光ビジネスが二流どまりになるのは、人流に関する国際的システムを創造する姿勢がないからです。
-

-
田口亜紀氏の「旅行者かツーリストか?十九世紀前半フランスにおける“touriste”の変遷」(Traveler or “Touriste”? : Distinctions in Meaning in Nineteenth Century France)共立女子大学文芸学部紀要2014年1月を読んで
2015年4月15日のブログに「羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作
-

-
若者の課外旅行離れは本当か?観光学術学会論文の評価に疑問を呈す
「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍が
-

-
人流抑制に関する経済学者と感染症学者の意見の一致「新型コロナ対策への経済学の貢献」大竹文雄 公研2021年8月号No.696を読んで
公研2021年8月号No.696にコロナ関連の有識者委員等である、行動経済学者大竹文雄氏の「新型コ
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-
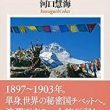
-
河口慧海著『チベット旅行記』の記述 「ダージリン賛美が紹介されている」
旅行先としてのチベットは、やはり学校で習った河口慧海の話が頭にあって行ってみたいとおもったのであるか


