『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.htm
エコツーリズムに対する批判は強烈である。
p161では、熱帯林地区ではツーリズムは野生生物保全手段にはなっても、伐採にかわりうる大規模な経済資源にはなり得ないと記述する。
欧米主導型で作られてきた昨今の「エコ」ツーリズムは、一体どこまで環境配慮型といえるのか、写真を撮ることに夢中になる等を「エゴ」ツーリズムと批判する。
私も観光は本質的に環境破壊であり、両立しないということを認識すべきであると思っているので共感を覚える。環境が大事なら観光はあきらめるべきである。両者を調和させることは観光側からはできない。別の次元で考えるべきでエコツーリズムなどというどこに調和点を求めれるべきかわからない考え方は中止すべきであろうと思っている。
同じことは文化の保護にも言える。先住民への影響は、「定住化と貨幣経済」「近代教育と宗教」だと厳しく氏は指摘する
p133で、ピグミーのショーのことを紹介し、入場料はほとんど酋長のもとに集まってしまうことを記述している。
アイヌの「七五郎沢の狐」はピグミーとテーマが共通
日本人の三味線撥へのこだわりがマルミミゾウの捕獲につながることも指摘。
ガボンでのザトウクジラ捕獲数確保のため、JICAプロジェクトが国際協力を実施し、商業捕鯨が継続している。
世界動物園水族館協会は日本動物園水族館協会にイルカショーの廃止を推奨したところ、いくつかの水族館が日本動物園水族館協会を脱会 。しかし、イルカはストレスがたまり一、二年で死亡してし
関連記事
-

-
国立国会図書館国土交通課福山潤三著「観光立国実現への取り組み ―観光基本法の改正と政策動向を中心に―」調査と情報554号 2006.11.30.
加太氏の著作を読むついでに、観光立国基本法の制定経緯についての国会の資料を久しぶりに読んだ。 そこ
-

-
日本の観光ビジネスが二流どまりである理由
日本の観光ビジネスが二流どまりになるのは、人流に関する国際的システムを創造する姿勢がないからです。
-

-
『結婚のない国を歩く』モソ人の母系社会 金龍哲著
https://honz.jp/articles/-/4147 書によれば、「民族」という単
-

-
1932年12月16日『白木屋の大火始末記』
関東大震災の始末が終了したころ 地下三階地上七階建てデパートの4階から出火 クリスマスツリーの豆電
-

-
『物語 ナイジェリアの歴史』島田周平著 中公新書
アマゾン書評 歴史家トインビー曰く、アフリカはサハラ砂漠南縁を境に、北のアラブ主義
-
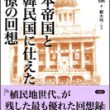
-
任文桓『日本帝国と大韓民国に仕えた官僚の回想』を読んで
まず、親日派排斥の韓国のイメージが日本で蔓延しているが、本書を読む限り、建前としての親日派排除はなく
-

-
『近世旅行史の研究』高橋陽一 清文堂出版 宮城女子学院大学
本書の存在を知り港区図書館の検索を探したが存在せず都立図書館で読むことにした。期待通りの内容で、
-
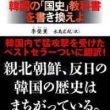
-
書評『大韓民国の物語』李榮薫
韓国の歴史において民族という集団意識が生じるのは二十世紀に入った日本支配下の植民地代のことです。
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代


