田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き
http://diamond.jp/articles/-/166765?page=3
真珠湾攻撃の前、陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
こうしたことは日本だけではない。どの国の軍も巨大な官僚機構で、組織の防衛と面目の維持を第一としがちだから、そのために部隊を犠牲にすることが起こる。最も顕著な例は、第1次世界大戦末期のドイツ海軍だ。敗色濃い中、巨費を投じた「大海艦隊」は出動すれば英海軍に撃滅されるのは必定だったから、港内に引きこもっていた。だが、海軍首脳部はあえて出動を命じ最期を飾ろうとした。無駄死にをさせる出動命令に水兵たちは反乱を起こし、これが全国に波及して革命となり、ドイツ皇帝はオランダに亡命した。
制空、制海権が十分に確保されない場合、「水陸機動団」が出動しなくても、メディアや政治家はそれを「臆病」と非難しないよう、気を付けねばならない。一方、制空、制海権が確立していれば、まず相手は攻めて来ないし、仮に上陸しても、補給が切れて立ち枯れになるのを待てばよい。この場合にも「水陸機動団」の出動を急がせるのは、無駄に死傷者を出すだけで愚策だ。どちらに転んでも「水陸両用団」の創設は無駄と考える。そもそもどうして「水陸機動団」が作られることになったのか。
陸上自衛隊が「南西諸島防衛」を主張し始めたのは、ソ連の崩壊後だ。 それまではもっぱらソ連軍の北海道侵攻への対処を主眼としていたが、その可能性が消えたため、大幅削減の“危機”に直面した陸上自衛隊は次の存在目的を南西諸島に求めた。
当初、海上、航空自衛隊では「陸上自衛隊は苦しまぎれにそんなことを言い出した」と冷笑し、「対艦ミサイル・ハープーン搭載の潜水艦を1隻出しておけば十分ですよ」とか、「航空優勢さえ確保すれば相手は来られませんよ」との声を当時、よく聞いた。 だが、「南西諸島防衛に必要」と言えば、海上、航空自衛隊も予算が取れる、と分かってそれに便乗し始めた。
旧ソ連の潜水艦を主敵と見てきた米海軍と海上自衛隊はその探知の経験を積み、装備を開発してきたから、対潜水艦能力では中国と大差がある。 小型の空母よりはるかに建造費用は安く、人員も少ない潜水艦に力を入れる方が合理的だろう。
日本が小型空母2隻「いずも」「かが」を持てば、イギリスが建造中の「クィーン・エリザベス」級(6万5000トン)2隻にははるかに及ばなくても、「海軍国」としての外見を備えることにはなるだろう。 だがそれが実際に活動するのは、おそらく米海軍の空母戦隊が中東などに出勤する際、その助手として付いて行く程度になるのではないか、と思われる。
関連記事
-

-
『旅行契約の実務』 鈴木尉久著2021年 民事法研究会発行
旅行業法の解釈について、弁護士でもある鈴木教授がどのような見解を持っておられるかと本書を図書館で
-
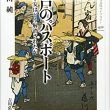
-
『江戸のパスポート』柴田純著 吉川弘文館
コロナで、宿泊業者が宿泊引き受け義務の緩和に関する政治的要望を行い、与党も法改正を行うことを検討
-

-
三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』なぜ日本に資本主義が形成されたか
ちしまのおくも、おきなわも、やしまのそとのまもりなり
-

-
ヨーロッパを見る視角 阿部謹也 岩波 1996 日本にキリスト教が普及しなかった理由の解説もある。
キリスト教の信仰では現世の富を以て暮らす死後の世界はあ
-

-
保護中: 蓮池透『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』
アマゾン書評 本書を読むに連れ安倍晋三とその取巻き政治家・官僚の身勝手さと自分たちの利権・宣伝
-
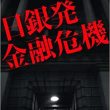
-
英国通貨がユーロでない理由 志賀櫻著「日銀発金融危機」
ポンド危機と英国通貨がユーロでない理由 サッチャー政権
-

-
保護中: 『市場と権力』佐々木実を読んで
日銀が量的緩和策で銀行に大量にカネを流し込んだものの、銀行から企業への融資はそれほど増えなかった。
-
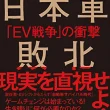
-
『日本車敗北』村沢義久著 アマゾンの手厳しい書評
車の将来の議論の前提に、地球温暖化への見解 ガソリン車 電気自動車 エンジンではな
- PREV
- 『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』川添愛著
- NEXT
- 民泊仲介業標準約款への疑問


