『日本が好きすぎる中国人女子』桜井孝昌
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
出版・講義資料
内容紹介
雪解けの気配がみえない日中関係。しかし「反日」という一般的なイメージと、中国の若者を知り尽くした著者の印象はまるで違う。中国人女子たちがいま愛してやまないもの。それはアニメやマンガ、J-POPなどの日本文化なのだ!
残念ながら当の日本人がその事実に気づかないうちに、韓国のポップカルチャーが勢力を急拡大。「クール・ジャパン」が提唱されてから久しいが、いったい問題はどこにあるのか。
日本のメイドカフェに憧れ、「早くOTAKUになりたい! 」と叫ぶ中国人女子の気持ちを知ってこそ、新しいビジネスチャンスは見出せる。文化外交の第一人者が届ける渾身の現地レポート。
内容紹介
中国の大学で日本語を学ぶのは女子ばかり
「カワイイ」と「萌え」が日本の象徴
なぜ中国人女子はメイドになるか?
現在のクール・ジャパン政策は死角だらけ
日本全体へのポップカルチャー教育がいまこそ必須
アマゾン書評
報道は全く触れないが、中国には、実は多くの熱烈な親日家がいる。彼女たちの意見や日常を生で聞くことが、ビジネスチャンスにつながるだけでなく、日中関係の改善に役立つ、という著者の主張はよく理解できた。
ただ、昨年の反日暴動で報じられたような、日本を憎んでいる愛国者「も」大勢いることや、彼らを恐れた日本企業が、中国へ進出しにくくなっていることについて、「日本が好きすぎる中国人女子」や著者がどう考えているのかについて、言及があまりないのが残念だった。日本文化を享受することで、彼女たちは身の危険を感じたりしないのだろうか。
悲観的すぎる発想かも知れないが、筆者を含めた日本人が、ビジネスや文化交流を名目に、日本を愛してやまない多くの宅男や腐女に会ったとしても、日中の溝は、危機管理上、意識せざるを得ないだろう。なにせ、日本人が紛争地域に乗り込んでボランティア活動をしていたとき、テロリストに拉致され殺された場合、殺したテロリストよりも、本人の危機管理能力の無さが咎められるという、自己責任の世界である。
日本への愛憎渦巻く中国で、火中の栗をどうやって拾うのか。悩ましいところであり、そこについて突っ込んだ考察がほしかった。本書にある通り悲観的になっても事態は前進しないが、手放しに楽観もできない。
中国のファッション界では「カワイイ」「萌え」の「日式」が「カッコいい」「韓式」と覇を競っているらしく、日本のファッション誌も大いに売れているという。
ところが、である。韓国企業が韓式ファッションを高値で売りまくっているのに対して、日式の店に並んでいるのは「安いバッタもん」ばかり。なんでやねん?
簡単な話で、「韓国人は来る。でも日本人は来ない」。これが著者には歯がゆくてしかたがない。だから、「今こそ日本企業は海外へ打って出よ」「今しかチャンスはない」と連呼することになる。
邪推するに、著者がいちばん歯がゆいのは、「日本経済再生」を謳い「日本企業」の尻を叩かなければならない自分自身の立場ではないか。
だいたい、「日本企業」なんてのは、既に海外で負けてきた連中だ。日本のポップカルチャーで部屋中いっぱいの中国人女子だって、テレビとケータイとパソコンは韓国製じゃないか。
日本を愛してやまない海外の日本ファンが心の底から欲しがっているものを作っているのは「日本企業」ではない。中小零細団体か個人、下手をすればただの素人だ。「早急な収益モデルの再構築」は必要だが、「それは産業構造や既得権に大きな影響を及ぼ」してしまうのだ。これからのアイデアを考えることができるのも、これまで「業界を発展させてきた人たちより」別の人たちなのだ。過去の栄光にしがみついているだけの「業界団体」や「伝統文化」の人では決してない。
「日本企業」なんかアテにする必要はない。筆者自身、自分ひとりでも海外に打って出るし、できることからどんどん始めてしまっている。
行けば出会える。「日本の魅力を発見しては、次から次に発信しつづけてくれている」「宝物のような存在」に。
出会えばわかる。「日本のファッションを心から着てみたいと憧れている」海外の女子たちの気持ちが。
「カワイイ服を着ると、それだけでポジティブな気持ちになれる」、日本がそんな自己演出を応援できるなら、こんな素晴らしいことはない。
「中小企業だからとか、東京にいるから世界に訴えることはできないということは、まるでない」。日本人一人ひとりができることは、多いはずなのだ。って、しょうがないからWeibo覗いてみようか。
程度の差はあれ、日本のポップカルチャーが世界各国の若者に受け入れられ、日常的に接する機会の乏しい日本の大人達の想像以上の「日本好き」な人達を誕生させているのは事実であり、喜ばしいことだ。それは、世界各地のアニメやマンガの催事の動員力が証明しているし、中でもパリで開催されている「ジャパンエキスポ」は今年は4日間で23万を動員し、映像を観ても活況を呈している。最近では、アニメやマンガに触発され、JポップやJロックにも注目が集まり、昨年から今年にかけてL’arc en cielやキャリーパミュパミュ、Perfumeなどが海外公演を成功させている。多くのファンは、日本のアニメやマンガなどを体験し、大人になるまでの「通過儀礼」になっているのではないかと想像されるが、その背景の下で、この本の著者も指摘している通り、you tubeなどのインターネットを通じた新しいメディアが強烈な伝播力を持っていることも影響しているだろう。何せ、キャリーパミュパミュの出世作「ポンポンポン」はyoutubeで5600万回も再生されている。勿論、日本やアジアからのアクセスが多い、AKBなどには及ばないが、特に、欧米を中心に世界的な広がりと言う点では評価されるのではないだろうか。
さて、本書では中国における大学生を中心とした「日本好き」の実態が報告されている。日本のマスメディアは、中国と言えば、尖閣の領土問題や何度も繰り返され歴史認識、あるいは中国内部の権力闘争や最近では、シャドウバンキングの問題、あるいはPM2.5などの汚染問題など、どちらかと言えば硬派の報道ばかりで、中国の若者の日常や意識などはほとんど報道されることが無い。その意味で、このレポートはとても興味深く、少しは希望ももてる話ではあった。しかしながら、いくら「日本が好きすぎる女子」が多くいるからといって、中国における日本企業のビジネスがもっとうまく行くはずだ、要は韓国と比べて「本気度」が足りないからうまく行かないのだ、と著者が結論づけるほど事は簡単ではないのではないか?若い女子に限らず「日本好きの一定のマーケット」が存在することとは重要であるが、企業側の覚悟や市場へのアプローチの仕方を変えれば、もっとうまく行くはずというレベルを超えた、困難さがあるからこそ、多くの日本企業が中国でのビジネスに「嫌気」を感じ、中国での金銭的な失敗だけで済むならともかく「身ぐるみはがされて」しまっているのが現状だ。著者は何度ももっと「日本が好きすぎる」若者に寄り添えと言う。その事を否定はしないが、そこから現実のビジネスまでの距離をどう埋めればよいのか?日本人のモノづくりの企画力と精神の賜物である商品やコンテンツをあっさりコピーし何とも思わない国民性や法律が機能しない中国で、どうすれば良いのか?「オタクのオタク」氏は答えていない。この本は、参考にはなるだろうが、商売人からすれば無責任なコンサルと変わらないという印象しか持てないのではないかと感じた。
「分析なきトートロジー」が繰り返されているように思え、
発行されてから放置していましたが、
一通り読み終えたいまも同じ感想です。
彼女たちがなぜ「日本」を好きになったのか、
その分析が全くできていません。
「アニメやマンガが好きな人はアニメやマンガが好きなのであり、日本を好きになるわけではない。
だから、伝統文化を海外に発信していくことが、日本への理解には重要なのだ」
という意見を著者は「この考えがいかにまちがいであるか」と主張しますが、
「この考え」は完全な間違いではありません。
京町家に暮らし、日本の漆塗り老舗を率いる英国人社長David Atkinsonさんは、
『身勝手な日本人が、日本の国宝をダメにする』というインタビューの中でこう語っています。
「2000年の歴史がある国で感動したのが自販機、コンビニ、アニメ、それだけ?
日本の魅力ってこの程度? って思う。見てると悲しくなるんですよ」
マンガやアニメは日本の伝統文化と断絶した戦後に形成された無国籍的な文化で、
日本特有の無宗教的価値観(無宗教ではない)を少し継承するのみです。(伝統が新しいということを知らないようだ 町家、瓦屋根の家は新しいものではないか Teramae)
いくら鳥獣人物戯画との関連性を訴えたところで、
日本が現存する世界最古の国家であったり、
世界で初めて人種差別撤廃を提唱した八紘一宇の理念は切断、葬られたままです。
彼女たちはマンガやアニメを通じて日本が好きなのか、
「日本」が好きなのかさえも分析されていません。
文化として見るのか、ビジネスとして見るのかの視点も曖昧です。
「K-POPと韓国製品はつながっている」というのは当たり前の話です。
韓流ブームは韓国製品(サービス)を売るためのマーケティング戦略として、
時の韓国政府・財閥の政策で、
日本人の岩堀利樹さんがコンダクターとなって韓国から仕掛けられたものだからです。
(ただし、現在は日本人の関与を否定)
韓流はそもそもビジネスとして立ち上げられたものであり、
不正なコピーやアップロード・ダウンロードをむしろ歓迎するビジネス・スキームとなっています。
日本のマンガやアニメ、ファッションはビジネスとして中国で成功していないかもしれませんが、
文化の伝播としては十分成功しています。
クール・ジャパンが何を目指しているのかバラバラで、
何をしたいのか全く見えていないのがそもそもの問題であり、
著者の見識不足の所為にできない部分が多いのも事実です。
関連記事
-

-
筒井清忠『戦前のポピュリズム』中公新書
p.108 田中内閣の倒壊とは、天皇・宮中・貴族院と新聞世論が合体した力が政党内閣を倒した。しかし、
-
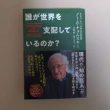
-
ノーム・チョムスキー著『誰が世界を支配しているのか』
アマゾンの書評で「太平洋戦争前に米国は自らの勝利を確信すると共に、欧州ではドイツが勝利すると予測
-

-
『サカナとヤクザ』鈴木智彦著 食と観光、フードツーリズム研究者に求められる視点
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ! アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大
-

-
ゲルニカ爆撃事件の評価(死者数の大幅減少)
歴史には真実がある。ただし人間にできることは、知りえた事実関係の解釈に過ぎない。もっともこれも人間
-

-
「起業という幻想」白水社 スコット・A・シェーン 職を転々として起業に身をやつす米国人の姿は、産学官が一体になって起業を喧伝する日本社会に一石投じることは間違いない。
マイクロソフトのビル・ゲイツ、アップルを立ち上げたス
-
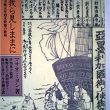
-
書評『我ら見しままに』万延元年遣米使節の旅路 マサオ・ミヨシ著
p.70 何人かの男たちは自分たちの訪れた妓楼に言及している。妓楼がどこよりも問題のおこしやすい場
-

-
聴覚 空間の解像度は視覚が強く、時間の分解度は聴覚が強い。人間の脳は、より信用できる方に重きを置いて最終決定する
人間の脳は、より信用できる方に重きを置いて最終決定する 聴覚が直接情動に訴えかけるのは、大脳皮質
-

-
『1964 東京ブラックホール』貴志謙介
前回の東京五輪の世相を描いた本書を港区図書館で借りて読む。今回のコロナと五輪の関係が薄らぼんやりと


