『セイビング・ザ・サン リップルウッドと新生銀行の誕生』ジリアン・テット 武井楊一訳
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
バブル期の金融問題に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はハゲタカファンド思想で書かれている。これとは対照的に本書は、ファイナンシャルタイムズ東京支社長を2年間務めた30代英国人女性によるもの。本書は、高橋治則イ・アイ・イ社長 大野木克信長銀頭取、八城政基新生銀行頭取の3人を中心に展開されている。高橋氏には、日経新聞の記者に頼まれて、瀬戸大橋開通式に高松出身の義父岩沢靖氏の参加の依頼を受けた時に、その存在をはじめて知った。柿の木坂の自宅に行ったとき、車止めの大きさに驚きどう人かと思ったからである。第二部で“ガイジンの襲来”と恐れられた起業再生ファンドリップルウッドが長銀を買収した舞台裏が描かれている。リスクが多い長銀を引き継ぐには、米国、韓国等での金融の売却に際に知られているロスシェアリングを用い、将来的に資産が不良化した場合に売り手と買い手が応分に負担することを約束することが合理的である。しかし90年代半ばの住専問題でこの流儀を採用して悲惨な結果に終わった日本政府は、のちに激しい批判を浴びた「瑕疵担保条項」を提案した。この仕組みはコストが膨大なものになる可能性があり、日本政府は物事をただただ引き延ばすという風潮だと記述されているが、それはコロナ禍でも変わっていない。第三部では、アメリカ流の経営手法を大幅に取り入れた新生銀行が、「そごうショック」や金融庁との闘いを乗り越えてIPO(新規株式公開)を果たすまでの歩みを検証している。インドの会社が販売するシステムを採用し、米国デルの廉価なコンピュータを購入したおかげで、邦銀が投資する額の10分の1の60億円でITシステムを変えることができた。みずほ銀行がいまだにトラブルを抱えているのとは好対照である。そごうの破たんは私にも現場感覚がある。JR東に出向中、立川の駅ビルに百貨店を設立する業務に携わり、そごう百貨店の人たちにいろいろ教わった経験があるからである。日本の私鉄系百貨店が、鉄道側から破格の賃料より成り立っていることも知った。そごうに瑕疵担保条項を使用することを日本政府は嫌っていた。国民が嫌うからであり、といって放置することも国民は嫌うのである。ハゲタカファンドや竹中平蔵嫌いの風潮は今でも継続している。
関連記事
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
-
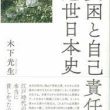
-
『貧困と自己責任の中世日本史』木下光夫著 なぜ、かほどまでに生活困窮者の公的救済に冷たい社会となり、異常なまでに「自己責任」を追及する社会となってしまったのか。それを、近世日本の村社会を基点として、歴史的に考察
江戸時代の農村は本当に貧しかったのか 奈良田原村に残る片岡家文書、その中に近世農村
-

-
『結婚のない国を歩く』モソ人の母系社会 金龍哲著
https://honz.jp/articles/-/4147 書によれば、「民族」という単
-
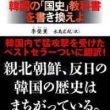
-
書評『大韓民国の物語』李榮薫
韓国の歴史において民族という集団意識が生じるのは二十世紀に入った日本支配下の植民地代のことです。
-

-
2016年7月29日「ファイナンスの哲学」多摩大学特任教授堀内勉氏の講演を聞いて
資本主義の教養学公開講座が国際文化会館で開催、場所が近くなので参加してみた。 1 資本主義研究
-

-
化石燃料は陸上生物の生息域の保全に役立っている 堅田元喜
https://cigs.canon/article/20201228_5529.html
-
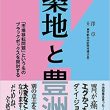
-
『築地と豊洲』澤章 都政新報社
Amazonの紹介では「平成が終わろうとしていたあの頃、東京のみならず日本中を巻き込んだ築地市場の
-
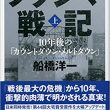
-
『フクシマ戦記 上・下』船橋洋一 菅直人の再評価
書評1 2021年4月10日に日本でレビュー済み国民の誰もがリアルタイムで経験した
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-

-
「太平洋戦争末期の娯楽政策 興行取締りの緩和を中心に」 史学雑誌/125 巻 (2016) 12 号 金子 龍司
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発
- PREV
- 『1964 東京ブラックホール』貴志謙介
- NEXT
- 『セイヴィング・ザ・サン』 ジリアン・テッド


