QUARA コロナ対処にあたってWHO非難の理由にWHOの渡航制限反対が挙げられていますが、これをどう思いますか?
渡航制限反対は主に「中国寄りだから」という文脈で語られています。しかし調べてみれば、今回のコロナウイルスだけでなく、昔の伝染病ブレークアウトもWHOが一様に渡航制限に反対してきたことが分かります。
例えば
2009年のインフルエンザパンデミック
国立感染症研究所の旅行に関するQ&A
WHOはパンデミックインフルエンザ(H1N1)2009に関して渡航制限を設けていない。
パンデミックインフルエンザウイルスはすでに世界中に存在する。拡散防止のために国際的な渡航を延期することを指示する科学的根拠はない。世界各国は、予防手段、適正な医療機関への平等なアクセス、そして公衆衛生的な対応計画を開始しようとする国々を支援することでウイルスのインパクトを最小限にとどめることを最大の目的としている。
2014年のエボラ
世界保健機関(WHO)は23日、西アフリカで感染が拡大しているエボラ出血熱について、専門家による緊急委員会が「渡航や貿易の禁止はすべきでない」と改めて強調したと発表した。渡航や貿易の禁止は感染国の経済を悪化させ、不法な出入国が増えて一段の感染拡大につながるとみている。米国などで渡航禁止を求める声が出ているのにクギを刺した格好だ。
また、渡航制限はブレークアウトした国にマイナスな影響をもたらす一方、それだけで伝染病の拡大防止に役立つ根拠があんまりありません。
上記国立感染症研究所のQ&Aで、渡航制限についてこんなことも言いました。
科学的研究に基づいた数理モデルの結果では、渡航制限による感染拡大防止効果はほとんど、あるいは全くないとなっている。過去のパンデミックインフルエンザやSARSがこのことを立証している。
マイナスな影響について、上記エボラに関する記事も言及しましたね。
渡航や貿易の禁止は感染国の経済を悪化させ、不法な出入国が増えて一段の感染拡大につながるとみている。
感染が集中的に起きた3カ国では、航空便の運航中止などの影響で経済状態が急速に悪化。支援もしにくくなったとされる。また、食料調達にも支障が出始めている。
また下記は米国の外交問題評議会の傘下組織が、今まで中国へ渡航制限をかけた国とかけてない国の感染状態を追跡してまとめた画像です。
赤い線はかけた国を意味し、青い線はかけてない国を意味します。
感染人数を比べる場合
百万人当たりの感染人数を比べる場合
Tracking Coronavirus in Countries With and Without Travel Bans | Think Global Health
渡航制限をかけた国が明らかに感染状態が良いということはありません、というかかけてない国と分別がつかないような状態です。
これについて、レポートは幾分遅らせることが可能だが、「渡航制限により、この新しいコロナウイルスの蔓延を止めることも、パンデミックになることを妨げることもない」と言い切っています。
実際、WHOもただの渡航制限ではなんの効果ももたらさないと警告したことがあります。
世界保健機関(WHO)で緊急事態対応を統括するライアン氏は十六日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、世界各国が相次いで導入している入国制限措置について「包括的な感染拡大防止策の一つにすぎない」と述べ、乱用は避けるよう訴えた。各国が入国制限で満足し、国内での感染拡大防止の取り組みがおろそかになることを懸念した発言。
記者会見でライアン氏は、感染者や感染経路の割り出し、クラスター(感染者の集団)の封じ込めといった感染拡大防止策を並行して行わなければ、渡航制限措置は「何の効果ももたらさない」と強調した。
つまり、WHOは過去の経験や研究から渡航制限に一貫して反対してきたし、実際中国への渡航制限の有無で感染状態が大きく異なったわけではありません。
ただ、過去がそうでも、百年以来のこのコロナウイルスのパンデミックにおいて、渡航制限がどれだけ感染の防止に役立ったかは後で研究が必要でしょうし、それに応じてWHOもやり方を変える必要があるかもしれません。それが人類の知恵や進歩というものですが、今それを特定の国と結びつけて批判するのは、このパンデミックを政治利用する感が否めない、というのが正直なところです。
関連記事
-

-
『婚姻の話』 柳田國男
日本は見合い結婚の国、それが日本の伝統文化である、という説に、柳田ははっきりノーを突き付ける。
-

-
太平洋戦争で日本が使用した総費用がQuoraにでていた
太平洋戦争で、日本が使った総費用はいくらでしょうか?Matsuoka Daichi, 九州大学で経
-
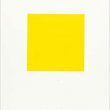
-
書評『日本社会の仕組み』小熊英二
【本書の構成】 第1章 日本社会の「3つの生き方」第2章 日本の働き方、世界の働き方第3章
-

-
『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.h
-
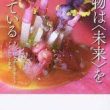
-
保護中: 『植物は未来を知っている』ステファノ・マンクーゾ 、動物が必要な栄養を見つけるために「移動」することを選択。他方、植物は動かないことを選び、生存に必要なエネルギーを太陽から手に入れるこにしました。それでは、動かない植物のその適応力を少しピックアップ
『植物は<未来>を知っている――9つの能力から芽生えるテクノロジー革命』(ステファノ・マンクーゾ著、
-

-
『中国人のこころ』小野秀樹
本書を読んで、率直に感じたことは、自動翻訳やAIができる前に、日本型AI、中国型自動翻訳が登場す
-

-
日経新聞2019年5月18日見出し「池袋暴走の87歳、ミス否定 「ブレーキ踏んだ」説明」へのTanaka Yukoh氏のNewspicksのコメントが秀逸ですが、イイネは少ないです。紹介します。
大変痛ましく残念な事件ですが。ただ、こういうのは御遺族もおられる事ですから、どうぞ冷静に。
-
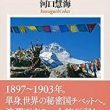
-
河口慧海著『チベット旅行記』の記述 「ダージリン賛美が紹介されている」
旅行先としてのチベットは、やはり学校で習った河口慧海の話が頭にあって行ってみたいとおもったのであるか
-

-
観光学を考える 『脳科学の教科書 神経編・こころ編』岩波書店 理化学研究所脳科学総合研究センター編 をよんで
図書館でこの二冊を借りてきて一気に読む。岩波ジュニア選書だから、子供が読む本だけれど私にはちょうどい
