「温度生物学」富永真琴 学士会会報2019年Ⅱ pp52-62
(観光学研究に感性アナライザー等を用いたデータを蓄積した研究が必要と主張しているが、生物学では温度生物学まで提唱されるように研究が進んでいる。人を移動させる刺激には、避暑避寒もあり温度も大きな要素である。温度による観光需要の変化等を実証的に研究したものは、まだ知らないから、若手研究が手掛けるといいと思う。)
以下表記論文のメモ
環境温度の感知は生存にとって重要機能
温度受容に係る研究は責任因子である温度センサーが不明なまま長らく続いてきた
温度感受性分子としてカプサイシン受容体TRPV1チャンネルがクローニングされ、一気に研究が進んだ
感覚神経で環境温度を感じるためには環境温度刺激が電気信号に変換されなければならない
温度感受性TRPチャンネル
1997年にラット感覚神経から哺乳類で初めて温度で活性化されるセンサー分子としてTRPV1が発見された
TRPチャンネルは、ヒトや鳥類、線虫などにおいて視覚、味覚、臭覚、聴覚、触覚、温覚、その他様々な物理・化学刺激の受容に極めて重要であることが分かっている
温度感受性TRPチャンネルの構造が原子レベルで明らかにされてきたが、未だに温度がどのようにしてチャンネル開口をもたらすかは明らかでなく、細胞膜脂質の関与が示唆されている。
TRPV1は43度という私たちの身体に痛みをもたらす熱という物理刺激のみならずカプサイシンを含む辛み物質(化学刺激物質)で活性化され、それらの刺激に相乗作用がある。暑くて辛い物をより辛く感じる。体温変化は起こらず感覚神経をだますようにして、温度感覚をもたらす。
温かいと甘みが増す現象や体温が高いと免疫機能が維持される現象等に関わっている。
現在の脊椎動物の温度感受性TRPチャンネルの基本的なレパートリーは脊椎動物の初期の時点ですでに備わっていた
温度を化学シグナルとは異なる「温度シグナル」として捉える考え方が提唱され「温度生物学」は生物学研究の一つの大きな方向である
関連記事
-

-
『平成経済衰退の本質』金子勝 情報、金、モノ、ヒト、自然 について、グローバリゼーションのスピードが違うことを指摘 情報と人流のずれが、過剰観光
いつも感じることであるが、自分も含め観光学研究の同業者は、研究原理を持ち合わせていないということ
-
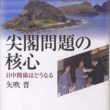
-
『尖閣諸島の核心』矢吹晋 鳩山由紀夫、野中務氏、田中角栄も尖閣問題棚上げ論を発言
屋島が源平の合戦の舞台にならなければ観光客は誰も関心を持たない。尖閣諸島も血を流してまで得るもの
-

-
保阪正康氏の講演録と西浦進氏の著作物等を読んで
日中韓の観光政策研究を進める上で、現在問題になっている「歴史認識」問題を調べざるを得ない。従って、戦
-

-
何故日米開戦が行われたか。秋丸機関の報告書への解説 『経済学者たちの日米開戦』
書名は出版社がつけたものであろう。傑作ではある。書名にひかれて読むことになったが、およそ意思決定
-

-
『サイロ・エフェクト』ジリアン・テット著 高度専門化社会の罠
デジタル庁が検討されている時期であり、港図書館で借りて読む。本書は、NYCのデータ解析により、テ
-

-
ハーディ・ラマヌジャンのタクシー数
特殊な数学的能力を保有する者が存在する。サヴァンと呼ばれる人たちだが、どうしてそのような能力が備わ
-

-
『総選挙はこのようにして始まった』稲田雅洋著 天皇制の下での議会は一部の金持ちや地主が議員になっていたという通説が実証的に覆されている。いわば「勝手連」のような庶民が、志ある有能な人物(国税15円を納める資力のない者)をどのような工夫で議員に押し立てたかを資料に基づいて丹念にドキュメンタリー風に解説
学校で教えられた事と大分違っていた。1890(明治23)年の第一回総選挙で当選して衆議院議員にな
-
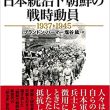
-
コロニアル・ツーリズム序説 永淵康之著『バリ島』 ブランドン・パーマー著『日本統治下朝鮮の戦時動員』
「植民地観光」というタイトルでは、歴史認識で揺れる東アジアでは冷静な論述ができないので、とりあえずコ
-

-
南米「棄民」政策の実像 遠藤十亜希著 岩波現代全書 最も南米移民を排出したのが最貧困地帯たる東北ではなく北部九州~山陽ラインだったのは何故か?
19世紀末から20世紀半ばまで、約31万人の日本人が、新天地を求めて未知の地ラテンアメリカに移住
-
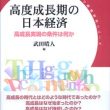
-
『高度経済成長期の日本経済』武田晴人編 有斐閣 訪日外客数の急増の分析に参考
キーワード 繰延需要の発現(家計ストック水準の回復) 家電モデル(世帯数の増加)自動車(見せびら
- PREV
- Nikita Stepanov からの質問
- NEXT
- human geography

