『中国人のこころ』小野秀樹
本書を読んで、率直に感じたことは、自動翻訳やAIができる前に、日本型AI、中国型自動翻訳が登場するのだろうということである。言葉がコミュニケーションの手段であるのであるから、コミュニケーションの取り方が異なれば、伝わり方も変わるわけで、ニーハオとコンニチハは誰が使っているかで違ってくる。AIにはそれがすべてわかるはずがないわけで、中国人用のAIと、日本人用のAIでは違うということである。それは、AIが人間にとって代われないのではなく、人間がする誤解をAIも同じようにするものまでは実現するが、それ以上のものはないということなのである。
日本人「あなたたちは、いま何時だかわかっているのか!?」 中国人「……夜の2時半です」
日本人バスガイドさん「皆さま、お疲れ様でした」 中国人観光客「いえ、私は別に疲れていません……」
上記のような「噛み合わない」やり取りは、今日もまたどこかの日本人と中国人との間で交わされているに違いない。
それではなぜ、こうした誤解やすれ違いが生じてしまうことになるのだろうか?
その答えのカギは、日本語と中国語のそれぞれの「ことば」がもつ特質と、それぞれの発想法の違いにあるのだという。
本書は、30年以上にわたり中国語を研究してきた著者が「言語」を切り口にして、
日本との比較を行いながら中国人に特有の思考様式や価値観について分析・紹介した、思わず笑える知識が満載のユーモア溢れる言語文化論である。
グローバル化が進み、中国人との日々の接点が増えている現代日本人にとって、必読の一冊だ。
【中国人の特徴を示すエピソード】 ( 本書内容より一部を抜粋 )
●定番の挨拶と思われている「你好(二―ハオ)」は、実はごく限られた場面や相手にしか使わない
●タテ社会ゆえ、人の呼び名にとりわけ細かい神経を使う
●「身内」か否かによって、その相手に対する態度がまったく違う!
●日本人に「いつもお世話になっております」と言われると、「世話をした覚えは無いのに……?」と反応に困ってしまうことも
●数字の験担ぎにとにかくこだわる
→最強のラッキーナンバー「99999」が付いた自動車のプレートが、なんと単体で5000万円で落札!!
●手土産はとにかく「大きさ」「豪華さ」が重要という文化
●ご馳走をするときは渋くて上品な和食料亭よりも、明るくて賑やかなファミレスがウケることも
●初対面の相手には「収入」を訊くのが定番だが、それはなぜか?
関連記事
-
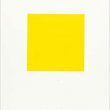
-
書評『日本社会の仕組み』小熊英二
【本書の構成】 第1章 日本社会の「3つの生き方」第2章 日本の働き方、世界の働き方第3章
-

-
ゲルニカ爆撃事件の評価(死者数の大幅減少)
歴史には真実がある。ただし人間にできることは、知りえた事実関係の解釈に過ぎない。もっともこれも人間
-

-
1932年12月16日『白木屋の大火始末記』
関東大震災の始末が終了したころ 地下三階地上七階建てデパートの4階から出火 クリスマスツリーの豆電
-

-
ニクァラグア手話 聴覚障害の子どもたちが手話を作り出すまで
https://youtu.be/qG2HjmG0JGk https://www.bbc
-

-
『時間は存在しない』カルロ・ロヴェッリ
『時間は存在しない』は、35か国で刊行決定の世界的ベストセラー。挫折するかもしれないので、港区図書
-

-
世界人流観光施策風土記 チベット旅行の検討から見えてきたこと
物流行政をしていたころ、港湾運送事業者が、貿易手続きが複雑なことが自分たちの仕事が存在する理由だとし
-

-
書評 AIの言語理解について考える」川添愛 学士会報940号P.42
分類がわかりやすい 1 今のAIは人間の言葉を理解している。 理解
-

-
Quora 古代日本語の発音
youtubeで、「百人一首を当時の発音で朗読」という動画を見ました。奈良・飛鳥時代の上代日本語
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
人口減少の掛け声に対する違和感と 西田正規著『人類史のなかの定住革命』めも
多くの田舎が人口減少を唱える。本気で心配しているかは別として、政治問題にしている。しかし、人口減少と

