書評『人口の中国史』上田信
中国人口史通史の新書本。入門書でもある。
概要
〇序章 人口史に何を聴くのか
マルサスの人口論
著者の「合散離集の中国文明サイクル」説。「合」は安定段階。「散」は求心力の低下。「離」新しい文明を担う可能性のある者同士の争い。「集」は一つの可能性が生き残り、全体を統合。
〇第一章人口史の始まりー先史時代から紀元後2世紀まで
東ユーラシアの一角に生まれた中国文明。
紀元2年の漢代に初の人口統計。戸数1225万、口数6000万弱。
〇第二章人口のうねりー2世紀から14世紀前半まで。
晋朝では戸数250万と減少。実際にはもっと多かった。
隋では戸数900万、総人口4600万人。華中の人口が増加。
唐朝の752年調査で、戸数890万戸、人口5200万人。
1210年の宋朝+金朝で、戸数2193万と増加。
〇第三章人口統計の転換ー14世紀後半から18世紀。
1741年清の乾隆帝が保甲制度による厳密な人口調査を指示。この年の民数(人口)1億4300万。
〇第四章人口急増の始まりー18世紀
以下後述。
〇第五章人口爆発はなぜ起きたのかー歴史人口学的な視点から。
〇第六章人口と反乱ー19世紀
〇終章現代中国人口史のための序章
私的感想
〇第一章から第四章までは、一般的な中国史事実に、人口動態の変化を加えたような叙述で進行していく。これが、第五章の「人口爆発はなぜ起きたのかー歴史人口学的な視点から」に入ると、世界が変わり、見たことのない世界に突入したようで、一気に面白くなる。
〇十八世紀の中国人口爆発(爆増)の原因として
☆まず、人頭税の廃止によって、隠された人口が表面に出てきた。→これは一時的な影響にすぎない。
☆ジャガイモ、トウモロコシの栽培の普及→これも一時的な人口増にとどまる。
☆族譜を調査し、推測していくと、1740年以降、生まれた子供の中の女児の比率は上がっている。これは「溺女」が減少したことが原因と考えられる。
☆溺女は女児が生まれてくれば水に浸けて間引いてしまう風習で、貧しい家では広く行われていた。皇帝はこれを禁止し、地方高官も布告を出したが、なかなか減らなかった。しかし、この時代は親戚姻戚からの嬰児援助も行われるようになり、「溺女」が減ってきた。「溺女」の減少は人口増加と関連する。
〇貨幣経済の普及も「溺女」の減少と関連する。すなわち、貨幣経済の普及は貧しい農民を直撃し、貧しい独身男性は職を求めて、地域の外に出ていった。その結果、比較的豊かな男性が残り、女性は余裕のある男性と結婚し、女児でも育てられるようになり、溺女は減少した。
〇「第六章人口と反乱ー19世紀」は地域を出ていった独身男性その後で、引き続き面白い。彼らは木廠や鉄廠で賃金労働の従事し、結婚できないまま、新興宗教に心の支えを求めていき、白蓮教、太平天国等の反乱に参加していく・・。
私的結論
〇後半は、中国史の別世界に連れていかれて、大変面白かった。
〇「合散離集の中国文明サイクル」説はちょっとこじつけのような・・すみません。
関連記事
-
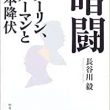
-
歴史認識と書評『暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏 』長谷川毅
日本降服までの3ヶ月間を焦点に、米ソ間の日本及び極東地域での主導権争いを克明に検証した本。
-
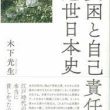
-
『貧困と自己責任の中世日本史』木下光夫著 なぜ、かほどまでに生活困窮者の公的救済に冷たい社会となり、異常なまでに「自己責任」を追及する社会となってしまったのか。それを、近世日本の村社会を基点として、歴史的に考察
江戸時代の農村は本当に貧しかったのか 奈良田原村に残る片岡家文書、その中に近世農村
-
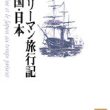
-
書評『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳
日本人の簡素な和式の生活への洞察力は、ベルツと同じ。宗教観は、シュリューマンとは逆に伊藤博文等が
-

-
『近世旅行史の研究』高橋陽一 清文堂出版 宮城女子学院大学
本書の存在を知り港区図書館の検索を探したが存在せず都立図書館で読むことにした。期待通りの内容で、
-

-
動画で考える人流観光学 観光活動論 訪問者数の推移
https://fb.watch/kEjmTswC1L/?fs=e&s=cl
-
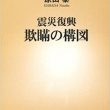
-
GOTOトラベルの政策評価のための参考書 『震災復興 欺瞞の構造』2012年 原田泰 新潮文庫
いずれ、コロナ対策としてのGOTOトラベル等の観光政策の評価が必要になると思い、災害対策等の先例を
-

-
田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き
-

-
Quora 英語は文字通り発音しない単語が多い理由は、ペストの流行が原因?
Shiro Kawaiさんの名回答 1400年頃までの中英語(Middle English)
-

-
国際収支の理解 インバウンド好調の原因
それでも円高にならないのはなぜか?「売った円が戻ってこなくなった」理由 https://www.
-

-
『中国人のこころ』小野秀樹
本書を読んで、率直に感じたことは、自動翻訳やAIができる前に、日本型AI、中国型自動翻訳が登場す
