書評『情動はこうしてつくられる』リサ・フェルドマン・バレット 紀伊国屋書店
公開日:
:
最終更新日:2020/12/01
脳科学と観光
参考になるアマゾンの書評の紹介
➀
本書のサブタイトルにある「構成主義(constructionism)」的情動理論とは、古典的(本質主義的)情動理論に対するものである。本書の前半(第1章~第8章)では、構成主義的情動理論の科学的な根拠が多角的に説明される。古典的情動理論においては、脳には外部や体内からの刺激を受けて反応する普遍的な回路が多数あり、刺激に応じて人は怒り、悲しみ、恐れなど各種の情動を引き起こす、とされる。これに対して、著者が主張する構成主義的情動理論では、情動は生得的なものでなく、個々の刺激要素(インスタンス)により動的に情動概念が形成される、というものである。また、社会的環境も概念形成には大きく影響する。古典的情動理論が前提としているような、各情動に特有の脳領域はなく、各情動において多数のニューロンがその都度、概念形成に寄与しているのである。また、「脳は刺激に反応するのでなく、予測する」という最近確立された、構成主義的情動理論の基礎となる科学的事実も興味深い。この脳の機能があるからこそ、イチロー選手を始めとする一流スポーツ選手の美技が可能になるのである。
著者の主張は、最新の脳イメージング技術を駆使した研究成果に基づいているもので、説得力がある。情動理論における「古典的理論対構成主義的理論」は、大げさにいえば、「天動説対地動説」、あるいは「ニュートン力学対量子力学」に例えられるほど、著者の理論は革新的である。
本書の後半では(第9章~第13章)、構成主義的情動理論が様々な分野に及ぼすインパクトが解説される。情動のメカニズムを深く理解することが情動を手なずけることにつながること、疾病の発症や治療へのインパクト、古典的情動理論に凝り固まっている法律へのインパクト(犯罪者の心理状態解釈や判決にも大きく影響しうる)、動物の「情動」をどう考えるか(ペットの犬と飼い主との「交感」は可能なのか)、などである。本書では詳しくは触れられていないが、哲学を含む人文科学や文学など芸術、さらには人間に関わること(社会・政治を含め)に大きな影響がありそうである。また、従来は「理性対情動(感情)」が多くの思想や人間学の前提条件であるが、構成主義的情動理論によればその前提条件が大きく揺らいでしまう。もはや理性の「特権的位置」も怪しくなり、「理性的人間」という西洋文明の前提条件も土台が崩れてしまう。
評者の感想として、構成主義的情動理論に深い感銘を受けた。今後、幅広い分野にジワリと影響が広がりそうである。また、古くからの東洋思想(たとえば禅)は、妄念が渦巻く人の頭の中を見抜いていたようで、構成主義的情動理論を先取りしていたような気もする。とにかく、脳神経科学だけでなく、広く人間学に関心を持つ方には、本書を一読されることを薦めしたい。
➁ 「情動を経験したり知覚したりするには、情動概念が必要とされる。」、これが著者バレット自身がいうところの、本書のもっとも斬新な主張である(p.236)。確かに斬新であるばかりか、脳を媒介として、情動ばかりでなく、人間の本性を解明する革新的な理論の登場である。
1.古典的理論の否定
何が革新的なのか。
・「刺激と反応」理論を否定する(p.185)。私たちは外界の出来事に反応するべく配線された動物ではない(p.254)。
・「いかなる情動概念も普遍的ではない」のだ(p.242)。情動を経験したり知覚したりするには、情動概念が必要とされるとしても、情動のイデアがあったり、情動に限らず概念を持って生まれてくることはない(p.161)。「ずぶ濡れになることに対する恐れは、クマに対する恐れと同じものではない。」というウィリアム・ジェイムズの言葉にあるように、本質的な「恐れ」はどこにもない(p.268)。
・「表情に情動の指標」を見い出すことはできないし、心臓の鼓動や手の震え、涙などの生理的反応を情動の指標とすることもできない(p.161)。
・「理性が情動を抑制している。」これは神話である(p.208)。
バレットの理論以前に似た理論はあったはずだ。ジェームズ=ランゲ説とソマティック・マーカー仮説はバレット理論に似ている。ただ、バレット自身はこれらの理論を評価してはいない(p.268)。脳科学が今ほど発展していなかった時のものなので無理もないかもしれないが、バレットは最近の脳科学の業績を大いに活用している。
また、バレットは決して観念論をいっているのではない。「脳は遺伝子によって、物理環境や社会環境に応じて配線する能力を与えられている。p.187」、「外界から入ってくる感覚刺激は、乳児が持つ世界のモデルの内部で概念になる。外部のものが内部のものになるのだ。p.193」、「情動は頭のなかにだけ存在すると言いたいわけでもない。p.234」などとあるように、常に外の世界が想定されている。
2.理論の要約
要約的説明は随所にあるのだが、それだけで理論の全容を理解することは難しい。そのなかでも、p.595の注12は比較的分かりやすかった。「一つの概念は、物理的には異なりうるが、特定の目的に照らして類似するものとして扱われる複数のインスタンスから構成される。社会的リアリティにおいては、その目的とは、インスタンスの物理的な本性を超えて、人々が(インスタンスに)課す一連の機能を意味する。(つまり人々はインスタンスを、物理的な差異に関わりなく、心的に類似したものとして扱う。)」とあり、類似したインスタンスによって概念が構成されていること、インスタンスは目的に合った機能を提供することが分かる。
「目下の状況にもっとも近似するシミュレーションが勝ち、それが経験になる。また、勝利したシミュレーションが情動概念のインスタンスであった場合、この経験は情動経験になる。p.251」も重要である。シミュレーションとは概念のインスタンスのことである。
概念を獲得する説明には「統計的学習」が援用され、勝者の選択には「コントロールネットワーク」が持ち出される。これらの説明は省略するが、広く他の有力な理論を引用することで、バレットの構成主義的情動理論は強化されている。
3.心的事象の一般原理
「人は概念を用いて分類し、内受容刺激や五感から意味を作り出している.....本書の目的は、分類することで私たちが経験する知覚、思考、記憶などのあらゆる心的事象が構築されるという点を示すことにある。p.149」とあり、「概念として組織化された過去の経験を用いて自己の行動を導き、感覚刺激に意味を与えているのだ。私は、この手法を分類と呼んできた。だがそれは科学では、経験、知覚、概念化、パターン完成、知覚的推論、記憶、シミュレーション、注意、道徳性、心的推論など、さまざまな名称で呼ばれている。....この種の用語は、....異なる現象として研究することが多い。しかし実際には、すべて同一の神経プロセスを介して生じるのだ。p.211」とある。ようするに、心的出来事のほとんどは情動と同じ推論のプロセスだということだ。
勝手ながらバレットの構成主義的情動理論を構成主義的推論理論と言い換えられると考える。だとすれば、下記の①②③もバレットの理論の守備範囲に入ろう。
①倫理の情動主義
倫理学の分野で情緒主義(emotivism、情動主義とも訳される)と呼ばれる立場がある。情緒主義はA・J・エイヤーやC・L・スティーヴンソンらの立場をいう。道徳判断は信念ではなく一種の感情の表現であり、あるいはそうした表現を通して相手の感情に訴えかけるための道具であるとする。倫理学にもバレット理論(構成主義的推論理論)が適用できそうだ。
②ゴッフマンのフレーム分析
社会学者のアーヴィング・ゴッフマンのフレーム・アナリシスは構成主義的推論理論で説明できそうだ。脳科学者ジョージ・ブザキ教授の研究によると、脳内の海馬は空間情報を処理する自動車のナビゲーションのようなもので、いま頭はどちらを向いているのかを示す頭方位細胞(head-direction cell)、周囲の環境を格子に区切って対象がどの格子にあるのかを判断する格子細胞(grid cell)、特定のどの場所にいるのかを教える場所細胞(place cell)があるそうだ。このように空間の探索に海馬が利用されている。自然環境のフレームワークの一つといえよう。
このフレームワークが社会環境に応用されて、いろいろな社会的場面のフレームがつくられていくとするのがフレーム・アナリシスの発想である。そう推測させるのは、海馬がこの機能を記憶の探索にも使っているからだ。社会的場面は記憶によって構成される。構成された社会的フレーム(バレットなら概念)を切り替えて、グレゴリー・ベイトソンのイルカが「新しい演技の訓練」というフレームから、「新しい演技の披露という遊び」のフレームに移行し、その場のトレーナーとのやり取りの不整合から新しい視点(バレットならインスタンス)を獲得することができるようになる。
こう想定すると、ジャン・ピアジェの「同化」と「調節」を思い出す。物事の認知のためのシェム(あるいはフレームor概念)を物事に当てはめることが「同化」で、うまく当てはまらないときにシェムを変更することが「調節」だ。バレットの理論なら、ピアジェの「同化」と「調節」は、概念やインスタンスの選択に相当する。ピアジェとベイトソンとゴッフマン、そしてバレットは同じことをいっているように思える。ピアジェは子どもの発達過程で、ベイトソンはダブルバインド状況でのメタ・コミュニケーションで、ゴッフマンは日常会話で、バレットは脳の神経プロセスで。
③ヴィゴツキーの発達の最近接領域
ロシアの心理学者レフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」とは、子どもたちの能力発揮の場であり、いままで子どもだけでは示し得なかった能力が大人や仲間の助けを借りて現実のものとなることである。また「発達の最近接領域」では、経験を踏まえた豊かではあるがときどき間違っている知識を、教育者によって系統的で科学的なそれに導く評価の場であり、教育の場である。そして、「今日二人でできることは、明日は一人でできる。」という言葉を残している。
バレットの場合、「乳児の概念の形成は言葉によって促されるが、それは、おとなが〈みて、あれは花だよ〉などと、伝達の意図を示しながら話す場合に限られる」という仮説を提唱する論文(Waxman & Markow 1995)を紹介している(p.166)。これは「発達の最近接領域」の乳児版といえる。
以上、本書は脳科学の成果を利用した自由の宣言とも思える。私たちは感覚入力を予測し、概念やインスタンスを構築し、行動を選択する。その意味で人は自由である。自由がなければ、この不確実な世界を生き抜くことはできないだろう。私たちは脳に操られるロボットではないのだ。
関連記事
-

-
「食譜」という発想 学士會会報 2017-Ⅳ 「味を測る」 都甲潔
学士會会報はいつもながら素人の私には情報の宝庫である。観光資源の評価を感性を測定することで客観化しよ
-

-
『答えのない質問』レナードバーンスタイン著 原理的に音楽には普遍性があるというのがバーンスタインの主張。その証明のため、チョムスキーの理論を援用 音楽を証明可能な科学で論じようとした
音楽教育に熱心だったバーンスタインが、1973年にハーバード大学で、6つのテーマをもとにしたレク
-

-
書評『ロボットと生きる社会』
新井紀子 AIが下す判断と人間が下す判断は違う AIは基本は検索。人間は実験ができないので科学的に
-

-
ハーディ・ラマヌジャンのタクシー数
特殊な数学的能力を保有する者が存在する。サヴァンと呼ばれる人たちだが、どうしてそのような能力が備わ
-

-
保護中: 観光研究におけるマインドリーディングの活用の必要性
関係学会における発表で、マインドリーディングを活用した論文がみられない。観光行動等は、楽しみの旅に関
-
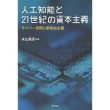
-
本山美彦著『人工知能と21世紀の資本主義』 + 人流アプリCONCURの登場
第6章(pp149-151)にナチスとイスラエルのことが記述されていた。ヤコブ・ラブキンの講演を基に
-

-
保護中: 学士会報No.946 全卓樹「シミュレーション仮説と無限連鎖世界」
海外旅行に行けないものだから、ヴァーチャル旅行を楽しんでいる。リアルとヴァーチャルの違いは分かっ
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 視覚 知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避、色盲メガネ
◎松井冬子 博士論文「知覚神経としての視覚によって覚醒される痛覚の不可避」 生まれ
-
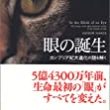
-
『眼の誕生』アンドリュー・パーカー 感覚器官の進化はおそらく脳よりも前だった。脳は処理すべき情報をもたらす感覚器より前には存在する必要がなかった
眼の発達に関して新しい役割を獲得する前には、異なった機能を持っていたはず しエダア
-
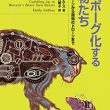
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
- PREV
- 書評『人口の中国史』上田信
- NEXT
- 書評 AIの進化が新たな局面を迎えた:GTP-3の衝撃


