『「日本の伝統」の正体』
公開日:
:
最終更新日:2023/05/21
伝統・伝承(嘘も含めて), 出版・講義資料
現在、「伝統」と呼ばれている習慣の多くが明治時代以降に定着したと聞いたら驚く人も多いかもしれない。
例えば、喪服は黒色でなく、室町時代以降、江戸時代に入っても白色だったし、七五三は関東限定の地域イベントだった。正月の代名詞ともいえる初詣に至っては誕生したのは明治中期で、今、世間を揺るがしている相撲が「国技」と呼ばれ始めたのは国技館がつくられた明治末だ。
歴史が浅いから価値が下がるわけではない。重要なのは、「伝統」と呼ばれる習慣の背後にはビジネスや権威付けをもくろむ人間が存在するという視点を持つことだと著者は指摘する。「伝統」の二文字が大好きな日本人にとっては耳が痛い話も多い。本書を読むと、我々がいかに深く考えずに前例を踏襲しているかに気づかされるだろう。 「初詣」は江戸時代になかった? ★「江戸しぐさ」のいかがわしさ ★神前結婚式は古式ゆかしくない ★「古典落語」は新しい? ★恵方巻は、本当はいつからあったのか? ★アレもコレも「京都マジック」! ★初めて「卵かけご飯」を食べた男とは? ★サザエさんファミリーは日本の伝統か? ……一見、古来から「連綿と続く伝統」のように見えるしきたりや風習・文化。しかし中には、意外に新しい時代に「発明された伝統」もある。もっともらしい「和の衣裳」を身にまとった「あやしい伝統」
関連記事
-

-
「太平洋戦争末期の娯楽政策 興行取締りの緩和を中心に」 史学雑誌/125 巻 (2016) 12 号 金子 龍司
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-

-
ネット右翼を構成する者 メディアが報じるような「若者の保守化」現象は見られない
樋口直人は『日本型排外主義』の中で、大部分は正規雇用の大卒ホワイトカラーであるとし、古谷経衡も「ネ
-
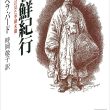
-
イサベラバードを通して日韓関係を考える
Facebook投稿文(2023年5月21日) 徳川時代を悪く評価する「薩
-

-
『時間は存在しない』カルロ・ロヴェッリ
『時間は存在しない』は、35か国で刊行決定の世界的ベストセラー。挫折するかもしれないので、港区図書
-

-
『昭和史』岩波新書青本 恐慌の影響で、朝鮮人(日本国籍がある)の満州移住が増加したが、中国側は日本の手先と見て敵視 奉天の柳条溝で満州事変 この頃からメディアも変わる
26年と30年を比較すると中国(満蒙含む)の輸出入貿易額に占める対日貿易額の占める割合は低下した
-

-
三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』なぜ日本に政党政治が成立したのか
1 なぜ日本に政党政治が成立したのか (これまではなぜ政党政治は短命に終わったかを論じてきた)
-

-
保護中: 学士会報No.946 全卓樹「シミュレーション仮説と無限連鎖世界」
海外旅行に行けないものだから、ヴァーチャル旅行を楽しんでいる。リアルとヴァーチャルの違いは分かっ
- PREV
- 『創られた伝統』
- NEXT
- 書評 渡辺信一郎『中華の成立』岩波新書
