『創られた伝統』
公開日:
:
最終更新日:2023/05/21
伝統・伝承(嘘も含めて), 出版・講義資料
第一に、全ての「伝統」は歴史の中で恒常的に取捨選択された結果であり、長年の「伝統」であれ、その都度の時代への適応の中で、常に重心の移動が起こっている。第二に、したがって、「伝統」には変えてよいものと変えられるべきでないものとがあり、「伝統」か「新しいもの」かという二分法は否定される。第三に、「伝統」というラベリングにより特定のものを聖域化する発想は思考停止であり、場合によっては差別の温存にもつながりかねない。第四に、その取捨選択の基準は常にその都度の「現在」(政治的、経済的、文化的要因)にある。第五に、どれだけの人に普及していれば「伝統の存続」と言えるのか、はいったん検討されるべきであり、社会には常に相矛盾する無数の「伝統」が並存していると考える方が妥当である。
「伝統」研究の古典としてお勧め。
本書は「創られた伝統」が、1870〜1914年の時期のヨーロッパで大量生産されたという史実を紹介している。そしてその原因として、当時の急激な産業社会化が、為政者に国民同士の連帯感やアイデンティティーの確保について不安を感じさせたことをあげて、社会を安定させようとして試みた様々な工夫が結果的に「伝統」の大量生産になったのだと論じている。考えてみると、この時期は国民国家としての日本が確立した時期にもあたっている。欧米の影響下で急激に日本社会の近代化が進展したが、やはりこの時期に、主として近代天皇制にまつわる様々な伝統が創り出されたことがわかる。それにしても、明治維新以降の近代化に伴なう社会の激変にもかかわらず、社会の安定が大きく損なわれなかったことは、伝統を創る際に参照可能な、豊かで長い日本の歴史があったからこそだと思った。
関連記事
-

-
The best passports to hold in 2021 are: 1. Japan (193 destinations)
https://www.passportindex.org/comparebyPassport.p
-

-
フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで
観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる
-

-
MaaSに欠けている発想「災害時のロジステックスを考える」対談 西成活裕・有馬朱美 公研2019.6
公研で珍しく物流を取り上げている。p.42では「自動車メーカーは自社の車がどこを走っているかという
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-

-
「太平洋戦争末期の娯楽政策 興行取締りの緩和を中心に」 史学雑誌/125 巻 (2016) 12 号 金子 龍司
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発
-

-
動画で考える人流観光学 マクスウェルの悪魔
【物理学150年の謎を日本人教授が解明】マクスウェルの悪魔が現れた!/東京大学 沙川貴大教授/教え子
-

-
国際収支の理解 インバウンド好調の原因
それでも円高にならないのはなぜか?「売った円が戻ってこなくなった」理由 https://www.
-
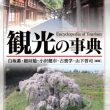
-
『観光の事典』朝倉書店
「観光の事典」に「観光政策と行政組織」等8項目の解説文を出筆させてもらっている。原稿を提出してか
-

-
畑中三応子著『ファッションフードあります』日本食は変化が激しい。フードツーリズムに法則があるのか?
ティラミス、もつ鍋、B級グルメ……激しくはやりすたりを繰り返す食べ物から日本社会の一断面を切り
- PREV
- 山泰幸『江戸の思想闘争』
- NEXT
- 『「日本の伝統」の正体』
