『庶民と旅の歴史』新城常三著
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
新城 常三(1911年4月21日- 1996年8月6日)は、日本の歴史学者。交通史を専門とした。1961年、「社寺参詣の社会経済史的研究」により、東京大学から文学博士の学位を授与される。1983年、『新稿社寺参詣の社会経済史的研究』で角川源義賞受賞。新稿社寺参詣の社会経済史的研究 塙書房 1982.5 本書が財団日本交通公社の「一度は読みたい観光研究書&実務書100選」に選ばれていないのは残念である。
旅と交通。旅はかつては、人の移動のみならず、広く運輸通信も含んでいた。陸上では、運輸も通信も人自身の移動=旅とともに果たされていたからである。
田中丘隅『民間省要』士農工商 主君の命に従っての旅行、生活のための旅、信仰のための旅、慰めのための遊山旅
ケンペルが当時の東海道の賑わいに、欧州大都会よりもにぎわっているという
中世の旅 中世の関所は古代や近世と異なり、交通税徴収のためのもの、大阪と京都間の淀川に660か所の関所、回族、山賊 信長、秀吉の統治で廃止になる。
病気治療の大義名分には勝てず、温泉行き等は認めていた。しかし、湯治や医療は、近距離の遊山旅の口実とはなっても、長期にわたる上方見物などに利用することは不向き。長期遠隔の旅の名目として、社寺参詣。これを抑制することは幕府も諸藩もできなかった。
「伊勢参り、大明神へもちょっとより」
隠れ念仏 封建領主の禁圧、薩摩藩等の真宗弾圧 隠れキリシタンと同じ潜伏門徒として明治維新まで継続
中世を通じ旅行界、参詣界に君臨していた武士は、江戸時代に入り、旅からは影を潜めた。
旅のシーズンは、農閑期1~3月、四月以降の旅行者の大半は、農村の有力者、商人、町民
抜け参りは伊勢特有の現象 身分的な桎梏を切断 婦女子、使用人 乞食巡礼
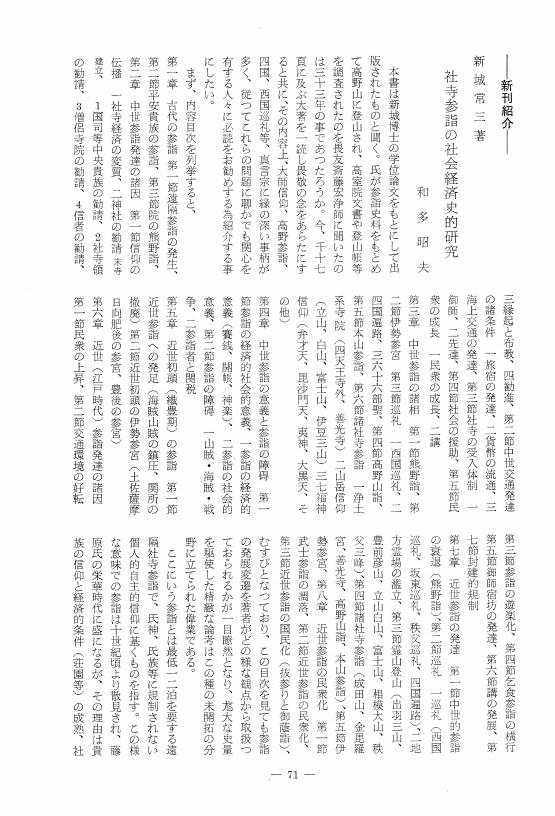
関連記事
-
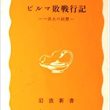
-
動画で考える人流観光学 『ビルマ敗戦行記』(岩波新書)2022年8月27日
明日2022年8月28日から9月12日までインド・パキスタン旅行を計画。ムンバイ、アウランガバード
-

-
「食譜」という発想 学士會会報 2017-Ⅳ 「味を測る」 都甲潔
学士會会報はいつもながら素人の私には情報の宝庫である。観光資源の評価を感性を測定することで客観化しよ
-

-
Quora Ryotaro Kaga·2019年8月1日Sunway University在学中 (卒業予定年: 2024年)なぜこんなに沢山の日本人女性が未婚なのですか?
Ryotaro Kaga·2019年8月1日Sunway University在学中 (
-

-
Transatlantic Sins お爺さんは奴隷商人だった ナイジェリア人小説家の話
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswg9n BBCの
-
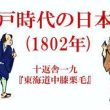
-
『日本語スタンダードの歴史』野村剛士は、「日本の話しことばについて」『現代国語三』所収 木下順二著1963年を否定
私の自説に、日常と非日常が相対化しており、観光資源もあいまいになってきているというアイデアがある
-

-
宇田川幸大「考証 東京裁判」メモ
政治論ではなく、裁判のプロセスを論じている点に独自性がある 太平洋戦争時のジュネー
-

-
ジャパンナウ観光情報協会機関紙138号原稿『コロナ禍に一人負けの人流観光ビジネス』
コロナ禍でも、世界経済はそれほど落ち込んでいないようだ。PAYPALによると、世界のオンライン
-

-
御手洗大輔「示威の自由に関する日中比較と日本人の課題」
『横浜市立大学論叢』第68巻社会科学系列2号 御手洗大輔「示威の自由に関する日中比較と日本人の課題」
-

-
『一人暮らしの戦後史』 岩波新書 を読んで
港図書館で『一人暮らしの戦後史』を借りて読んでみた。最近の本かと思いきや1975年発行であった。
- PREV
- 『富嶽旅百景』青柳周一 観光地域史の試み
- NEXT
- 『フクシマ戦記 上・下』船橋洋一 菅直人の再評価
