『富嶽旅百景』青柳周一 観光地域史の試み
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
港区図書館で借りだして読んだ。本書は、1998年東北大学提出学位論文がベースとなっている。外部から旅行者をはじめとする人々の流入を積極的に受け入れることで再生産を継続するタイプの地域社会の歴史的研究=「観光地域史」研究を提唱し、その成果は『富嶽旅百景-観光地域史の試み-』として上梓している。「観光地域史」としているが、私の印象では、観光政策論としても十分に通用し、なおかつ、近世の観光政策を論じたものとしても初めてのものではないかと思う。
観光概念が発生していたかの判断は、何のために論じるかということにもなるが、「楽しみのための旅の大衆化」とすれば、まさに近世の富士参詣は大衆化の時期であったから、人流政策は観光政策ととらえることができる。政策と政策以外のもとを区別する要素は単純で、唯一「権力の行使」があるか否かである。権力基盤が確立した近世の時期、富士参詣を巡って、吉田村沿道地域等からたびたび当局に訴えが行われている。私法と公法が未分離な時代(現代でも単純な私法、公法の区分は否定されているが)、当局は何らかの判断基準により訴えを処理しているから、人流政策を行っていたと考えられる。
以下内容紹介
参詣ルートの変化と統制 沿道での稼ぎが住民たちに大きな利益をもたらすのもであっただけに、ルートが変更して参詣客が通らなくなるようなことがあれば深刻な問題が生じることになったと記述(p.19)するが、空港や新幹線等現代の人流政策でも同じである。品川宿は、江戸から神奈川宿まで一気に海上を船で行くようになり、富士等へ向かう参詣客が減少したので「船往来」差し止めを町奉行に申し出ているから、まさに政策論議である。宝永4年富士山噴火により、参詣ルートに大きな影響が発生した。その災害復旧の過程で沿道利害集団が形成され、その都度当局に対して、参詣客集客に関し、優遇策と他地域の抑制策が訴えられている(p.36以下)。中世より存続してきた参詣者と御師(旅行手配士)の関係並びに御師と宿泊所の関係が、近世の参詣客の増大により大きく変化した。ITにより、旅行者と旅行業や宿泊業の関係に大きな変化が発生している現代にも通じるものである。独占禁止法的な発想がない近世であるから、仲間内での規則の制定は試みられているが、他地域との調整、御師と宿泊所の関係は民間だけでは処理しきれないものであるから、当局に訴えがなされることになる。
当局側の最大の関心は、災害時の参詣客の処理である。師檀・定宿関係を持たず来た参詣者は単独登山するため、遭難時等の処理が村役人には困難を伴うこととなる。そのための予防措置等が政策として講じられることとなったのである。また、よそ者である参詣客の増大は地域住民との利害が対立することがある。物価高騰、環境破壊は近世後期も現代も同様であり、私法領域だけではなく、まさに観光政策が求められる。
オリンピックを巡り前会長の女性蔑視発言が国際的な話題となったが、近世後期も女人禁制が大きなテーマであった。規制札が沿道に建てられていたから、行政の関与はあったはずであるものの、内容も理由も明確でない。女性に対する穢れ思想の存在は否定されているようでもあり禁制自体が曖昧である中、近世後期には女性参詣客が増大した。観光と無関係の地域住民は、悪天候の発生源としてのイメージを仮託して、排除を試みた(p.145)が、集落同士の競争もあり、禁制の弛緩化が進行した。1872年3月太政官布告第98号「神社仏閣女人結界の場所を廃し登山参詣を随意とす」により女人結界が解除された。政府からの税制上の措置を受けている相撲協会の方針は、相撲を神事と考えないのであれば理解できるが、神事とすれば布告の精神には反しているのであろう。
富士山頂の所属を巡り、静岡県と山梨県で見解がことなる。同書でも第3章をこの話題に充てている。公物管理ではなく私的財産権の問題で論じるのであれば、観光政策の出る幕ではないものの、近世後期の当局の関心事は、やはり遺体の処理責任者の決定であるから、現代風に理解すれば交通事故の県警の決め方の問題である。瀬戸大橋での交通事故の場合、岡玉県と香川県では、県境で区分せず、接近の便利なレーンをそれぞれ分け合っている。逆に言うと、近世後期も死骸処理の方法の判断事項として取り扱われており、決着するまで7年かかったようである(p.209明和・安永論争)。観光政策でいえば、よそ者のの取扱いに関し、どの行政組織の担当かということになる。現代の国境紛争のように、すべての法律事項を国境で明確に区分するというものでもないことである。
いずれにしろ、本書は近世における貴重な観光政策の材料を提供してくれており、観光研究者には必読の書である。
関連記事
-

-
コロナ後の日本観光業 キーワード 現金給付政策を長引かせないこと、採算性の向上、デジタル化、中国等指向
今後コロナ感染が鎮静化に向かうことが期待されているおり、次の課題はコロナ後の回復に向けての施策に重
-

-
『中国人のこころ』小野秀樹
本書を読んで、率直に感じたことは、自動翻訳やAIができる前に、日本型AI、中国型自動翻訳が登場す
-

-
『日本が好きすぎる中国人女子』桜井孝昌
内容紹介 雪解けの気配がみえない日中関係。しかし「反日」という一般的なイメージと、中国の若者
-

-
中山智香子『経済学の堕落を撃つ』
経済学は、なぜ人間の生から乖離し、人間の幸福にはまったく役立たなくなってしまったのか? 経済学の
-
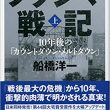
-
『フクシマ戦記 上・下』船橋洋一 菅直人の再評価
書評1 2021年4月10日に日本でレビュー済み国民の誰もがリアルタイムで経験した
-

-
保護中: 『市場と権力』佐々木実を読んで
日銀が量的緩和策で銀行に大量にカネを流し込んだものの、銀行から企業への融資はそれほど増えなかった。
-
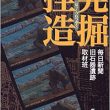
-
『発掘捏造』毎日新聞旧石器遺跡取材班
もう20年も前の事であるが、毎日新聞取材班の熱意により旧石器遺跡の捏造事件が発覚した。その結果、
-

-
日本人が海外旅行ができず、韓国人が海外旅行ができる理由 『from 911/USAレポート』第747回 「働き方改革を考える」冷泉彰彦 を読んで、
勤労者一人当たり所得では、日本も韓国も同じレベル 時間当たりの所得では、日本は途上国並み これで
-

-
ピアーズ・ブレンドン『トマス・クック物語』石井昭夫訳
p.117 観光tourismとは、よく知っているものの発見 旅行travelとはよく知られていな
- PREV
- 『近世旅行史の研究』高橋陽一 清文堂出版 宮城女子学院大学
- NEXT
- 『庶民と旅の歴史』新城常三著


