「南洋游記」大宅壮一
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
出版・講義資料
都立図書館に行き、南洋遊記を検索し、[南方政策を現地に視る 南洋游記」
日本外事協会/編 — 高山書院 — 1937 –を借り出す
大宅壮一の名前を見つけまずそこから読む。
南洋といっても、台湾、パラオ、フィリピンである。
どこかの出版社の視察に文化人として誘われて参加しており、あご足つきである。さしずめ今なら、テレビで撮影にタレント教授が参加しているようなもの、といっても一流の文化人であるから、今なら池上彰クラス、NHKスペシャルのろけに行くような感じか。
船で神戸から台湾に向かうとあり、一年前に飛行機で瀬戸内海を渡ったから、時間がかかって云々という記述があったが、自慢話であり、筆が滑ったのであろう。当時は大宅壮一クラスでも飛行機に乗ったことがうれしかったのだ。確か朝日新聞にジェット教授として九州と東京を講義のため通う話が出ていたことを思い出した。
台湾について、面白い記事。台湾大学は生徒一人に先生一人という記述。台湾大学には入学希望者が少なく、本土の他の大学に入れなかった学生が入学するので、定員に満たないと書いている。当事者には失礼な話であるが、私の父親世代は、このような「どこそこの学校は・・・」話を平気でしていた。一方、大学教師は、本土と異なり定年がなく、年に数回の渡航費用も出て、賃金も割増であるようなことを記述。昭和12年の世相がわかって面白い。今なら、台湾大学はエリート校である。
関連記事
-

-
『不平等生成メカニズムの解明』「移民はどのようにして成功するのか」竹中歩・石田賢示・中室牧子
「移民はどのようにして成功するのか」竹中歩・石田賢示・中室牧子『不平等生成メカニズムの解明』ミネルバ
-
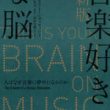
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
-

-
ゆっくり解説】突然変異5選:新遺伝子はどうやって生まれるのか?【 進化 / 遺伝 子 / 科学 】
https://youtu.be/bGthe_Aw1gQ ミトコンドリアと真核生物の起源:生物進化
-

-
2002年『言語の脳科学』酒井邦嘉著 東大教養学部の講義(認知脳科学概論)をもとにした本 生成文法( generative grammar)
メモ p.135「最近の言語学の入門書は、最後の一章に脳科学との関連性が解説されている」私の観光教
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
-

-
QUORAにみる観光資源 なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか?
とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。 一般的に思われてい
-

-
矢部 宏治氏の「なぜ日本はアメリカの「いいなり」なのか?知ってはいけないウラの掟」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52466 外務省がつ
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-

-
学士会報926号特集 「混迷の中東・欧州をトルコから読み解く」「EUはどこに向かうのか」読後メモ
「混迷の中東」内藤正典 化学兵器の使用はアサド政権の犯行。フセインと違い一切証拠を残さないが、イス
-
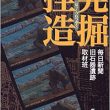
-
『発掘捏造』毎日新聞旧石器遺跡取材班
もう20年も前の事であるが、毎日新聞取材班の熱意により旧石器遺跡の捏造事件が発覚した。その結果、

