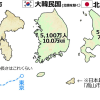『はじめての認知科学』新曜社 人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
脳やコンピュータでも、神経細胞やエレクトロニクス素子などミクロ的世界まで下りてゆけば、そこには「わかる」も「意味」も消え失せてしまう。そういう状況の中でどうして人はわかったり意味を感じたりするのか。その謎を解きたいというのが認知科学
そもそも意味を含まない計算モデルから、最終的に意味が生じるのはどうしてかということを突き止めたいというのが認知科学の究極の目的
文法の基本的な構造はすでに生まれたときからすべての人の頭に同じ形で存在するとう、チョムスキーの生成文法という言語理論 言語以外のことに関する認知能力とはMったく違う認知の在り方だという考え方 反チョムスキー派との論争では「何が生得的か」が中心議論
記号接地問題 人はどうやって理解をはじめて、最終的にすべての関係を整理できるのか
膨大な数の単語を要素としながら巨大で複雑なネットワークの中でそれぞれの言葉が関係づけられた心内辞書、メンタルレキシコンを作ってゆく過程は未解明なことばかり
アントニオ・ダマジオ等らの研究 側頭葉の先端は人の名前、下側頭領域では動物の名前、さらに下側頭領域後部から外側後頭葉では道具の名前が関係しているという
動物でもできる連合学習、統計学習の能力を使えば、曖昧性のない状況で、一つの記号と一つの対象の結びつきを学習することはできる
ヒューリスティックな思考をするバイアスは「論理的には正しくない」とはいえ、とても実際には役に立つ思考の仕方 これがあるからこそ、人は言葉を駆使することができるようになった可能性がある
人の心の中で数万語の言葉がお互いの関係まで含めて、ほとんど他の人から教わることもなしに辞書を作成してしまうというのは奇跡的な出来事
神経細胞モデルを使ったニューラルネットも、膨大な数の脳神経そのものを完璧にシミュレーションはできておらず、大まかな近似に過ぎないが、脳神経細胞をまねる試みは続けられた。2006年トロント大学ジェフリー・ヒントンがデープラーニングという方法を開発。これでも、機械による学習の結果がなぜそうなるのかという説明はなかなか難しいのである。人の知能の働き方の理解というわかり方がニューラルネットではいまだに困難
ミラーニューロンシステム(MNS)1990年代前半イタリア・パルマ大学ラゾモ・リゾラッティらにより発見 マネの手前の段階といえる「他者の運動の理解」という機能を支えているというシミュレーション仮説 サルなどの動物にもある共感という現象も、MNSが支えている
すべての分野で遺伝子研究、分子生物学の裏付けなしには神経細胞とそのネットワークのミクロな生物学的解明は難しくなっている
脳の活動を目に見える形で提示する方法の開発 感性アナライザー
脳とコンピュータの直接接続 ブレイン・マシーン・インターフェースBMIの開発研究
究極はヒトの脳・心の解明
環境が提供する(アフォードする)価値や意味と人の行為の関係をアフォーダンスという。環境にあるモノを知覚することと運動がダイレクトかつ不可分に結びついていることが重要。アフォーダンスには記号操作は必ずしも必要ではない
自分が物をつかむ行動をとるときに発火する神経細胞のうちに、つかむことのできる対象を見ただけで発火する細胞があることが分かった。カノニカル・ニューロンという。アフォーダンスに対して活動する神経細胞である。他人の身体と自分が相互作用する物体のそれぞれを認知するシステムが備わっている
狐の家畜化 40年間の実験 外見も犬のようになってきた。一つの種で、その認知能力は決して固定したものではなく、時間とともに変わってゆくことが分かった
ニューラルネットで問題が解けたときの表象は各神経細胞がどのように結合しているかというミクロの状態で、それを解析しても直感的なモデルの形で取り出すことは困難
ニューラルネットによる人工知能の認知についても同様のことがいえる。機械の思考はヒトにはわからないようになってきているのかもしれない
脳科学でも同様の事態が起こり始めているという声がある。これまでの認知科学の枠組みで解析することは相当難しい
関連記事
-

-
QUORA ゴルビーはソ連を潰したのにも関わらず、なぜ評価されているのか?
ゴルバチョフ書記長ってソ連邦を潰した人でもありますよね。人格的に優れた人だったのかもしれませんが
-

-
倉山満著『お役所仕事の大東亜戦争』1941年12月8日『枢密院会議筆記』真珠湾攻撃後に、対米英宣戦布告の事後採決
海軍が真珠湾攻撃のことを東条に伝えたのは直前のこと 倉山満著『お役所仕事の大東亜戦争』p.2
-
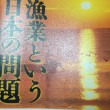
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は
-

-
井伏鱒二著『駅前旅館』
新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は
-

-
人流・観光学概論修正原稿資料
◎コロナ等危機管理関係 19世紀の貧困に直面した時、自由主義経済学者は「氷のように
-

-
QUORAにみる観光資源 なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか?
とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。 一般的に思われてい
-
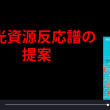
-
AIに聞く、甘利俊一博士の「脳・心・人工知能」を参考にした、『観光資源反応譜』の提案
人流・観光に関する学生用の教科書として、amazonのkindleで『人流・観光学概論』を出版してい
-
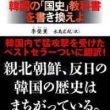
-
書評『大韓民国の物語』李榮薫
韓国の歴史において民族という集団意識が生じるのは二十世紀に入った日本支配下の植民地代のことです。
-

-
英国のドライな対外投資姿勢 ~田中宇の国際ニュース解説より~
私の愛読しているメール配信記事に田中甲氏の田中宇の国際ニュース解説 無料版 2015年3月22日 h
-

-
Quoraなぜ、当時の大日本帝国は国際連盟を脱退してしまったのですか?なぜ、満州国について話し合ってる中で軍事演習をしてしまったのか、なぜ、当初の目的である権益のほとんどを認められているのに堂々退場したのか。
日本の国際連盟脱退は、満州事変に対するリットン調査団の報告書を受け入れられないと判断して席を蹴った