『一人暮らしの戦後史』 岩波新書 を読んで
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
出版・講義資料
港図書館で『一人暮らしの戦後史』を借りて読んでみた。最近の本かと思いきや1975年発行であった。
戦前の女性が、戦争で男性が減少した結果、未亡人になったり独身のまま戦後を生きてきたことがテーマになっている。
私が社会に出たころは、母親世代が働いていたから、実感もある。敦賀の義理の伯母は、沖縄線で伯父をなくしているから、戦争未亡人でもあった。
(沖縄戦は、兵士が不足し、年配者の伯父にまで徴兵がかかってきたのである。サイパン陥落後の太平洋戦争の末期に大半が死亡しているのは、戦争指導者の大きな責任であり、日本人自身が戦犯問題を処理すべきことでもあった)。
面白い記述は「スーパーマーケットに買い物に行ったときなど、一人で暮らしていていけないのかと叫びたくなる」というご婦人の話であった。「食料品を買うにも四人家族用のパックばかり。こうした商習慣から社会制度、ものの考え方まで家族単位に出来上がっており、一人暮らしの立場というのは考えられていない」
「日本人の結婚率は世界でも極めて高く、アメリカ、韓国に次いで三番目である。西欧では独身主義の風潮が強く、生涯に一度も結婚しない人が人口の一割もいるのに比べて、日本人は大変な結婚好きで、50歳までに98%は結婚するという」
しかし、国民皆結婚社会になったのは戦前のことで、江戸時代まではそんなことはなかったはずだ。
関連記事
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進
-
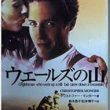
-
観光資源創作と『ウェールズの山』
観光政策が注目されている。そのことはありがたいのであるが、マスコミ、コンサルが寄ってたかって財政資金
-

-
岩波書店の丁稚奉公ストライキ
『教科書には載っていない戦前の日本』p.222 封建的な雇用制度の改善を求めて岩波書店側に突
-
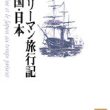
-
書評『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳
日本人の簡素な和式の生活への洞察力は、ベルツと同じ。宗教観は、シュリューマンとは逆に伊藤博文等が
-

-
宇田川幸大「考証 東京裁判」メモ
政治論ではなく、裁判のプロセスを論じている点に独自性がある 太平洋戦争時のジュネー
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
『不平等生成メカニズムの解明』「移民はどのようにして成功するのか」竹中歩・石田賢示・中室牧子
「移民はどのようにして成功するのか」竹中歩・石田賢示・中室牧子『不平等生成メカニズムの解明』ミネルバ
-

-
シャマニズム ~モンゴル、韓国の宗教事情~プラス『易経』
シャーマン的呪術は筮竹による数字と占いのテキストを使った方法にかわった。このことにより特殊能力者でな
-
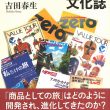
-
『パッケージツアーの文化史』吉田春夫 草思社
港区図書館の新刊本コーナーにあり、さっそく借り出して読んだ。JTBでの実務経験が豊富な筆者であり、
- PREV
- 白バスと白タク論議の峻別
- NEXT
- 伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで


