『国際報道を問いなおす』杉田弘毅著 筑摩書房2022年
公開日:
:
歴史認識
ウクライナ戦争が始まって以来、日本のメディアもSNSもこの話題を数多く取り上げてきている。必ずしもYoutubeなどはロシア批判一辺倒ではないが、マスメディアはほぼロシア批判一辺倒であり、公の場で私人がウクライナ批判をすることが憚れる状態である。その原因が、日本のマスメディアが欧米メディアを情報源にして報道しているからであり、日本のメディアが現地取材と称して報道しているものも、ウクライナが用意した舞台で行っている。そのような中、本書が発行されたので、急いで読んでみた。
国際報道の中では珍しく報道量が多いウクライナ戦争報道である。しかし国際報道と言いながら、国際競争にさらされていない日本のメディアの限界が正直感じられる。本書はカタールの報道機関アルジャジーラは、ウクライナ難民が特別扱いを受け、シリア難民は冷遇されているという報道視点があるとする。アフリカやインド等では、方々で内戦や暴動が起きており、BBCなどは旧宗主国の視点なのかもしれないが、毎日報道している。日本の報道はパレスティナやバルカン関係について比較的客観的であるとされるが、その分日本人の視点というもが感じられない。ウクライナも歴史は共有していないが、攻撃者がNATO(アメリカ)ではなく、ロシアであったことから嫌露がベースの報道になっていると感じていたので、その点からも本書に興味を抱き読んでみたが、メジャーな報道機関関係者というなのか、ほぼ西欧メディアと同じ論調であった。本書では北方領土返還への過大期待報道も解析されているが、その分ウクライナ戦争報道では嫌露姿勢が強くなっているのであろう。
それでも本書は、1990年代の旧ユーゴスラビア紛争で、米国大手広告代理店がセルビアを悪者に仕立て反セルビア(反ロシア)報道を煽り、その結果米国の軍事介入が 実現したこと、湾岸戦争でクウェート人少女の米議会における虚偽証言の騙されて報道されたことについて記述する。その米メディアに頼る日本のアメリカ理解では、世界理解はゆがんだものになるとする。確かに私も、アメリカの脅しに従い核兵器を放棄した結果、カダフィー政権は崩壊し、一人当たり2万ドルあったリビア国民を極貧状態に陥れていると思う。アメリカ政府とメディアがカストロを共産主義者と勝手に決めつけた結果、革命後カストロは共産側についてしまったと思っている。
第2章の南ベトナム解放戦線びいきの報道の反省が興味深い。ベトナム戦争は、現役公務員時代に物流政策の意見交換にベトナムを訪問した時、向こうの公務員から「ベトナムはアメリカに負けなかったが、日本はアメリカに負けたので経済成長を早く達成できてよかった」的な話を夜の酒の時に聞かされたように思う。北ベトナム兵士が陥落解放させたサイゴンを訪れて、その経済繁栄に驚いたという逸話もよく聞く話である。と言って、植民地支配者のフランスや、トンキン湾事件をでっち上げ、ソンミ村虐殺事件等を引き起こした米軍を擁護するつもりにはなれないが。
本書で記述している、中国を正確に見据えるのが日本人は不得意で、誤った予測を積み重ねてきたというところも完全に同意できる。紅衛兵、文化大革命は、私が高校大学時代であり、朝日新聞等を通して美化されて報道され、信じ込んでいた。美化しない産経新聞は追放されてしまった。駒場時代の国際関係論の授業で、衛藤瀋吉先生が盛んに朝日新聞批判をし、いまとなっては真実を講義されていたことが理解できた。学生運動家は授業中衛藤先生に猛烈に講義をしていたことを思い出すが、そのつけが後になって朝日新聞の凋落となって跳ね返っているようにも思う。もっとも今のネトウヨや嫌中派のメディアは、それ以上に害悪であろうが。
第3章は、アメリカのメディアは世界で過大評価されているが、実は政治家のスキャンダル報道には熱心な一方、戦争については、愛国心に染まりやすく、戦争のお先棒を担いでしまう欠陥があるとする。米メディアを通して米国像、世界像を描くと間違えるとする。最高裁がメディアの評価を下げていると記述する。ウォーターゲート事件では報道の自由を掲げたメディアを支えた最高裁であるが、 ブッシュ対ゴアの大統領選の勝敗を最高裁が決めるとき、メディアへの評価は否定的(民主党の宣伝機関と批判)であったとする。国民の意識の反映であると記述する。
さて、トランプ対クリントンの選挙時、ロシアの関与を示唆する「スティール文書」が報道され、トランプ批判になったことは記憶に新しい。しかし、この文書は根拠があいまいで、クリントン側の仕掛けたものであるとすることの方がむしろ有力であるようだ。そのように思うと、CNN等でのトランプ批判報道も半分差っ引いて聞いておかないといけないのかもしれないから、バイデン大統領のロシア批判もうのみにする気にはなれないのである。
関連記事
-

-
『永続敗戦論 戦後日本の核心』、『日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』『英国が火をつけた「欧米の春」』の三題を読んで
「歴史認識」は観光案内をするガイドブックの役割を持つところから、最近研究を始めている。横浜市立大学論
-

-
QUORAに見る歴史認識 香港国家安全法について、多くの中国本土の人々はどのように考えているのでしょうか?
私は初めて香港に行ったとき、深セン税関の前で大声で怒鳴っている香港人たちがいて、聞き取れたのは"香
-
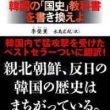
-
書評『大韓民国の物語』李榮薫
韓国の歴史において民族という集団意識が生じるのは二十世紀に入った日本支配下の植民地代のことです。
-
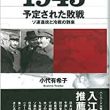
-
歴史認識と書評『1945 予定された敗戦: ソ連進攻と冷戦の到来』小代有希子
「ユーラシア太平洋戦争」の末期、日本では敗戦を見込んで、帝国崩壊後の世界情勢をめぐる様々な分析が行
-
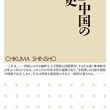
-
平野聡『「反日」中国の文明史 (ちくま新書) 』を読んで
平野聡『「反日」中国の文明史 (ちくま新書) 』に関するAmazonの紹介文は、「中国は雄大なロ
-

-
保阪正康氏の講演録と西浦進氏の著作物等を読んで
日中韓の観光政策研究を進める上で、現在問題になっている「歴史認識」問題を調べざるを得ない。従って、戦
-

-
山泰幸『江戸の思想闘争』
社会の発見 社会現象は自然現象と未分離であるとする朱子学に対し、伊藤仁斎は自然現象
-
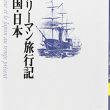
-
『シュリューマン旅行記』 清国・日本 日本人の宗教観
『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳 シュリューマンは1865年世界漫遊の旅に出か
-
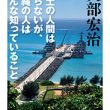
-
『本土の人間は知らないことが、沖縄の人はみんな知っていること』書籍情報社 矢部宏治
p.236 細川護熙首相がアメリカ政府高官から北朝鮮の情勢が緊迫していること等を知らされ、米国は


