『芸術を創る脳』酒井邦嘉著
メモ P29 言葉よりも指揮棒を振ることがより直接的 P36 レナードバースタイン 母校ハーバードでの講義「答えのない質問」チョムスキーの影響を受けて音楽の普遍性を論じた 言語と将棋の共通性 ポップアウト 注意に係る脳の働き
【主要目次】
はじめに――脳はどのように芸術を生み出すか
I なぜ音楽は楽しいのか 曽我大介(指揮者・作曲家)
対談を終えて――意外性に満ちた創造の現場
II なぜ将棋は深遠なのか 羽生善治(将棋棋士)
対談を終えて――芸術性が分かる感覚
III なぜマジックは不思議なのか 前田知洋(クロースアップ・マジシャン)
対談を終えて――脳が不思議を感じるとき
IV なぜ絵画は美しいのか 千住博(日本画家)
対談を終えて――生きる活力としての芸術
おわりに――人間・言語化・対話という共通性
アマゾン書評の例
著者は言語脳科学者であるらしいが、「芸術を創る脳」といったものが科学的に分析されていない。
1.芸術は人間固有の脳機能によって生まれる
2.芸術は人間の言語機能を基礎とする
3.美的感覚は芸術を支える心の機能である
と結論づけているが
1は当たり前。
あえてこのように結論づけるなら動物実験を行うなり
人間と動物との脳機能の差を示すべき。
2は著者のこじつけ。
著者は誘導尋問のように、各人の芸術と言語を結びつけていた。
むしろ言語では表現できないことを芸術に託す部分もあるだろうに。
3、美的感覚とは脳のどういったはたらきなのか示すべき。
全体的にこじつけ感が強い。脳科学はほとんど登場しない。
対話は著者と対談者の主張がお互いに強いので
対話としてかみ合ってない部分が多くみられる。
関連記事
-

-
学士会報926号特集 「混迷の中東・欧州をトルコから読み解く」「EUはどこに向かうのか」読後メモ
「混迷の中東」内藤正典 化学兵器の使用はアサド政権の犯行。フセインと違い一切証拠を残さないが、イス
-

-
保護中: 『from 911/USAレポート』第827回 「アベノミクスの功罪と出口シナリオ」冷泉彰彦 これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働集約型の観光業を主要産業とするという、どう考えても悲劇的な産業構造に追い詰められた、これは7年半にわたって改革に消極であったことのツケにしても、随分と妙な方向になったと思います
結果的に、これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働
-
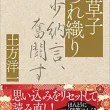
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-

-
鬼畜米英が始まったのは、1944年からの現象 岩波ブックレット「日本人の歴史認識と東京裁判」吉田裕著
靖国神社情報交換会に参加した。歴史認識は重要な観光資源であるとする私の考えに共鳴されたメンバーの
-

-
ふるまいよしこ氏の尖閣報道と観光
ふるまいよしこさんの記事は長年読ませていただいている。 大手メディアの配信する記事より、信頼できる
-

-
動画で考える人流観光学 脳が心を生み出す仕組み 他者起源説
https://jinryu.jp/blog/?p=43483 ヒトの心はどのように生れ、進化して
-

-
シャマニズム ~モンゴル、韓国の宗教事情~プラス『易経』
シャーマン的呪術は筮竹による数字と占いのテキストを使った方法にかわった。このことにより特殊能力者でな
-

-
QUORA 北方四島問題でソ連は日ソ不可侵条約が有るも拘わらず、終戦直後参戦し北方四島を強奪しましたが、国と国の条約は形式だけで何の意味も持たないのですか?
https://qr.ae/py4JmS 北方領土問題の発端は、大東亜戦争(太
-

-
中国の観光アウトバウンド政策 公研No.675 pp45-46
倉田徹立教大学法学部教授 1997年にアジア通貨危機、2003年にSARS流行発生時、香港経
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
