須田寛「国鉄改革を顧る」(くらしのリサーチセンター)メモと国の交通施策への感想
公開日:
:
最終更新日:2023/04/29
路銀、為替、金融、財政、税制
敬愛する須田寛氏の対談メモ。内容は既に知られていることではあるが、当事者が語ったものとしては数少ない貴重な資料。いずれオーラルヒストリーが発表され、政府高官等の更に詳しい資料が世の中に出てくると思うが、それまでは貴重な資料の一つであろう。
記
○国鉄運賃50%値上げ時を振り返り「新幹線の旅客数の変化を見ると、ピーク時は1975年で、すとんと落ちて1991年まで戻りません」と語る。75年末のスト権ストにつき「労働組合側は1日か2日やったら、国も国鉄も困ってスト権を与えるだろうと思っていたんですね。でもあまり困らなかった」「国鉄の労働争議なのに、国鉄には当事者能力がないので、そういう(政府と組合が話し合う)情けない状態になった」
ここのところは、私も当時運輸省鉄道監督局にいて、国鉄運賃法の改正を実際に担当し、スト権ストを目の当たりにしていたので懐かしい出来事。全日空の株がどうなるか観察していたところ、急騰したので自分も買っておけばよかったと思ったことを思い出す。はやり金もうけには向いていない役人だったのだろう。須田さんは旅客局総務課長でよく運輸省に顔を出されていたことを思い出す。また国会答弁が上手だったことも思い出される。
○実際には本州が一本化されなかったのはどうしてでしょうかという点には「本州だけそのままにしておいたら、また同じことを繰り返すと思われたのではないか」「いまおもえば、政府の分割民営化案でよかったのかもしれない」
私がその後JR東に出向した時に、国鉄改革の連判状組の一人であった若手のリーダー故内田氏が隣の机に座っておられ、国に押し付けられた借金を国に引き取ってもらった後は、再度JRは一本になるのだと語っておられたことを思い出す。しかし、一本になるときの中心であるJR東は、巨大東京圏をもち、他と一緒になる必要性を感じなかったので、その構想は立ち消えになった。もちろん、JR東海も西日本も程度の差はあれ同じであったろう。
○「ただ貨物を別会社にするのが良かったのか私にはわからない」「JR東海や北海道のように、貨物の依存度の高い会社は、貨物への持ち出しが多い」「東海の場合、本当に頂くべき使用料の半分くらいしかもらっていない」「第三セクターが各地にできますが、国が補助してフルコストを払う。貨物会社は今もって一人立ちできない体質」「地域別に分割して旅客会社に割り振った方がむしろ良かったのではないか」
貨物会社については、物流の勉強をしていて、当時心情的に別会社に賛成であった。日通の意向が強く働いたように思う。寺田さんという日通総研出身の人が広瀬真一氏(運輸・国鉄OBで元日通社長)の秘書的な仕事をしていたので、広瀬氏の意向が別会社であったように聞かされていた。しかし、私はその後JR東に出向し、やはり地域別の方がよかったと思うようになった。当時の副会長の山之内秀一郎氏も同じ考え方をされていた。貨物の取り分の半分は通運会社に行く構造で、日通とJR東の交渉であれば、日通に強く臨めるが、貨物会社では日通に強く臨めない。その結果無駄な税金が投入されてしまうことになった。
○5兆円で買わされたことに「東北上越、東海道、山陽の新幹線をそれぞれ営業係数99にするため、逆算して東海道を5兆円でかわされた」「JR東海はいまも2兆円の返済中。この債務がなければとうにリニアは着工している」
「当初は数年に一度値上げをする計画。バブルの一番景気が良かった時にスタートしたので、3~4年間で新幹線のお客様が3割も増加。結果的に値上げせずに済んだ」
この点の追加的な重要点は、JR東海は、国からの負担が少なければ、東海道新幹線運賃が更に安く設定されたか、あるいはリニアが早く開業することこととなったであろうから、東京・大阪間の航空輸送に大きな影響が出たはずであることである。羽田の発着枠や関西国際空港の問題の展開も大きく変化していたであろう。
関連記事
-

-
観光学を考える 『脳科学の教科書 神経編・こころ編』岩波書店 理化学研究所脳科学総合研究センター編 をよんで
図書館でこの二冊を借りてきて一気に読む。岩波ジュニア選書だから、子供が読む本だけれど私にはちょうどい
-

-
2013.8.19 そして預金は切り捨てられた 戦後日本の債務調整の悲惨な現実 ――日本総合研究所調査部主任研究員 河村小百合
ここで紹介されている「 昭和21年10月19日には、「戦時補償特別措置法」が公布され、いわば政府に
-

-
日本人が海外旅行ができず、韓国人が海外旅行ができる理由 『from 911/USAレポート』第747回 「働き方改革を考える」冷泉彰彦 を読んで、
勤労者一人当たり所得では、日本も韓国も同じレベル 時間当たりの所得では、日本は途上国並み これで
-

-
動画で考える人流観光学 「日韓露」つなぐ唯一の航路廃止
「日韓露」つなぐ唯一の航路廃止、累積赤字41億円…一度も黒字化できず 2020/0
-

-
保護中: 『from 911/USAレポート』第827回 「アベノミクスの功罪と出口シナリオ」冷泉彰彦 これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働集約型の観光業を主要産業とするという、どう考えても悲劇的な産業構造に追い詰められた、これは7年半にわたって改革に消極であったことのツケにしても、随分と妙な方向になったと思います
結果的に、これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働
-

-
人流ビジネスと利用運送
旅客運送事業法が設備の数量規制を行っていた時代は、旅客運送行為は運送事業者が自ら行うことが前提となっ
-

-
1936年と2019年のホスピタリィティ比較
『ビルマ商人の日本訪問記』ウ・ラフ著土橋康子訳を読むと、 1936年当時の日本の百貨店のことを、店
-
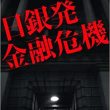
-
英国通貨がユーロでない理由 志賀櫻著「日銀発金融危機」
ポンド危機と英国通貨がユーロでない理由 サッチャー政権
-

-
フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで
観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる
-

-
ブロックチェーンと白タク、民泊シェアリングエコノミー 『公研』2018.12.No.664 江田健二×大場紀章 を読んで考える
白タクや民泊は、絶えずその有償性が問われて、既存業界の攻撃の的になる。無償であれば全く問題がない

