歴史は繰り返す遊興飲食・宿泊税とDMO論議
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務, 路銀、為替、金融、財政、税制
デスティネーションを含んだDMOなる言葉が独り歩きしている。私がカタカナ用語のデスティネーションを聞いたのは、例の国鉄のデスティネーション・キャンペーンだから、古い語感を覚えたものだ。
そのDMOに公的な資金を入れるべきとの観光関係者の意見も最近はよく見かける。海外の例を持ち出す場合もあるが、日本観光協会の助成金の経験から、これも違和感を覚える。
観光関係者の強い政治的意向により、観光関係の財源が廃止になっているからである。今回の国際観光振興税(出国税)が素直に成立したので、私としては何が変わったのかと思ってしまう。
1989年消費税導入に伴い、入場税と通行税は廃止されたが、料理飲食等消費税は特別地方消費税として存続した。都道府県にとって税率が消費税よりも高く重要な財源であったからである。その当時は今日ほど観光に対する政策的期待は高くなく、源泉徴収を行う宿泊、飲食業者は二重課税であるとして廃止運動を展開し、2001年度限りで廃止された。廃止された料理飲食等消費税の1988年度の予算額は、東京都1450億円、大阪府482億円であり、出国税の500億規模をはるかに上回っている。料理飲食等消費税がそのまま存置されていれば観光施策の貴重な財源となったはずであった。 海外の例など参考にすることはないのであり、日本の歴史を知ればいいのである。
その昔、観光は課税対象としては奢侈的ととらえられていた。観光は贅沢なものであり、大衆にかけられるものではないから税金がかけやすかった。太平洋戦争前に設けられた物品特別税は、贅沢品に課税するものであった。贅沢品の消費を抑えるためとされるが、実態は戦争の費用の一部を調達するためのものであった。
大正時代には県や市町村は料理店等における遊興・飲食等に対して、遊興税、歓興税を課税していた。財源確保のためであったから広く課税されていた。その後、支那事変の戦費の一部を調達し奢多的消費を抑えるためとして、通行税及び入場税が設置するとともに、この遊興飲食税を国税に移管した。1940年芸者の花代には20%、その他には10%(終戦直前は芸者の花代300%、遊興飲食100%)課税されていた。
戦後、地方財政の自主強化を目途としたシャープ勧告に基づき、再び地方税に移管されたが名称は遊興飲食税と奢侈的にとらえられていた。1950年から52年までは接客人税も設けられ 芸者、ダンサー等は一人一月について百円を市町村に収めることとされた。さすがに娼妓賦金の変形として好ましいものではなく、廃止の方向を考えるとの認識が国会の議論でもあったが、遊興飲食税の徴収にも便利だということで実施されていた。遊興飲食税の徴収に苦労している税務当局の苦労が垣間見られる対応である。
入場税は、演劇、活動写真、競馬場、舞踏場、ゴルフ場、観物(相撲、野球等のことを言う)を催す場所、博覧会、遊園地等ありとあらゆる娯楽施設が対象とされていた。学生の運動競技大会にも特別入場税として課税されていた。これらも贅沢税として戦費調達目的であったが、ここまで広く課税されると大衆課税であった。地方税であったが、東京等の大都会での税収に寄与したが、消費者の居住する自治体には寄与しないという不満もあり、国税にして人口に応じて地方に配布されるようになった。この時に徴収しづらい映画館等について、娯楽施設利用税と名称を変更して地方税のままにしておいたので、地方担当部局は遊興飲食税に手をつけず、やりやすい入場税に手をつけたと、珍しく政府部内での国会対応が分かれることとなった。
さすがに経済が回復してからは、次第に課税範囲が制限されるようになった。各種スポーツ、芸術、文化団体も自ら国会議員を送り出すとともに、盛んに議員に政治ロビー活動を行った。スケート場がスキー場より先に外れたのも政治運動があったからである。これらの入場税は1989年の消費税実施に伴い廃止されたが、娯楽施設利用税はゴルフ場利用税として現在でも残っている。消費税導入時の時代背景が、ゴルフ場の発言を抑えたものと思われるが、ゴルフも大衆化していから、その後青少年、高齢者に対する非課税措置が図られた。
通行税は、1905年の非常特別税法において日露戦争の戦費調達を目的とした非常特別税の一部として創設された。1910年の改正で独立の税となったが、1926年にいったん廃止された。1938年に復活した後、1940年通行税法が制定された。入場税と同様に当初は広く課税する大衆課税であったが、経済が回復するとともに、課税範囲が縮小され、航空機と国鉄のグリーン車、A寝台にまで限定された。1989年消費税実施とともに廃止された。 遊興飲食税は1961年に料理飲食等消費税に改称され、ようやく遊興の文字は消えた。
関連記事
-

-
『ホテル経営論』徳江純一郎
○○経営論は一般的に使用され、多くの著作物が出されている。経営などしたことのない私だが、縁あってホ
-

-
外国人労働者受入と外国人観光客受入は違うのか違わないのか?~「人流による収斂」と「金流による収斂」~
国際観光が政策として叫ばれているが、その政策的意義が考えれば考えるほどわからなくなってきた。それは移
-

-
観光とタクシー論議 (執筆時 高崎経済大学地域政策学部教授)
最も濃密なCRM(Customer Relationship Management)が可能なはずのタ
-

-
保護中: 『from 911/USAレポート』第827回 「アベノミクスの功罪と出口シナリオ」冷泉彰彦 これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働集約型の観光業を主要産業とするという、どう考えても悲劇的な産業構造に追い詰められた、これは7年半にわたって改革に消極であったことのツケにしても、随分と妙な方向になったと思います
結果的に、これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働
-

-
『戦後経済史』野口悠紀雄著 説得力あり
ドッジをあやつった大蔵省 シャープ勧告も大蔵省があやつっている。選挙がある民主主義では難しいこと
-

-
ブロックチェーンと白タク、民泊シェアリングエコノミー 『公研』2018.12.No.664 江田健二×大場紀章 を読んで考える
白タクや民泊は、絶えずその有償性が問われて、既存業界の攻撃の的になる。無償であれば全く問題がない
-

-
旅館業法の「宿泊拒否」箇所を削除、衆院委で改正案を可決 2023年5月27日読売新聞記事
「衆議院厚生労働委員会は26日、感染症流行時の宿泊施設の対応を定める旅館業法などの改正案について、自
-

-
『国債の歴史』(富田俊基著2006年東洋経済新報社)を読んで
標記図書を読み、あとがきが要領よくまとめられていた。財政に素人の私には、非常に参考になる。 要約す
-
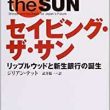
-
『セイヴィング・ザ・サン』 ジリアン・テッド
バブル期に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はア
-

-
『ビルマ商人の日本訪問記』1936年ウ・ラフ著土橋康子訳 大阪は「東洋のベニス」
1936年の日本を見たビルマ人の記述である 1936年当時の大阪市は人口三百万、町全体に大小


