意識あるロボットの出現とホスピタリティー論の終焉
かねがね、観光学研究で字句「ホスピタリティー」が使用されていることに大きな疑問を感じていた。意識あるロボットの研究をする方がよほど研究に資すると考えていたからである。
フロントでロボットが出迎えるホテルが話題になっている。練れていないネーミングであるが宣伝効果はある。 赤坂にもありわざわざ見に行ったが、おもちゃのようなものであった。これをもてはやすようでは、ホスピタリィー研究の退化ではないかと思ったくらいである。中国では、顔認証ができるAIロボットによりホテルのフロントで顧客管理を始めたというから、こちらの方こそ話題にすべきで、日中の格差の将来を感じさせるものである。
深層学習技術によりAIは、認識能力レベルでは既に人間を超えている。従って顔認証システムが導入されている。ベテランのホテルマンよりも素早く認識するから、20年前に宿泊した者にも、お久しぶりですねと声がかけられる。膨大なデータベースを瞬時に活用できるから、顧客の好みを間違えることもない。個人情報の取り扱いが違う中国では、銀行の口座情報から宿泊引き受けを丁寧にお断りすることもあるかもしれない。昨日利用したレストランまでクレジットカード情報で手に入れているかもしれないのである。
脳の可視化も進みつつある。私は2015年に、感性アナライザーを用いて実証実験をした(ブログにもアップしてある)が、実用化は時間の問題である。ウェアラブルデバイスも日進月歩だ。便利になれば今のスマホみたいなもので、万人が着用するであろう。
味覚、臭覚等の非言語情報も数値化が可能となっており、顧客の反応のデータベース化ができる道ができてきた。「お味はいかがでしたか」「お部屋には不都合はありませんでしたか」といちいち野暮な質問をしなくてもウェアラブルデバイス着用の顧客からは正直な反応が得られる。冗談交じりに言えばメイドに対するセクハラの事前予防も可能である。
しかしながら、フロントのロボットに心をあたえるには、人間の脳の仕組みを完全に理解しないとできない。
周りの環境は動物にその意味を与える。与えるという意味からアフォーダンスというが、そのアフォーダンスに対して活動する神経細胞であるカノニカル・ニューロンも発見されている。アフォーダンスには記号操作は必ずしも必要ではない。他人の身体と自分が相互作用する物体のそれぞれを認知するシステムが備わっているのである。
優秀なロボットにはカノニカル・ニューロンが必要である。 我々は通常6万の語彙を持っている。この膨大な数の単語をお互いの関係まで含めて、ほとんど他の人から教わることもなしに心内辞書を作成してしまう。「嫌い嫌いも好きのうち」と理解するのは奇跡的な出来事であるから、当分の間、すべてをロボットに奪われることはないであろうが、宿泊業従業員にとって代わるのは時間の問題かもしれない。
私は概念として観光とツーリズムを使い分ける研究者には、英文でその違いを記述することが如何に困難であるかを説明してきた。このブログでも何度も記述している。字句「tourism」が宙に浮いてしまうからである。概念ホスピタリティーの場合、字句「hospitality」と同義だとするならば、逆に日本語を造語し字句「ホスピタリティ」の使用をやめてもいいはずである。ましてや人の移動を前提とする観光活動の一部として論じるのであれば、移動を前提としないものと字句の使い分けをしておかないと混乱が発生するから、ホスピタリィティもhospitalityも議論の足りない概念であり字句なのであろう。
オリンピック誘致で「おもてなし」が話題になった。でも海外メディアではホスピタリティ、トリートメントと翻訳されて報道されたから、あくまで国内の話題であった。何のために議論するかを明確にして、字句を選択しなければならない。観光客の心の満足をいかに提供するかということであれば、観光客以外の者への心の満足を提供するかとの違いを明確にして議論を進めなければならないが、結局観光の定義問題に行き着いてしまう。
関連記事
-
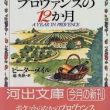
-
『プロヴァンスの村の終焉』上・下 ジャン=ピエール・ルゴフ著 2017年10月15日
市長時代にピーターメイルの「プロヴァンスの12か月」読み、観光地づくりの参考にしたいと孫を連れて南仏
-

-
『芸術を創る脳』酒井邦嘉著
メモ P29 言葉よりも指揮棒を振ることがより直接的 P36 レナードバースタイン 母校ハー
-

-
by them 美しい日本、なのか?海外で気づいた「衛生」意識の違い
新型コロナウイルスに対する不安は、外出禁止令や緊急事態宣言が緩和されたあとでもしばらくは拭えない。
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進
-

-
世界人流観光施策風土記 チベット旅行の検討から見えてきたこと
物流行政をしていたころ、港湾運送事業者が、貿易手続きが複雑なことが自分たちの仕事が存在する理由だとし
-
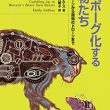
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
-

-
広田照幸著『日本人のしつけは衰退したか』を読んで
日本人の車内でのマナーが良いとか、駅のトイレがきれいだと自画自賛する傾向が強い。しかし、国鉄末期の駅
-

-
保護中: 池谷裕二氏の一連の「脳と心」にかんする著作を読んだメモ
外の世界は「目」を通して第1視覚野に写し取られ、そのあと、色に反応する第4視覚野や動きを見る第5視覚
-

-
「脳コンピューター・インターフェイスの実用化には何が必要か」要点
https://www.technologyreview.jp/s/62158/for-brain-
-

-
書評『ロボットと生きる社会』
新井紀子 AIが下す判断と人間が下す判断は違う AIは基本は検索。人間は実験ができないので科学的に
- PREV
- 歴史は繰り返す遊興飲食・宿泊税とDMO論議
- NEXT
- 『市場と権力』佐々木実を読んで
