旅館業法論議 無宿人保護(旅館業法)と店子保護(不動産賃貸)の歴史
公開日:
:
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務, 民泊問題
◎東洋経済の記事
見出しにつられて読んだが、アマゾンのたとえはあまり適切ではないだろう。
これまで不動産業界で電子化が進まなかった理由は、「不動産業界がITに及び腰というよりも、むしろ賃貸借契約が法律でがんじがらめに規制されているためだった。 宅地建物取引業法(宅建業法)は物件概要や契約条件などが記載されている「重要事項説明書(重説)」について、専門の資格を有した宅地建物取引士が対面で説明しなければならないと規定しており、これが電子化を阻む要因」と解説しているが、旅行業界が2000年ころに直面した問題に類似する。旅行業界ではその昔に解決済みであるが、不動産取引では無産階級出征兵士の留守家族を守る戦時法制の借地借家法以来の伝統的店子保護の精神が 行き届いていたから旅行業ほど簡単には進まなかった。しかし定期借地借家権も創設され時代も変化した。
同記事は「2017年10月よりテレビ電話などを介した「IT重説」が解禁され、説明を聞くためだけに来店する必要はなくなった。それでも契約成立時には書面を交付しなければならず、手続きの完全なペーパーレスには障壁が残っていた。だが、これはあくまで「仲介」の場合だ。物件の貸し主が直接借り主とやりとりする場合には、宅建業法の射程外となり重説の必要はない。自ら貸し主となるサブリースはこれに当たる。すでにアパートのサブリースを展開するレオパレス21が「貸し主」としての立場を生かして、2015年11月より直営店で契約の電子化を進めているが、OYO LIFEもこの空隙を突いた」としてアマゾンになぞらえたのである。
しかし、記事にすべき主眼は下記内容にあると考える。
「仕掛けたのはインド発のホテル運営会社OYO(オヨ)だ。OYOはインドのほか、インドネシアや中国、イギリスなど世界8カ国で事業を展開する。日本ではヤフーと共同で「OYO TECHNOLOGY&HOSPITALITY JAPAN(商標:OYO LIFE)」を設立した(OYO66.1%、ヤフー33.9%出資)。日本ではホテルではなく、賃貸住宅事業に進出する。その理由についてOYO LIFEの勝瀬博則CEOは、「日本の賃貸住宅市場は約12兆円と、ホテル市場の10倍。ホテルは競争が激しいが、賃貸住宅ではホテルのように合理的な商品やシステムが成熟していない」と語る。「OYOはリビングスペースを提供する会社。賃貸住宅とホテルとの間に明確な違いは見出していない」(同)。」「 狙うのは、自分のライフスタイルに合わせて住居を転々とすることに魅力を感じる若い世代。退去にかかる金銭的、時間的コストを最小限に抑えることで、春は桜の見えるところ、夏は海に近いところといったように、気軽に住み替える需要を掘り起こす 」という点である。
ここでも旅館業法の間違った解釈が横行している。「 利用日数を原則30~90日としたのには理由がある。まず最低利用日数の30日は、1カ月未満の利用が旅館業法に抵触しかねないためとし、「「民泊に進出する気はない。賃貸と一緒に展開することにはリスクがある」(勝瀬CEO)。さらに90日を超えると、法律上「一時使用目的の建物賃貸借」と認定されないリスクがある。そのためOYO LIFEでは、90日を超えて住む場合、改めて書面で定期借家契約を結ぶようにした。この点で、自慢の「契約電子化」が完全に実現したわけではない」と解説する。 「1カ月未満の利用が旅館業法に抵触しかねないため」 という点はおかしいが、事業家として旅館業界の横暴に押される可能性のある行政とはことを構えたくないということであろう。私は下宿営業の定義の一か月がそのまま論理的に宿泊の定義に直結するわけがないと思っているから、内閣法制局の公式見解をもとめるなり、訴訟で明確化すればいいと思っている。
いずれにしても、宿と住の相対化現象なのである。一極集中に対抗して地方分散や二重居住などというスローガンを掲げるよりも、住と宿が相対化すれば、一極集中自体の概念も変化するのである。
◎ コンテナで暮らす新生活 ”車輪付き”コンテナホテルも人気 貨物だけじゃない!「コンテナ」に革命
◎インドから上陸「不動産業界のアマゾン」の正体の記事 OYO
関連記事
-
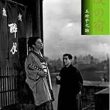
-
『大阪の宿』水上瀧太郎著 小説 映画
東京のサラリーマンが転勤で大阪の下宿屋に暮らした2年間を描いたもの。小説では大正時代(「大正十四
-

-
泊食分離のコンプライアンス 違法旅館・泊食抱合販売
Facebookの書き込みを見ていると、泊食分離論議が出ている。驚いたことに食事つきでなければ宿
-

-
旅籠とコンテナは元来同義 自動運転時代を予感 『旅館業の変遷史論考』木村吾郎
世界各国、どこでも自動車が走行している。その自動車の物理的規格も公的空間では世界共通であり、道路の規
-

-
newspicks のコメント紹介 米国の場合は、住居を宿泊施設として紹介することは法的にできない
NAKAJIMA NAOTO( 30年間米国LAに暮らし、LAをベースに米国内、欧州、アフリカなど
-

-
民泊仲介業標準約款への疑問
民泊と旅館の制度矛盾が感じられます。 旅館業法の唯一の法律事項は宿泊引受義務です。しかし、旅行業法
-

-
生産性向上特別措置法(規制のサンドボックス)を必要としない旅行業法の活用
参加者や期限を限定すること等により、例えば道路運送法の規制を外して、自家用自動車の有償運送の実証実験
-

-
一見さんお断りの超一流旅館のコンプライアンス
インバウンドブームがまだ本格的に始まる前、大連にある大学の観光学の教授から、中国の富裕層を数人日本
-

-
民泊×助成金セミナー「助成金活用型民泊オールインパック」に参加して 2016年7月26日 渋谷クロスタワー32階
24日お昼にFACEBOOKの広告に表記の案内がアップされ、偶然に目に留まった。さっそくFACEBO
-

-
『旅館業の変遷史論考』木村吾郎
第1章 「旅篭屋」「湯治宿」から「旅館」への業名変遷過程 江戸時代は「旅籠 」で、


