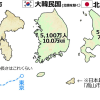『大阪の宿』水上瀧太郎著 小説 映画
公開日:
:
最終更新日:2023/05/27
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務
東京のサラリーマンが転勤で大阪の下宿屋に暮らした2年間を描いたもの。小説では大正時代(「大正十四年十月から同十五年六月まで九回に亙って、當時大阪プラトン社発行の雑誌「女性」に連載された。父親は大阪東区で生まれているんので、この時代なのである)、映画では戦後初期。下宿のことが知りたくて調べたのである。
大阪の中之島に水上瀧太郎(本名:阿部章蔵)の記念碑がある。
小説は青空文庫で無料で読めるhttps://www.aozora.gr.jp/cards/000800/files/51211_53589.html
普通の宿泊料ではやりきれないので、男のやうな口のきゝ方をする大柄おほがらのかみさんに談判して、月極つきぎめにして割引いて貰ふ事にした。
次の日、三田は又大鞄と夜具と机を積んだ荷車の後あとを押して引越して來たのである。
旅館業法が、下宿と旅館を同じ法律で規定している事情が肌で納得できるものである。
以下次のサイトから引用
http://www.tokyo-kurenaidan.com/minakami-osaka1.htm
水上瀧太郎(本名:阿部章蔵)が大阪に転勤して最初に住む下宿がこの天満橋近くの高橋館です。水上瀧太郎の小説「大阪」の主人公三田が下宿を探しに天満橋近くに行く場面です。「…行過ぎる電車の中に、天満橋行というのがあるので、迫かけて飛乗った。四つ五つ停留場を週ぎて、川上の遠く霞んでいる長い橋を素晴らしい音を立てて渡ると、其処が終点で、その橋が天満橋だった。目の前の坂を上るのが、即ち南へ上るのだろうと思った。…」。水上瀧太郎は大阪での経験をそのまま小説にしています。私も勤務した大阪陸運局が天満橋にあったのでこの辺りは懐かしい。
水上瀧太郎(本名:阿部章蔵)が大阪で二番目に住む下宿がこの旅館照月です。「大阪の宿」で書かれている下宿屋がここになります。島町通の城西館(高橋館)は一年ほどで出て、土佐堀の酔月(旅館照月)に移っています。「…三田は、大阪へ来て、まだ半年にしかならない。其間、天満橋を南へ上る、御城の近くの下宿に居たが、因業食欲吝薔の標本のような宿の主人や、その姉に当る婆さんが、彼のおひとよしにつけ込んで、事毎に非道を働くのに憤慨し、越して行く先も考えずに飛出してしまった。…… 「安うて居心のえゝ宿屋やったらな、土佐堀の酔月や。」 厚ぼったい唇をなめながら、鍋の上につんのめりそうな形だった。…… 三田は酒のみの癖に酔払が嫌いなので、何を云われても取合わなかったが、酔月という名を忘れなかった。そして翌日会社の帰りに土佐堀の川岸を順々に探して行って、此の家を見つけたのである。…三田が会社へのゆきかえりに通る、教会の真向の家というのは、二階建の二軒長屋で、天井の低い二階も階下も、おもてに向いた方はすべて格子造で、それを紅殻で塗り、入口のくゞりの中は土間になっていて、裏口迄つきぬけているといったような古風なものだった。格子窓の障子のあいている事はあっても、内部は光線が充分はいらないので、人が居るのか居ないのかわからなかった。屋根も廂も、恐らくは土台迄も傾いた古家で、此の新しいもの好きでは今正に東京を凌駕して亜米利加に追随しょうと云う大阪に、不思議にも多く残っている景色である。近松や西鶴の描いた時代から、今日迄立腐れつゝ焼残ったものであろう。 その長屋から前帯結んだおかみさんでも出て来るのなら似合わしいが、年ごろの綺麗な娘が住んでいるとは、ついぞ想わない事だった。…」。
<土佐堀川>
土佐堀川北側から川を挟んで見た酔月(旅館照月跡)です。「…淀川へ上る舟、河口へ下る舟の絶え間無い間を縫って、方々の貸舟屋から出る小型の端艇が、縦横に漕廻る。近年運動事は東京よりも遥かにさかんだから、女でも貸端艇を漕ぐ者が頗る多い。お店の小僧と女中らしいのが相乗で漕いでいるのもある。近所の亭主と女房と子供と、一家総出らしいのもある。丸吉や銀杏返の、茶屋の仲居らしいの同志で、遊んでいるのもある。三田もふいと乗ってみる気になって、一人乗の端艇を借りたのが病つきになり、天気のいゝ日には、大概晩食後、すっかり暮れきる迄の時間を水の上に過した。…… 中流に漕ぎ出したのにむかって、岸の女はなおからかいやまなかった。宿屋の縁側にも、亭主とおかみさんらしいのが、此方を指さして何か話合っていた。娘は袂を顔にあてて、愈いようつむいてしまった。 端艇はどんどん上流に滴った。橋をくゞると、もう酔月は見えなかった。三田は汗をかく迄踏張って、中之島の方迄漕いで行った。…」。三田はこの土佐堀川をボートで漕いでいたようです。現在は護岸が高くて貸しボート屋などはありません。

写真の正面やや右側の高いビルがYMCAです。護岸の茶色のビルの左側三軒目が酔月(旅館照月)跡です。
「天子様の赤子のひとりやさかい」とは老人の言葉です。天皇が、庶民の意識の中に、ここまで浸透していることに驚きます。
天皇は、明治のはじめには武士や皇族以外の一般庶民には知られてませんでした。明治天皇はその存在を日本国民に知らせるため「天皇告知キャンペーン」とでも言うべき、100回近い全国巡行をしています。
関連記事
-

-
Google戦略から見るこれからの人流・観光(東京交通新聞2014年6月23日)
『モバイル交通革命』の出版から11年がたちます。スマホに代表されるように『位置情報研究会』での論議以
-

-
民泊仲介業標準約款への疑問
民泊と旅館の制度矛盾が感じられます。 旅館業法の唯一の法律事項は宿泊引受義務です。しかし、旅行業法
-

-
泊食分離のコンプライアンス 違法旅館・泊食抱合販売
Facebookの書き込みを見ていると、泊食分離論議が出ている。驚いたことに食事つきでなければ宿
-

-
保護中: 🌍🎒シニアバックパッカーの旅 トリエステ(イタリア特別自治州🏳🌈㊳) 旅行準備資料 アルベルコ・ディフィーゾ
◎Stop Flixbus Trieste
-

-
東京オリンピック・パラリンピック時代の医療観光(日本医療・病院管理学会講演要旨)
都市の魅力を訪問客数で競う時代になっている。ロンドン市長が世界一宣言を行ったところ、パリが早速反駁し
-

-
2016年3月1日朝日新聞8面民泊関連記事でのコメント
東京都大田区が、国の特区制度を活用して自宅の空き部屋などを旅行者に有料で貸し出す「民泊」を解禁
-

-
旅籠とコンテナは元来同義 自動運転時代を予感 『旅館業の変遷史論考』木村吾郎
世界各国、どこでも自動車が走行している。その自動車の物理的規格も公的空間では世界共通であり、道路の規
-

-
newspicks のコメント紹介 米国の場合は、住居を宿泊施設として紹介することは法的にできない
NAKAJIMA NAOTO( 30年間米国LAに暮らし、LAをベースに米国内、欧州、アフリカなど
-

-
井伏鱒二著『駅前旅館』
新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は