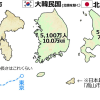『旅館業の変遷史論考』木村吾郎
公開日:
:
最終更新日:2023/05/27
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務
第1章 「旅篭屋」「湯治宿」から「旅館」への業名変遷過程
江戸時代は「旅籠 」で、その意味はコンテナのこと。「旅館」が使われなかったのは漢語であり、官庁御用達のイメージがあった。囚人も宿泊した。
明治に宿駅制度が廃止になり旅籠もなくなる。
もう一つの流れに、湯治宿があり、 三週間一巡り(一週間もある)の長期滞在。
旅館の屋号化は大正時代に広がった。
旅館とホテル、下宿に区分。旅館は一泊二食、ホテルは食事なしと記述。ではなぜ、ホテルは食事がなかったのか。
外国人には朝食がないと不便ではないか。戦後の国際観光ホテル整備法とは逆の思想。
旅館は、その昔は食事など出さなかったと思えるが、いつごろから二食付きになったのか。それが戦後の旅館業法ではなぜ外れたのか。研究課題が多くある。
第2章 鉄道駅の設置と「駅前旅館」の出現
えきべん白木屋 高野商店
第3章 鉄道省の観光旅行客増強対策事業
第4章 経営改善と近代化意識の高まり
第5章 昭和戦前期の旅館の統計記録と経営環境
第6章 宿屋・旅館同業組合組織の変遷
第7章 国際観光事業の復活と旅館の組織化対応
第8章 日本観光旅館連盟と日本交通公社協定旅館連盟
第9章 戦後復興期から平成期への変遷過程―量的成長の限界と質的成長への方向
第10章 ホテルの成長発展と旅館への影響
第11章 観光旅行需要拡大化の態様と旅館の対応
関連記事
-

-
動画で考える人流観光学 【コンテナホテル宿泊記】災害時は移動して大活躍
こうなると、自動運転機能が付随すると、社会は大きく変わるかもしれない。まさに、住と宿の相対化である。
-

-
Oneida Community Mansion House
https://www.bbc.com/reel/playlist/hidden-historie
-

-
泊食分離のコンプライアンス 違法旅館・泊食抱合販売
Facebookの書き込みを見ていると、泊食分離論議が出ている。驚いたことに食事つきでなければ宿
-

-
旅館業法論議 無宿人保護(旅館業法)と店子保護(不動産賃貸)の歴史
◎東洋経済の記事 https://toyokeizai.net/a
-

-
保護中: 🌍🎒シニアバックパッカーの旅 トリエステ(イタリア特別自治州🏳🌈㊳) 旅行準備資料 アルベルコ・ディフィーゾ
◎Stop Flixbus Trieste
-

-
WEDGE2016年3月23日 中国民泊の記事を読んで
日本市場に吹き荒れる「中国民泊」旋風 http://wedge.ismedia.jp/article
-

-
『ホテル経営論』徳江純一郎
○○経営論は一般的に使用され、多くの著作物が出されている。経営などしたことのない私だが、縁あってホ
-

-
Google戦略から見るこれからの人流・観光(東京交通新聞2014年6月23日)
『モバイル交通革命』の出版から11年がたちます。スマホに代表されるように『位置情報研究会』での論議以
-

-
民泊仲介業標準約款への疑問
民泊と旅館の制度矛盾が感じられます。 旅館業法の唯一の法律事項は宿泊引受義務です。しかし、旅行業法
- PREV
- 賃金統計不正
- NEXT
- 観光概論にみる字句「観光」の説明