泊食分離のコンプライアンス 違法旅館・泊食抱合販売
公開日:
:
最終更新日:2023/05/27
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務
Facebookの書き込みを見ていると、泊食分離論議が出ている。驚いたことに食事つきでなければ宿泊を断ればいいという暴論が出ていた。
旅館経営者はプロであり、違法民泊云々といっている者が多いので、当然順法精神があると思っていた。しかし、旅館業法を理解していないで営業していることに驚いた。これでは違法民泊と言って騒いでいる人達のコンプライアンス精神が疑われるのである。
戦後24年に旅館業法が制定されたのは、最終列車で終着駅等に到着しても宿泊することろがないと治安が悪くなるという、当時の発想から、旅館に宿泊引き受け義務を課すことにした。当然権利義務にかかわることなので法律が必要であったから、内務省の系統の厚生省の所管法令として、旅館業法が制定された。運輸省(観光庁)ではないことに注意しないといけない。
旅館の定義として、国会(参議院)で修正があり、「寝具を用いて有償で宿泊させる」と規定がなされた。下宿や簡易宿所も含まれる。無償は当然除外される。親せきや友人の家に宿泊することまで規制する必要はないからである。ここで重要なのは食事のことは法律では触れていないことである。食事は旅館業法の対象外で、あまたある食堂と同じ規制の下にあるということである。保健所の許可を受ければいいのである。カレー屋のカレーも旅館の食事も行政法規の適用は同じである。
食堂には、引受義務はない。いやな客なら断ればいいのである。食堂ではないが、公衆浴場で外国人お断りという張り紙をして、名誉棄損で訴訟になり、慰謝料を払わされた事例がある。しかし、営業停止にはならない。法律違反ではないからである。
旅館は引受義務があるから、正当な理由がないのに宿泊を拒否すると、営業停止になる。黒川温泉でハンセン氏病が治癒した人たちの宿泊を拒否し、営業停止になった例がある。
食事と宿泊を抱合せで販売し、素泊まりだけなら宿泊を拒否すると、旅館業法では、部屋があるにもかかわらず契約を拒否したことになる。食事の抱き合わせ販売になる。宝石を買わないと宿泊を引き受けないということと同じである。
宿泊料の設定において、食事は無料にしておいて食べても食べなくても、料金が同じであれば、違反にはならない。ビジネスホテルの朝食無料がその例である。逆に、朝食代を分離して販売するケースもある。しかし、抱き合わせ販売は違法である。
旅行業法では、旅行契約引受義務がない。試験問題にも出される設問である。従って、パック旅行では食事つきが存在する。
なお、旅館業法の特別法として、外国人誘致を目的にした国際観光ホテル整備法がある。戦後の外貨獲得のための法律であり、進駐軍にホテルを接収されていたことから、ホテルを整備するために制定された。外国人のために、朝食が提供できることを前提としている。宿泊費と食事代を別に表示しなければならないこととなっている。当時はアメリカ人ご婦人のため、野蛮な混浴は回避できますよという意味で、近年まで各部屋にバス設備の設置が義務付けられていた。いまでは、この国際観光ホテル整備法は、固定資産税の減免のための法律になっており、時代遅れのものとなっている。フランスでは、五つ星ホテルの税金の方が高いものだから、あえて四つ星にしているホテルがあるくらいである。
関連記事
-

-
生産性向上特別措置法(規制のサンドボックス)を必要としない旅行業法の活用
参加者や期限を限定すること等により、例えば道路運送法の規制を外して、自家用自動車の有償運送の実証実験
-

-
動画で考える人流観光学 【コンテナホテル宿泊記】災害時は移動して大活躍
こうなると、自動運転機能が付随すると、社会は大きく変わるかもしれない。まさに、住と宿の相対化である。
-

-
井伏鱒二著『駅前旅館』
新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は
-

-
観光とタクシー論議 (執筆時 高崎経済大学地域政策学部教授)
最も濃密なCRM(Customer Relationship Management)が可能なはずのタ
-
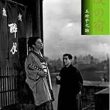
-
『大阪の宿』水上瀧太郎著 小説 映画
東京のサラリーマンが転勤で大阪の下宿屋に暮らした2年間を描いたもの。小説では大正時代(「大正十四
-

-
『地方創生のための構造改革』第3章観光政策 論点2「日本における民泊規制緩和に向けた議論」(富川久美子)の記述の抱える問題点
博士論文審査でお世話になった溝尾立教大学観光学部名誉教授から標記の著作物を送付いただいた。NIRAか
-

-
newspicks のコメント紹介 米国の場合は、住居を宿泊施設として紹介することは法的にできない
NAKAJIMA NAOTO( 30年間米国LAに暮らし、LAをベースに米国内、欧州、アフリカなど
-

-
WEDGE2016年3月23日 中国民泊の記事を読んで
日本市場に吹き荒れる「中国民泊」旋風 http://wedge.ismedia.jp/article
-

-
旅行業法の不思議② 宿泊引受義務と民泊(Airbnb)論議
Airbnbは、同社にとって最も成長率の高い市場である日本において、登録物件の近隣に住む住民が苦情を

