畑中三応子著『ファッションフードあります』日本食は変化が激しい。フードツーリズムに法則があるのか?
公開日:
:
伝統・伝承(嘘も含めて), 観光資源, 観光資源の均一化
ティラミス、もつ鍋、B級グルメ……激しくはやりすたりを繰り返す食べ物から日本社会の一断面を切り取った痛快な文化史。年表付。解説 平松洋子
新しくなきゃ、おいしくない!―ファストフードからエスニック料理、B級ご当地グルメやカフェ飯まで、次から次へと登場する新しい食べ物と、『アンアン』『ノンノ』といったメディアや、食のイベントなどから発信される価値観。それらをあわせて情報として消費しては節操なく楽しみ、食べつくす日本社会の姿を、皮肉と愛を込めて描く痛快な文化史!年表付
書評1 いち読者の主観だが、この本、まともに読むと結構疲れる。
中身は非常にたっぷりなのだが、上記の通り網羅的。全体を統一するひとつの主張や、視点が存在しない。言い方は悪いが、まとめ方だけだと夏休みの小学生の自由研究レベルである。お菓子や車や伝統工芸といった一項目を、図鑑等で調べてノートに束ねた感じ。もちろん調査方法や編集能力は、小学生の比ではない。しかしやっていることは同等で、少々がっかりする。歴史を俯瞰・紹介することが最大の目的なら、仕方がないのかもしれないが……枝葉を細かく綴るばかりで、幹が見えない。
文章もやや読みにくい。一文が長め&知識濃厚で、目と頭が息継ぎに困る。読破までに七、八時間はかかってしまった。三十分で読める小説とは密が違う。
日本料理は、日本の風土と社会で発達した料理をいう。洋食に対して和食とも呼ぶ。食品本来の味を利用し、旬などの季節感を大切にする特徴がある。和食は2013年に無形文化遺産に登録された。定義がないのではないか???
広義には日本に由来して日常作り食べている食事を含むが、狭義には精進料理や懐石料理などの形式を踏まえたものや、御節料理や彼岸のぼたもち、花見や月見における団子、冬至のカボチャなど伝統的な行事によるものである[7][8]。日本産の農林水産物・食品の輸出も2013年から右肩上がりに伸びている。2016年は7502億円と2012年の4497億円から1.7倍に増え、2017年は8000億円台に乗せた。日本国政府(農林水産省)は1兆円を目標としており、日本食レストランの増加と日本食材輸出を推進している。
関連記事
-

-
AI に書かせた裸婦とダリ
AIに描かせたという裸婦の絵がネットで紹介され、ダリが描いたようだと注釈。 正確にいえば、AIが描
-

-
『「食べること」の進化史』石川伸一著 フードツーリズム研究者には必読の耳の痛い書
食べ物はメディアである 予測は難しい 無人オフィスもサイバー観光もリアルを凌駕できていない
-

-
プロテスタンティズムと現代政治 学士會会報NO.927 2017年Ⅵ 深井智朗 pp24-27
マルティン・ルターによる神聖ローマ帝国の宗教の改革は、彼の意図に反して、すぐに政治化し、彼の死後まも
-

-
伝統は後で作られる例①
日本のサンクチュアリシリーズ 484宮内庁書陵部 皇居の庁舎で天皇・皇族の戸籍簿「皇統譜」や文書類
-

-
保護中: Quoraに見る観光資源 世界で最も有名な詐欺師は誰でしょうか? フェルメール贋作 ナチスを騙した男ーオランダの画家ハン・ファン・メーヘレン
美術オークションの仕事世界で最も有名な詐欺師は誰でしょうか? フェルメール贋作 ナ
-

-
2015年「特攻」 HNKスペシャル
http://www.dailymotion.com/video/x30z4ho フィリピ
-

-
『素顔の孫文―国父になった大ぼら吹き』 横山宏章著 を読んで、歴史認識を観光資源する材料を考える
岩波書店にしては珍しいタイトル。著者は「後記」で、「正直な話、中国や日本で、革命の偉人として、孫文が
-

-
ハイフンツーリズム批判と『「日本の伝統」の正体』藤井青銅著
観光研究者が安易に○○ツーリズムを提唱していることへの批判から、これまで伝統や歴史は後から作れると述
-
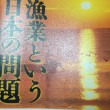
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は

