『帝国陸軍師団変遷史』藤井非三四著 メモ
公開日:
:
最終更新日:2018/10/22
観光資源
薩長土肥による討幕が明治維新ということになっているが、なんと首都の東京鎮台本営に入った六個大隊のうち四個大隊が徳川勢の差出。いくら御一新となって徳川家が恭順の意を表しているといっても、新政府としては不安でなかったのかと不思議だ。その代りに、九個大隊の御親兵がいるということだが、この配置は後述する長州勢の深謀遠慮だ 政府が方針とする四民平等など聞く耳もたぬすぐにでも危険な薩摩兵を分散させ、徳川勢と東京でかみ合わせてけば、双方とも動きがとれまいという長州の発想
戊辰戦争の当時から漢軍は同も兵力が足らず、素質など無視して脱藩浪士、流れ者、果ては博徒までを部隊に組み入れた。これが会津なので乱暴狼藉を働き、その遺恨は今でも忘れられていない。
帰還して伏見付近の河東に設けた屯所に入った。粗暴で手に負えない連中だとなり、兵隊とはこんなものかという思潮が京阪地域に生まれた
国土地図は工兵となった旧幕臣がリード。明治維新における軍事面は、旧幕臣を抜きにしては語れない
昭和6年度 徴兵検査の受検者は62万人、甲種合格者は約18万人、甲種でも8万人は入営しないことになる。抽選。くじ逃れになるお札を配る神社静岡県の龍爪神社が有名
弾除けの神様が徴兵逃れの神様になり、現在では恥もあるのか徴兵逃れはあまりネットでも記述されていない神社が各地にある
/http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/50/1/ssr4-45.pdf
日本の徴兵制の問題は、国民皆兵とはいいながら、実は多くのものが軍事訓練を受けていなかったことにある。概算で約半数しか軍事訓練を受けていない。それが戦時になるとこの未教育の装丁も召集。そのための様々な悲劇が発生 終戦時「これは軍隊ではない。飯場」
師団 フランス語のディヴィジョンの訳 周代の軍政に由来 五単位制で部隊を積み上げていた 五人の「伍」二十五人の「両」一〇〇人の「卒」五百人の「旅」二五〇〇人の「師」そして一二五〇〇人の「軍」。軍は戦車を囲むという意味で全軍を表す。「旅」は「軍旗を押し立ててすすむもの」という意味
今も昔もロシアは謎の軍事大国 ロシアの能力を正しく評価できていたなら、日露開戦には踏み切れなかったであろう
師団の増設 問題のあるものを差し出す部隊に紛れ込ませる。今の役所も同じ?
革命後、「ロシアは軍事大国として再登場する」 これに対して軍部内部ではそういっていないと「ロシア屋」は失業するからなという姿勢 反発がロシア班の橋本欣五郎の桜会 ロシア屋の予測が正しかった 世界の最先端を行く冶金技術をもって大陸軍の成長 この時にソ連軍の実力を正しく評価していれば、満州事変時に北満鉄道を超えて作戦はできなかったはずだ。 昭和6年の陸軍省と参謀本部の課長クラスのメンバーによる国策研究会は国際世論の支持を醸成するという結論であったが、関東軍はその手間を省いて柳条湖で口火を切った
昭和10年時点で、極東ソ連軍 戦車850両航空機950機 日本軍 戦車30両航空機220機 と絶望的な格差 20年8月 関東軍の武装解除に当たったソ連軍は、これで我々と本気でたたたうつもりだったのかと驚いた
参謀本部ロシア班の作成した極東ソ連軍の戦力推移表を見せられた、参謀本部第二課長に就任した流石の石原莞爾も絶句
17年8月のガナルカダル戦いらい失敗の連続 陸海軍の統合が全く形になっていない結果。輸送船団を置き去りにして遁走、それどころかおとり作戦まで。
硫黄島 栗林中将 人事権を大胆に行使 あてがいぶちの人事を受け入れる慣例を破る
絶対国防圏を設定してからの昭和18年末 日本は汽船気帆船あわせて6800隻、五百万総トン保有 連合艦隊もほぼ健在 これだけのシーパワーがあれば大きな航空基地がある島嶼部にそれなりの陸上部隊を送り込むことができたはず
なおざりにされた本土防衛 もし米軍が投機的な性格であったなら、まさに危機
昭和19年2月の人口調査 内地の総人口は7278万人 うち軍隊に在営している者を除く男性人口は3444万人 陸軍290万人、海軍68万人だから動員率は5% 余裕があるように見えるが、農業の問題からそろそろ限界が見えていた
このようなことを見越して18年8月朝鮮において徴兵制を施行して2500万人を動員基盤に加えた。そこで問題が「権利なきところに義務はない」という法理 朝鮮人に選挙権を与えたうえで兵役義務を課する。当面は産業徴用や志願兵で対応
日本陸軍と陸上自衛隊 郷土色部隊が鮮明
関連記事
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-

-
プロテスタンティズムと現代政治 学士會会報NO.927 2017年Ⅵ 深井智朗 pp24-27
マルティン・ルターによる神聖ローマ帝国の宗教の改革は、彼の意図に反して、すぐに政治化し、彼の死後まも
-

-
『維新史再考』三谷博著 NHKブックス を読んで
p.4 維新というと、とかく活躍した特定の藩や個人、そして彼らの敵役に注目しがちである。しかし、こ
-

-
シャマンに通じる杉浦日向子の江戸の死生観
モンゴルのシャマン等の観光資源調査を8月に予定しており、シャマンのにわか勉強をしているところに、ダイ
-

-
観光資源の評価に係る例 米国の有名美術館に偏り、収蔵作品は「白人男性」に集中
https://www.technologyreview.jp/s/117648/more-th
-

-
観光資源・歴史は後から作られるの例
http://www.asahi.com/articles/ASKB05T40KB0ULZU015.
-
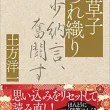
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 資料 ハルハ川戦争 戦跡観光資源
https://youtu.be/RijLPLzz5oU 中国とロシア
