シャマンに通じる杉浦日向子の江戸の死生観
公開日:
:
最終更新日:2023/05/20
観光資源
モンゴルのシャマン等の観光資源調査を8月に予定しており、シャマンのにわか勉強をしているところに、ダイヤモンドオンラインに「江戸の死生観がその生涯に重なる 杉浦日向子の復活」と題した佐高信の記事が出ていた。シャマンは病気を人体から追い出す役割を担っていた。
以下掲載する。
「個人差はあれ、死は特別視されていませんね。頼れる医療技術がないですから、あるがままを受け入れる姿勢になるんでしょう。“生老病死”を春夏秋冬、つまり、季節のうつろいみたいに」 こう言われて、私は、「へえー」と驚き、「医者の数は?」と問いを重ねた。 「多いんですが、ヤブだらけですから。医者の手にかかるっていうのは、死の一歩手前ってことです。まず、加持祈祷して薬を飲んで養生して、それでも治らなかったら、最期の段階として、医者にでもみせておくかという、坊主の前の露払いです」 彼女にはいつも感心させられたが、いまは引用しているだけで悲しい。こんな箇所もある。「江戸が今といちばん違うところは、病に対する受け止め方です。人間は病の器という考え方で、一病息災とも言いますけども、何かしら病があって、それと引き換えに生きて、いい思いしている、厄落としのような観念があるんです」
江戸時代は日本にもシャマンの存在基盤があったということが理解できる。
関連記事
-

-
ヒトラー肝いりで建造の世界最大のホテル・プローラ
観光政策というより、福祉政策なのかもしれませんが、現代なら民業圧迫という声が出るでしょう。
-

-
『素顔の孫文―国父になった大ぼら吹き』 横山宏章著 を読んで、歴史認識を観光資源する材料を考える
岩波書店にしては珍しいタイトル。著者は「後記」で、「正直な話、中国や日本で、革命の偉人として、孫文が
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源論 宇宙旅行
https://youtu.be/KpGnwLiTYj8 https://youtu.be/a
-

-
マルティニーク生まれのクレオール。 ついでに字句「伝統」が使われる始めたのは昭和初期からということ
北澤憲昭の『<列島>の絵画』を読み、日本画がクレオールのようだというたとえ話は、私の意見に近く、理解
-
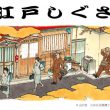
-
伝統は後から創られる 『江戸しぐさの正体』 原田実著
本書の紹介は次のとおりである。 「「江戸しぐさ」とは、現実逃避から生まれた架空の伝統である。本書は
-
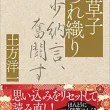
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-

-
『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志著 中公新書 メモ書き
福音書の示すイエスの生涯はほとんどの部分が死の前の2,3年前の出来事 降誕劇は神話 ムハンマドの活
-

-
現代では観光資源の戦艦大和は戦前は知られていなかった? 歴史は後から作られる例
『太平洋戦争の大誤解』p.183 日本人も戦前はほとんど知らなかった。戦後アメリカの報道統制
-

-
伝統は古くない 『大清帝国への道』石橋嵩雄著を読んで
北京語 旗人官僚が用いていた言語 山東方言に基づく独自の旗人漢語を北京官話に発展させた チャイナド


