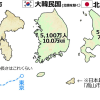『源平合戦の虚像を剥ぐ』川合康著 歴史は後から作られる
公開日:
:
最終更新日:2019/07/02
観光資源
源平の合戦は全国で、観光資源として活用されている。「平家物語」の影響するところが大きい。また、文学作品として中等教育で学ぶ機会が多いことも影響している。世界遺産にも登録されているものがあるが、史実は後世作り直されてもいる。
表記の書物は「平家物語史観」を乗りこえ 内乱が生んだ異形の権力 鎌倉幕府の成立にせまるものであり、観光資源の作り直しにも資するものかもしれない。
同書はアマゾンの紹介では、屍を乗り越え進む坂東武者と文弱の平家公達――。我々がイメージする源平の角逐は、どこまで真実だったのか? 「平家物語史観」に基づく通説に対し、テクストの精緻な読みと実証的な探究によって、鋭く修正をせまる。さらに、源平合戦の実像や中世民衆の動向、内乱の歴史的所産としての鎌倉幕府の成立過程までを鮮やかに解明した、中世史研究の名品となっている。
現在でも、武士を暴力団にたとえ、その武力を超歴史的に批判するような見解は目についても、肝心の武士が「戦士」として行動する「戦争」や「武力」の在りかたについては、まだまだ未解明な部分が多い。……「源平合戦」にロマンを感じておられた方は、少々失望されることになるかもしれないが、本書としてはできるだけ現実的・冷静に、治承・寿永内乱期の戦争の実態を復元し、そのうえで、たんに戦乱の被害者にとどまらない中世民衆の動向や、内乱の歴史的所産としての鎌倉幕府の成立を、検討していきたいと考えている。――<本書「はじめに」より>
駆武者は源氏平家を通じて一般的であり、平家が駆武者が多くて弱かったわけではない
石母田領主制史観:「一荘園を舞台として,在地領主・民衆による古代専制支配の克服過程をダイナミックに描き出したもので,中世を構造的に理解しようとする研究者に大きな影響を与え,戦後歴史学の出発点となった」とされる。 古代国家の傭兵隊長として位置づけられた平家の没落が自明のこととしている点で「平家物語史観:と共通
書評で参考になったもの
http://emasaka.blog65.fc2.com/blog-entry-971.html
源平合戦というと、「貴族化した平氏 vs. 全国の武士を代表する源氏」という図式で伝えられることが多い。頼朝の挙兵とか、富士川の戦いでビビって逃げる平氏とか、義経の活躍とか。で、盛者必衰というまとめに。
本書はそのような「平家物語史観」に対して反論する。そもそも「源平合戦」というのは「治承・寿永の内乱」の一部にすぎず、そのバトルロイヤル状態を勝ち抜いたのが源氏である、という。
また、武士の職能起源論をとり、そうした堂々とした武士像から治承・寿永内乱期に変化した様子を検証。これは平氏も源氏も同様であること、戦い方が変わったことと相互に関連して多くの人が動員され、その戦時体制が鎌倉幕府となったこと、だからこそ武士としての正当性の主張として、その当時でも古い形の武士である「弓馬の道」が鎌倉幕府に推奨されたことなどが論じられる。
このような史観を、一般向けの平易な解説ながら、さまざまな検証をまじえて解説している。上記の本筋以外の部分でも、日本史をよく知らない自分にとってへぇな話がいろいろ続いて面白かった。巻末の解説によると、1996年に刊行された本書が歴史学と国文学に少なからぬ影響を与えたのだとか。
以下、本書からの自分メモ。
- 平家物語史観=源平交替の思想
- 歴史的発展段階として必然視する石母田領主制論から、全国的内乱とする「治承・寿永の内乱」論へ
- 鎌倉幕府は予期せぬ結末
- 軍事的成長をとげた反乱軍がみずからを位置づけていく事態
- 馳射の技術にすぐれていたのは平氏軍
- 富士川合戦では平氏が敗れたものの、1183年初頭までは平氏のほうが優勢
- 駆武者は当時の軍隊の一般的特徴
- 馳組み:今昔物語時代の武士像
- 源平時代の老武者の証言:最近は敵の馬を射たりして組打ちで倒す戦闘が流行してきたことの嘆き
- 相撲、馬当て
- 平安後期:芸能者の一類としての武士
- 武士成立について、在地領主の武装化説への疑問
- 9世紀の狩猟民からの精兵組織 → 類党、説
- 武士は都の貴族社会で発展した説
- 大鎧:近衛次将の装備から発展したものと推定
- 合せ弓:宮廷の儀式で出現
- 騎射:貴族社会の伝統
- 馳組みは至近距離、馬術が大きな比重
- 源平時代:馬を走らせないで弓を引く形態に
- 那須与一
- 掻楯
- 同時多発だった治承・寿永の内乱
- 源平合戦はその一部にすぎない
- 数千・数万規模の軍勢に飛躍的増加
- 農耕馬に乗って出陣するような「器量に堪えうる輩」=小名階層の出現
- 戦闘様式の変化
- 鎌倉幕府が馳射を奨励したのは、それが軽視されていた武装集団を都の伝統を受けつぐ武士に仕立て上げる政治的努力、とする説
- 治承・寿永内乱期の「城塞」=バリケード
- 馬が越えられないようにする
- 石弓
- 戦闘員の拡大による徒歩立ちの軍勢を優位にする
- 決戦の場ではなく、包囲はしても攻城線は避け交渉で開城させるのが基本形態だった、とする説
- 大規模な工事をともなう「城郭」の例も:阿津賀志山二重堀
- 平氏の杣工の大量動員
- 工兵隊
- 兵站指揮官としての梶原景時
- 民衆動員と勧農政策
- 大飢饉
- 兵糧調達:国平均賦課、有徳役、路次追捕(掠奪)
- 夫兵:補給部隊
- 戦場に動員された村人が路次地域の資材を掠奪する事態
- 人取り
- 民衆が資材を守る方法
- 寺社に資材を預ける
- 梶原景時の勝尾寺襲撃
- 頼朝が挙兵したときには、義朝の武士団の多くは平氏軍下にあった
- 「(平家の)恩こそ主」
- 頼朝、武士一人一人を呼んで「汝を恃む」
- 平氏軍政から疎外された東国武士の危機感が頼朝挙兵に
- 路次にあたる国々宿々で国々の輩を動員
- 御家人制:軍事動員の中で形成
- 主人を替えるのはあたりまえの時代
- 文治勅許
- 義経・行家追討のため地頭職の設置を認める、というかつての通説
- 石母田氏、国地頭職の発見
- 川合説:再設置された
- 敵方所領没収=地頭制度
- 占領の継続化
- 平氏は朝廷体制下にあったので敵方所領を自ら家人に与えられなかったが、鎌倉方は反乱軍なので与えられた
- 戦時体制の没官刑システムが朝廷に追認された鎌倉幕府
- 奥州合戦の翌年からの諸政策:朝廷接近政策と御家人政策
- 武家の棟梁として主従関係を設定しなおす
- 奥州合戦は治承・寿永の内乱の頼朝による延長
- はじめて頼朝自身が出陣
- かつて敵方中枢にいて囚人とされていた武士までを動員し、失地回復のチャンスに
- 有力御家人でも不参は所領没収
- 義経反乱以前に計画されていた
- 挙兵時には、源氏の間で「一門更に勝劣なし」
- 頼朝が貴種性を確立するための政策へ
- 藤原泰衡追討:前九年合戦の再現
治承・寿永の内乱
源平合戦の呼称で想起されるような、源氏と平氏がそれぞれの一族を糾合して戦った訳ではないのである。
源氏同士、平氏同士が争う現象は日本各地で見られた。父系で見れば源氏だが、母系で見れば平氏、またはその逆という武将も少からずいて
関連記事
-

-
『帝国陸軍師団変遷史』藤井非三四著 メモ
薩長土肥による討幕が明治維新ということになっているが、なんと首都の東京鎮台本営に入った六個大隊のう
-
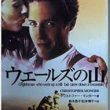
-
観光資源創作と『ウェールズの山』
観光政策が注目されている。そのことはありがたいのであるが、マスコミ、コンサルが寄ってたかって財政資金
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源論 フィリピンセブ島刑務所の囚人ダンス
フィリピンセブ島観光・旅行【決定版】絶対にするべき39スポット&アクティビティ http://ce
-

-
新華網日本語版で見つけた記事
湖南省で保存状態の良い明・清代の建築群が発見 http://jp.xinhuanet.com/20
-

-
『素顔の孫文―国父になった大ぼら吹き』 横山宏章著 を読んで、歴史認識を観光資源する材料を考える
岩波書店にしては珍しいタイトル。著者は「後記」で、「正直な話、中国や日本で、革命の偉人として、孫文が
-

-
伝統は後から作られる例 関西は阪神フアンという伝統
これも学士會会報の記事、何時も面白い話をしてくれる井上章一氏の「ゆがめられた関西像」 戦後しば
-

-
『ピカソは本当に偉いのか?』西岡文彦 新潮新書 2012年 を読んで
錯覚研究会での発表に備えて読んでみた。演題が「ピカソの贋作は本物を超えるか」としたため、慌てて読んで
-

-
本当に日本は職人を尊ぶ国であったのか?
司馬遼太郎氏は、韓国、中国との比較においてなのか、『この国のかたち』のなかで、「職人。実に響きがよ
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 動画で見る世界人流観光施策風土記 モンゴル紀行 メモ書き シャーマン動画 トナカイ解体動画
ツァータン族の居住地の4泊分は、通訳代、移動費を別にして、180万ツグルであった。 ツァーマン
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら
- PREV
- 観光資源、観光行動の進化論
- NEXT
- ジャパンナウ予定原稿 感情と観光行動