観光資源としての明治維新
公開日:
:
観光資源
義務教育やNHKの大河ドラマを通じて、日本国民には明治維新に対するイメージが出来上がっている。
しかし、そのイメージは、歴史学者の考えるものとは大きくずれている。
そのことが、明治維新百五十年にあたり、中央公論の特集記事をはじめとして、改めて浮き彫りにされている。
浮き彫りにされることは好ましいが、観光研究者は改めて自分たちの観光資源論を問い直さなければならない。
観光資源は、研究者の間で文化資源と自然資源に分類することが通例である。
私はそのことを何度も否定して来ているが。
文化財保護法の文化財と文化観光資源も何の疑いもなくほぼ同一視されている。
しかし私は、観光資源は、人間の「興味」が土台であり、フェイクであっても構わないと主張している。
坂本龍馬は武器商・グラバー商会の使い走りであり、吉田松陰は偏狭的なテロリストであると歴史学者はいう。幕府は気にも留めていない小物であったが、自ら過激なことを言って自首してきたので処分せざるを得なかったとする。
そこには、大衆がイメージするものとは大きなギャップがある。
明治維新は決して薩長の下級武士が行ったものではなく、橋本佐内など高級武士が唱えたものの成果だというのが学者である。
忠臣蔵も石川五右衛門も歌舞伎などによりフェイクの部分が多いが、観光客はそれでも楽しんでいるのだから、
高知県や鹿児島県、山口県、京都府は、明治維新の評価が変わっても、観光ビジネスが成り立たなくなるから困るということにはならないであろう。
白虎隊の福島県でも、戊辰戦争はサムライの戦争であり、庶民には関係がなかったとする見方もある。これでは悲劇の観光資源ではなくなってしまう。
しかし、観光研究者の観光資源に関する説明ぶりは、変えてもらわなければならないであろう。一応、サイエンスなのだから。
財団法人JTBは、観光資源台帳を作成し、超A級観光資源を「わが国を代表する資源であり、世界に誇示しうるもの。日本人の誇り、日本のアイデンティティを強く示すもの。人生のうちで一度は訪れたいもの」とするが、「日本人の誇り、日本のアイデンティティを強く示すもの」とするのは表現の行き過ぎかもしれない。フェイクである可能性があるものが含まれていないとは限らない。
関連記事
-

-
『明治維新を考える』三谷博 有志舎 2006年
序章 明治維新の謎 維新という言葉 幕末から頻用されてきた「一新」という言葉を中国の古典に置き換え
-

-
『帝国陸軍師団変遷史』藤井非三四著 メモ
薩長土肥による討幕が明治維新ということになっているが、なんと首都の東京鎮台本営に入った六個大隊のう
-

-
シャマンに通じる杉浦日向子の江戸の死生観
モンゴルのシャマン等の観光資源調査を8月に予定しており、シャマンのにわか勉強をしているところに、ダイ
-

-
マルティニーク生まれのクレオール。 ついでに字句「伝統」が使われる始めたのは昭和初期からということ
北澤憲昭の『<列島>の絵画』を読み、日本画がクレオールのようだというたとえ話は、私の意見に近く、理解
-

-
『素顔の孫文―国父になった大ぼら吹き』 横山宏章著 を読んで、歴史認識を観光資源する材料を考える
岩波書店にしては珍しいタイトル。著者は「後記」で、「正直な話、中国や日本で、革命の偉人として、孫文が
-

-
蓮池透・太田昌国『拉致対論』めも
p.53 太田 拉致被害者家族会 まれにみる国民的基盤を持った圧力団体 政府、自民党、官僚、メディ
-

-
伝統論議 蓮池薫『私が見た「韓国歴史ドラマ」の舞台と今』
〇 蓮池氏の著作 「現代にも、脈打つ檀君の思想、古朝鮮の魂』などをよむと、南北共通の教育があること
-

-
『公研』 2018年2月号 「日本人は憲法をどう見てきたか?」
歴史は後から作られるの例である。 境家史郎氏と前田健太郎氏の対談 日本国民が最初から憲法九条
-
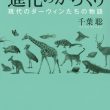
-
進化論 宗教と進化論 『進化のからくり』千葉聡 ガラパゴス島が観光資源になる過程の材料として面白い
イスラム教と進化論、初期キリスト教と進化論 https://youtu.be/i_lrAKC3
-

-
歴史は後から作られるの例 「テロと陰謀の昭和史」を読んで
井上日召の「文芸春秋臨時増刊 昭和29.7 p.160「血盟団」の名称は、木内検事がそう呼んだので
