筒井清忠『戦前のポピュリズム』中公新書
p.108 田中内閣の倒壊とは、天皇・宮中・貴族院と新聞世論が合体した力が政党内閣を倒した。しかし、腐敗した内閣であっても野党によって倒されるのが健全な議会政治。
二大政党時代に、その健全な育成に意を注がなかった。吉野作造もその典型である。
天皇の政治的シンボルとして肥大化が、後の天皇型ポピュリズムを導き出すことになったが、政党人にはその自覚に乏しかった。
p.112 田中内閣辞職後、1929年浜口内閣の成立 緊縮財政政策 全官吏の俸給一割削減声明を出すと、行政官より廉給の判事・検事とともに、鉄道省の官吏が反対運動開始し、撤回される。この時「天皇は文武官の俸給を定める」という大権の干犯とする批判が政友会内部に登場したが、政争にはしなかった。しかし翌年の総選挙大敗後統帥権干犯問題を持ち出す。
天皇型ポピュリズムに走るのは政治的に苦しい立場に立たされた時なのである。
帝人事件
でっち上げの背後にいたのは、司法官僚出身で当時枢密院副議長の平沼騏一郎とされる。平沼は五・一五事件で暗殺された犬養毅の後継内閣総理大臣の地位を狙っていたが、後継の推薦権がある元老・西園寺公望からその志向をファシズム的であるとして嫌われ、推薦候補にすら上らず、また枢密院議長昇格の要望も西園寺の反対で副議長のまま置かれていた。このため、西園寺とこれを支持する立憲政友会主流派(但し、同党総裁であり平沼直系の鈴木喜三郎も西園寺により後継総理就任を阻止されていた。)を深く恨んで、同党内部の不満分子を抱き込みながら捜査を進めていったという。
また時事新報が記事を書いたのは、丁度この頃、朝日新聞の東京進出が云われており、焦ったためだという[1]。
のちに河井信太郎が帝人事件を評して、次のように語っている。
「塩野季彦司法大臣の大英断により控訴を断念したが、検事が証拠品の検討を怠っていたことが無罪の致命傷になった。掛物によく描かれている、水の中の日影を猿が藤蔓につかまってしゃくろうとしている画になぞらえて、影も形もないものを一生懸命にすくい上げようとしているのが検察の基礎であって、検察には争うことができなかった。」[2]
福沢諭吉は「福翁自伝」の中で、西洋の議会で党派に分かれて対峙し、議論を
戦わすというスタイルが果たして日本人に馴染めるものかと、正直に違和感を
感じたと語っていましたが、本書176頁あたりでも触れられているように、大正
から昭和初期にかけての政党政治の全盛時代、政友会と憲政党が競い合っていた
時代の、殊に地方の状況は醜悪きわまりなく、末端に至るあらゆる組織がそれぞれ
の党派ごとに分裂し、互いに反目しいがみ合い、感情的に対立した挙句、時には
暴力沙汰になるようなありさまだったと、小さいころに父に教えられたことがあり
(父も生まれる前のことですが)、これが民主政体の受容における日本人の実力
であったことは、肝に銘じておく必要があります。
本書の章立ては、次の通り。第1章「日比谷焼き打ち事件」、第2章「大正期の大衆運動」、第3章「朴烈怪写真事件」、第4章「天皇シンボルとマスメディア」、第5章「統帥権干犯問題と浜口雄幸内閣」、第6章「満洲事変とマスメディアの変貌」、第7章「五・一五事件裁判と社会の分極化」、第8章「国際連盟脱退と世論」、第9章「帝人事件」、第10章「天皇機関説事件」、第11章「日中戦争の開始と展開に見るポピュリズム」、第12章「第二次近衛内閣・新体制・日米戦争」、以上、全十二章である。
これを見てもわかるように、本書は、大正から昭和前期にかけての重大事件の、ほとんどすべてをフォローしている。ということは、本書は、戦前の諸事件の中に「ポピュリズム」を見出そうとした本というよりは、むしろ、「ポピュリズム」という視点から、戦前(大正から昭和前期まで)の歴史を再解釈しようとした本だと言ってよいである。そして、その大胆な試みを、見事に成功させた本なのである。
本書を読んでいて、最も印象的だったのは、第7章「五・一五事件裁判と社会の分極化」であった。五・一五事件(一九三二年)は、事件そのものの影響よりも、翌年から始まった裁判の影響、あるいはその裁判をめぐる報道の影響が大きかった、という指摘に説得力があった。
五・一五事件では、主謀者である海軍軍人の最高刑が懲役一五年であった。現役の軍人が、一国の首相を謀殺しておいて、懲役一五年というのは、いかにも「軽い」が、これは、国民各層からのも減刑運動が奏功したことを意味する。
本書の章立ては、次の通り。第1章「日比谷焼き打ち事件」、第2章「大正期の大衆運動」、第3章「朴烈怪写真事件」、第4章「天皇シンボルとマスメディア」、第5章「統帥権干犯問題と浜口雄幸内閣」、第6章「満洲事変とマスメディアの変貌」、第7章「五・一五事件裁判と社会の分極化」、第8章「国際連盟脱退と世論」、第9章「帝人事件」、第10章「天皇機関説事件」、第11章「日中戦争の開始と展開に見るポピュリズム」、第12章「第二次近衛内閣・新体制・日米戦争」、以上、全十二章である。
これを見てもわかるように、本書は、大正から昭和前期にかけての重大事件の、ほとんどすべてをフォローしている。ということは、本書は、戦前の諸事件の中に「ポピュリズム」を見出そうとした本というよりは、むしろ、「ポピュリズム」という視点から、戦前(大正から昭和前期まで)の歴史を再解釈しようとした本だと言ってよいである。そして、その大胆な試みを、見事に成功させた本なのである。
本書を読んでいて、最も印象的だったのは、第7章「五・一五事件裁判と社会の分極化」であった。五・一五事件(一九三二年)は、事件そのものの影響よりも、翌年から始まった裁判の影響、あるいはその裁判をめぐる報道の影響が大きかった、という指摘に説得力があった。
五・一五事件では、主謀者である海軍軍人の最高刑が懲役一五年であった。現役の軍人が、一国の首相を謀殺しておいて、懲役一五年というのは、いかにも「軽い」が、これは、国民各層からのも減刑運動が奏功したことを意味する。
本書を読むと、ポピュリズム的な煽り方にも二種類があり、ひとつは、天皇や
憲法などの不可侵とされる原則を盾に政敵を攻撃するもので、美濃部達吉の
天皇機関説への攻撃も、初めは貴族院議員だった美濃部の正論にやり込められた
政治家が意趣返しとして機関説を攻撃し始めたのが、首尾よく大運動に発展し、
まっとうな政治家にも抗しきれないほどまでに拡大したようで、もうひとつの
大問題であった「統帥権干犯」にしても、最初にこの論法を使ったのは野党時代の
憲政党だと聞きますが、選挙で敗れた政友会の犬養や鳩山などの若い議員が、
国際協調と海軍にとっても利益になるはずのロンドン軍縮の調印に対して、
統帥権を盾に攻撃するという挙に出たもので、その背景には、当時の政党政治を
支える層の体質も関係していたと思われます。
もう一つのポピュリズムの流れは、メディアによる徹底的で煽情的な報道の
姿勢で、これは方向性には定式がないところも不気味なところで、国民が
政党政治に飽きると、こうした報道にいいように煽られるようになり、殊に、
ポピュリズムの輿に乗った近衛文麿は、日中戦争では世論の圧力実はメディア
の圧力に唯々諾々と屈して、不拡大の方針を貫徹できず、現場で模索された
和平工作も頓挫させるというお粗末ぶりで、満州事変の頃には軍をこき下ろし
ていたメディアも、日中戦争以降、殊にヒトラーの快進撃が伝えられるように
なると、朝日新聞が初出とされる「バスに乗り遅れるな」という言葉で、
国民と軍とを積極的に煽るようになります。
戦後を顧みると、大手新聞がGHQの検閲を受けたことや、社会党に政権を担う
意志がなかったことが幸いして、メディアによる煽りが永い間深刻な影響を
もたらさずに済みましたが、93年と09年にはメディアによる煽りが政権
交代につながり、殊に近衛の孫でもある細川護熙の日本新党への「日本晴れ」
的な期待は異常なもので、反対にメディアがポピュリズムと看做した小泉内閣は、
永く主張してきた構造改革の政策案が地方の自民党員に受け入れられたことが
誕生のきっかけで、そこは取り違えてはいけないところです。
著者は冒頭にポピュリズムの定義として「大衆の人気に基づく政治」とし、日本では戦前からそれが蔓延り、現在と比較しても
あまり変わらないという。いや、もっと言うと日本を日米戦争に追い込んだのはそのポピュリズムであり、そのことを誰も書かない
ことを不思議に思いながらこの本を著したと言っている。日露戦争の後の講和条件への不満から起きた日比谷焼打ち事件を
そのポピュリズムの第一号とし、その後のいろいろな事件で政治家に圧力をかけて来たのがポピュリズムと、マスメディアであると言い切って
いる。外交評論家清沢冽の言葉を引用して「衆論に抗して毅然として立つ少数有力者がいなくなってきた」ことがその理由の一つだ
とも言う。大正時代から戦前にかけての史実を説き起こしながら、丁寧にポピュリズムの勃興とそれを煽るマスメディアの無責任さを
指摘する。この書物を読みながら一部の固有名詞を変えることで、今現在の政治状況と極めて酷似していると感じる人は
多くいるであろう。いかに大衆というのは移ろいやすく、かつ徹底的に愚かになりうる存在であり、それを煽るマスメディアは
いつの時代でも「健在」であることをこの書物は再認識させてくれる。
関連記事
-

-
『国債の歴史』(富田俊基著2006年東洋経済新報社)を読んで
標記図書を読み、あとがきが要領よくまとめられていた。財政に素人の私には、非常に参考になる。 要約す
-
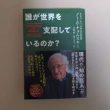
-
ノーム・チョムスキー著『誰が世界を支配しているのか』
アマゾンの書評で「太平洋戦争前に米国は自らの勝利を確信すると共に、欧州ではドイツが勝利すると予測
-

-
『源平合戦の虚像を剥ぐ』川合康著 歴史は後から作られる
源平の合戦は全国で、観光資源として活用されている。「平家物語」の影響するところが大きい。また、文
-

-
『休校は感染を抑えたか』朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/ASP6J51TNP6CULEI0
-

-
『起業の天才 江副浩正 8兆円企業を作った男』大西康之
父親の縁で小運送協会が運営していた学生寮に大学1,2年と在籍していた。その時の一年先輩に理科二類
-

-
天児慧著『中国政治の社会態制』岩波書店2018を読んで
中国民族は概念としては梁啓超以来使われていたが実体のないものであった。 それを一挙に内実化し実体を
-

-
伝統は古くない 『大清帝国への道』石橋嵩雄著を読んで
北京語 旗人官僚が用いていた言語 山東方言に基づく独自の旗人漢語を北京官話に発展させた チャイナド
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進
-
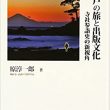
-
『江戸の旅と出版文化』原淳一郎
中世宗教史と異なり近世宗教史の大きな特徴に寺社参詣の大衆化がある。新城常三の「社寺参詣の社会経済史
-
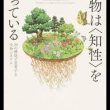
-
保護中: 『植物は知性を持っている』ステファノ・マンクーゾ 動物と植物は5億年前に進化の枝を分かち、動物は他の動植物を探して食べることで栄養を摂取する「移動」、植物は与えられた環境から栄養を引き出す「定住」、を選択した。このことが体構造の違いまでもたらしたらしい。「目で見る能力」ではなく、「光を知覚する能力」と考えれば、植物は視覚を持つ
植物は「動く」 著者は、イタリア人の植物生理学者ステファノ・マンクーゾである。フィレンツェ大学国際

