辛坊正記氏の日本の中小企業政策へのコメント
公開日:
:
最終更新日:2023/05/09
観光学評論等
下請け泣かせにメス、政府が価格交渉消極企業を指導-150社採点 Bloomberg 2023/02/07へのnewspicsコメント
「発注側企業の約150社について価格交渉や転嫁の状況の取り組みについて採点」、「価格転嫁の取り組みを支援することで中小企業が賃上げを行えるよう後押し」、「大企業では賃上げに向けて前向きな取り組みが広がりつつあるが、雇用の約7割を占める中小企業が鍵」 (@@。
大企業が本当に必要とし、そこしか生めないモノやサービスを提供する中小企業なら、自ずと価格転嫁が進むはず。購買力が弱く価格転嫁も出来ない企業は合従連衡やM&Aを通じて競争力を高め大型化するのが筋なのに、雇用規制と雇用調整助成金、さらに様々な補助金に恵まれて我が国では中小企業の新陳代謝が進みません。そして後継者も無いまま消えてゆく。事業変革と新陳代謝が進まないという点では大企業もまた然り。
こうした状況下で非効率な中小企業の価格転嫁を政府が強制的に進めたら、大企業の側が国際競争力と賃上げ余力を失って、日本に根を張る企業群が中長期的に弱くなってて行くだけじゃないのかな・・・
強い大企業を虐めて弱い中小企業を守る施策は国民の正義感をくすぐって歓心を買いますが、日本を中長期的に豊かにすることにはなりません。我が国は恒常的な人手不足状態にあるのです。中小企業庁が目指すべきは公正な市場で企業が切磋琢磨して効率性を上げる仕組みを整え、他省庁と連携して非効率な企業を離れた従業員が賃金の高い企業に安心して移れる体制を整えることにあるように感じます。
こうした介入は刹那的に中小企業を守る役には立ちますが、国内に根を張る大小企業群の国際競争力を全体的に低下させ、我が国を結局は貧しくしてしまうんじゃないのかな (・・? 社会主義国じゃあるまいし、政府がこうした形で民間企業の経営に踏み込むのは如何なものかと思います。 ( 一一)
関連記事
-

-
『ダークツーリズム拡張』井出明著 備忘録
p.52 70年前の戦争を日本側に立って解釈してくれる存在は国際社会では驚くほど少ない・・・日本に
-

-
自動運転車とドローン
渋谷のスクランブル交差点を見ていると、信号が青の間の短い時間に、大勢の人が四方八方から道路を横断して
-

-
千相哲氏の「聞蔵Ⅱ」を活用した論文
「「観光」概念の変容と現代的解釈」という論文を偶然発見した。 http://repository.
-

-
人流抑制に関する経済学者と感染症学者の意見の一致「新型コロナ対策への経済学の貢献」大竹文雄 公研2021年8月号No.696を読んで
公研2021年8月号No.696にコロナ関連の有識者委員等である、行動経済学者大竹文雄氏の「新型コ
-

-
若者の課外旅行離れは本当か?観光学術学会論文の評価に疑問を呈す
「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍が
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら
-
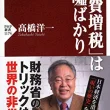
-
『戦後経済史は嘘ばかり』高橋洋一
城山三郎の著作「官僚たちの夏」に代表される高度経済成長期の通産省に代表される霞が関の役割の神
-
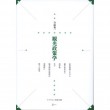
-
羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作家の旅行記に見られる旅の主体の変遷」を読んで
一昨日の4月9日に立教観光学研究紀要が送られてきた。羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-

-
Nikita Stepanov からの質問
Nikita Stepanov (Saint-Petersburg State Polytechn

