「DMO」「着地型観光」という虚構
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
観光学評論等
DMOという新種の言葉が使われるようになってきていますが、字句着地型観光の発生と時期を同じくします。
物流では運賃をだれが払うかの発荷主、着荷主概念があります。Amazonのように無料で注文者にお届けするか、国鉄時代の一部の貨物のように買主が駅頭倉庫まで取りに行くかです。観光・人流でいえば、観光資源のあるところまで自分で来てもらうか、自宅までお迎えに行くかです。
自分の費用で来てもらう以上は、消費者は自宅で目的地(デスティネーション)を選択するのですから、着地型ではなく、発地型でしょう。従来から存在するパターンです。これに対して、カジノは上得意客に対して、ファーストクラスの航空券をお渡ししてお迎えに行きます。現地でもスウィートルームを無償で提供します。ですから、着地型観光といえるのでしょう。わが国でも、関東の温泉地が新宿まで無料のバスを出して顧客をお迎えに行く形態が発生していますが、これは着地型といえるでしょう。
しかしながら、従来と同じく、顧客は自宅にいて自分の費用で自分の判断で観光地を選択するようでは、何も変わりません。旅行業者を通じてセールスをするか、ネット等でセールスをするかの違いは本質的とは言えません。それなのに、デスティネーション(目的地)を着地型といい、DMO等の字句をもって何か新しい動きであるが如く記述するのは、科学的とは言えないでしょう。観光地の事業者が連携して宣伝すること自体は、戦前の風致地区協会以来、戦後の各地観光協会、観光推進機構等が地道に行ってきていることです。
なお、政策用語の観光とは1930年に外客誘致からスタートしていますが、各自治体は、本音の部分で日本人観光客誘致に力を入れていました。このことを「内主外従」といいます。戦前でもそれだけ日本人が豊かになり、ホテルに泊まり、洋食を食べたのです。政策として日本人の観光を推進することは行われていませんでしたから、戦後も、ソーシャルツーリズムの名前のもと、厚生省が、国民宿舎等の整備を行ったのです。
なお、原忠之氏のfacebookFでのやり取りも一部メモ代わりに残しておきます。
はい、日本ではDMOとDMCを混同している議論を複数見かけました。おっしゃる通りです。 「着地型」という限りはそれはDMC (a professional services company possessing extensive local knowledge, expertise and resources, specializing in the design and implementation of events, activities, tours, transportation and program logistics)という民間営利企業の話であり、公的資金を受けるような組織の話ではなくなります。 DMO (an organization that promotes a town, city, region, or country in order to increase the number of visitors. It promotes the development and marketing of a destination, focusing on convention sales, tourism marketing, and services. Its mission is to promote economic development of a destination by increasing visits from tourists and business travelers, which generates overnight lodging for a destination, visits to restaurants, and shopping revenues and are typically funded by taxes.) とDMCの話がどうも日本で混乱しているので、また別途FBに書こうかと思っておりました。 「日本版」という形容詞がついたDMOは、当地で既に数十年成功裏に機能しているDMOと比較してファンデイング側の議論が抜けているのか「日本版」なのかと思います。 補助金目当てで自主的なFundingのビジネスモデルが描けない非営利団体は持続性が無い訳です。 今まで観光協会等、地元政府の一般財源でファンデイングしていた組織が意識改革なしに看板付け替えても持続性は欠如しています。 また本来の大きな目的は各地方での輸出産業としての観光奨励による地方創生ですので、日本人団体観光客を都会から連れてきますという20世紀の旅行代理店モデルの延長では趣旨に合致していないわけです。 米国のDMOは季節性の高いレジャー客以外のセグメントを開発するために設立された経緯があるので、MICEセグメントを追いかけるために設立された経緯がありますが、わたくしの記憶では日本版DMOの8割以上の応募者はMICEの言及一切なしでしたし、外貨獲得(=インバウンド層)にきっちりターゲットを絞っていた所も2割もなかった気がします。Yes, Japanese government earmarked significant amount of funding to support establishment of DMOs (destination marketing organizations) all across Japan, but the reality is that people do not understand clear difference between DMOs and existing Tourism Promotion Office of the municipal governments. At least in the USA, DMOs are often funded by special purpose local taxes at county-city levels, thus it would not encroach into general budget of the resident taxpayers. I will talk more about this later, while those who are interested in working in tourism and hospitality fields in Japan, please stay tuned.
これに対して私は「ただ、行政機関からの補助金は、お金による権力行使です。受け取る義務はありませんから、双務契約です。政策とは、劣位にあるものを平均水準に引き上げるため権力を使うことが基本ですから、観光とは本質的に不協和なものだと思っており、私は日本でDMOといっているものも、補助金受け皿の農協と変わらないという印象です」と返信しておきました。
観光庁のHP
日本版DMOは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。
このため、日本版DMOが必ず実施する基礎的な役割・機能(観光地域マーケティング・マネジメント)としては、
(1) 日本版DMOを中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成
(2) 各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく明確なコンセプトに基づいた戦略(ブランディング)の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立
(3) 関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組み作り、プロモーション
が挙げられます。 また、地域の官民の関係者との効果的な役割分担をした上で、例えば、着地型旅行商品の造成・販売やランドオペレーター業務の実施など地域の実情に応じて、日本版DMOが観光地域づくりの一主体として個別事業を実施することも考えられます。
関連記事
-

-
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月 を読んで
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月の存在をうかつにも最近まで知
-

-
Deep learning とサバン(思い付き)
「 スタンフォード大学の研究チームが、深層学習を用いて衛星画像からソーラーパネルを探し出すディープ
-

-
学士会報第20回関西茶話会「新興感染症の脅威と現代世界」光山正雄
感染症は今も世界の人々の死因第一位 歴史上の重大感染症 ①ペスト 14世紀 欧州で大流行 当時の
-

-
「植民地朝鮮における朝鮮総督府の観光政策」李良姫(メモ)
植民地朝鮮における朝鮮総督府の観光政策 李 良 姫 『北東アジア研究』第13号(2007年3月
-
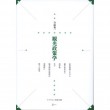
-
羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作家の旅行記に見られる旅の主体の変遷」を読んで
一昨日の4月9日に立教観光学研究紀要が送られてきた。羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
-

-
『地方創生のための構造改革』第3章観光政策 論点2「日本における民泊規制緩和に向けた議論」(富川久美子)の記述の抱える問題点
博士論文審査でお世話になった溝尾立教大学観光学部名誉教授から標記の著作物を送付いただいた。NIRAか
-

-
日本の観光ビジネスが二流どまりである理由
日本の観光ビジネスが二流どまりになるのは、人流に関する国際的システムを創造する姿勢がないからです。
-

-
国立国会図書館国土交通課福山潤三著「観光立国実現への取り組み ―観光基本法の改正と政策動向を中心に―」調査と情報554号 2006.11.30.
加太氏の著作を読むついでに、観光立国基本法の制定経緯についての国会の資料を久しぶりに読んだ。 そこ
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら

