マルティニーク生まれのクレオール。 ついでに字句「伝統」が使われる始めたのは昭和初期からということ
北澤憲昭の『<列島>の絵画』を読み、日本画がクレオールのようだというたとえ話は、私の意見に近く、理解できた。ついでいえば、世界中がクレオール化している。
このクレオールが、マルティニークから発生したことは、うかつにもこの本で知った。今年の2月にマルティニークで、飛行機の時間を見損なったから、よく覚えているが、クレオールの発祥の地であれば、もっとしっかり観察してくるべきであった。その時はカリブ海クルーズ客の動向にばかり目が行っていた。
北澤論は・・・「絵」の不在というのは、絵画のクレオール化の根底にオリジナルのものを想定できないということを意味する。言い換えれば底止することなきクレオール化の連鎖ということだが、こうした認識においてこそ、最もラディカルな「日本画」の在り方が可能となる・・・
p.28 伝統という言葉 これが何か誇りのようなものを含意する熟語として 旧日本陸軍の『歩兵操典(1909年(明治42年)11月8日軍令陸第7号)』に見える「赫々タル伝統ヲ有スル国軍」という文言に示されるように 使われるようになるのは明治以降のことであり、この語が、そのような意味で一般的に流布するようになるのは昭和初期以降のことなのである。
https://blogs.yahoo.co.jp/skylinegtrr33jp/36518918.html
このような意味あいで「伝統」の概念が重視されるようになったのは、一つには、。自民族中心主義に由来するところが大きいのだが、それとともに、近代国家としての体裁を整えるという要請にもかかわっていた。
絵においても、「廃藩置県」と同様の動きが起こった。京都/江戸という双分組織的な文化構造や身分制に基づいて江戸時代までに形成された様々な画派が「日本画」の名のもとに統合されてゆくのである
p.39 かつての日本画は、西洋画とあい携えて、植民地の美術界に宗主国の絵画として君臨していた。和製西洋画は被害アジアにおける先駆的近代化の証として、日本画は日本文化の代表として、それぞれ政治的意義を担っていた。その玉座として設けられたのが朝鮮美術展覧会と台湾美術展覧会である。
富士山は、 その末広がり形状が図像的コンベンションとして長い間流通してきたために、個性化が求められる平時の近代的心情に対して、どれほど魅力を持つか疑わしい。
<海山十題>的自然はすでに魅力を失っている。
実は自然は魅力を失っている。 保護されるべき対象と化している。介護老人保健施設で、静かに余生を送っている。
東北大地震は「非自然災害」
以上が本書のメモ
ついでに、
「初詣」の誕生は明治中期である。1872年、東海道線が開通し、川崎大師へのアクセスが容易になる。川崎大師は江戸から見て恵方にあたり、行楽も兼ねて参詣に行く人が急増し、特に1月21日の縁日(初大師)は大盛況となった。とはいえ、恵方は5年に1回しか来ない。当たり前だが鉄道会社としては毎年来てくれたほうが儲かる。そこで、大晦日から寺社に籠って元日を迎える「年籠り」、年明けはじめての縁日に参詣する「初縁日」、居住地から見て恵方にある寺社を参詣する「恵方詣り」といった古来からの行事を組み合わせ、縁日も恵方も関係ない「初詣」をつくりあげ宣伝文句とした。「重箱のおせち」もかなり新しい伝統だ。おせちは「お節」と書き、祝いの席の料理として奈良時代から存在したが、正月のおせちを重箱に詰めるようになったのは幕末から明治にかけてで、戦後、デパートの販売戦略によって定着した。
「讃岐うどん」という言葉自体は60年代の誕生で、「越前竹人形」は水上勉が1963年に発表した小説『越前竹人形』が初出
関連記事
-

-
蓮池透・太田昌国『拉致対論』めも
p.53 太田 拉致被害者家族会 まれにみる国民的基盤を持った圧力団体 政府、自民党、官僚、メディ
-

-
『源平合戦の虚像を剥ぐ』川合康著 歴史は後から作られる
源平の合戦は全国で、観光資源として活用されている。「平家物語」の影響するところが大きい。また、文
-

-
『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』川添愛著
ディプラーニングを理解しようと読んでみた。 イタチとロボットの会話は全部飛ばして、解説部分だけ読め
-
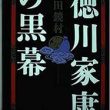
-
『徳川家康の黒幕』武田鏡村著を読んで
私が知らなかったことなのかもしれないが、豊臣家が消滅させられたのは、徳川内の派閥攻勢の結果であったと
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
-

-
観光資源としての明治維新
NHKの大河ドラマは、源平合戦、関ケ原の戦い、明治維新が三大テーマのように思うが、観光資源としての価
-

-
岩波新書『日本問答』
本書では、大島英明著『「鎖国」という言説 ケンペル著・志筑忠雄訳『鎖国論』の受容史 人と文化の探究』
-

-
字句「美術」「芸術」「日本画」の誕生 観光資源の同じく新しい概念である。
日本語の「美術」は「芸術即ち、『後漢書』5巻孝安帝紀の永初4年(110年)2月の五経博士の劉珍及によ
-

-
ヒトラー肝いりで建造の世界最大のホテル・プローラ
観光政策というより、福祉政策なのかもしれませんが、現代なら民業圧迫という声が出るでしょう。
-

-
自動運転車とドローン
渋谷のスクランブル交差点を見ていると、信号が青の間の短い時間に、大勢の人が四方八方から道路を横断して
