試験問題1(歴史や伝統は後から作られるということを何度か述べました。その実例を自分で考えて3編以上紹介し、観光資源としての歴史、伝統の活用について、400字以内で論述せよ。)
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
伝統・伝承(嘘も含めて)
この設問は、事前に講義中に出題しておいた。実例を自分で探してもらうためだ。出席していない学生は教科書やHPから引用するだろうが、それはそれで評価するが、観光は個性の発揮でもある。しかし、恵方巻、赤レンガ等の似たような例の回答が多く、少し当てが外れた。例示とともに、観光資源としての活用についての記述は極めて少なかった。
私としては、古くから信じられてきたことが意外に新しく、意表を突くものであり、そのことが面白くもあって観光資源としてますます価値を高めるといった例が欲しかったのである。
よく勉強してきた学生は、歴史認識に触れている。歴史解釈が後で作られているという自覚をしっかりしておけば、観光資源として余裕をもって接触できることができるということを理解している。教えがいがあるというものである。
お国自慢の観光資源は学生もふるさと自慢を兼ねて答案に書き込んでいた。女装した男性が行う戸塚区のお札まきは江戸時代から継続しているようだが、ヘミングウェがパップローナの牛追い祭りを小説に使用したようなことでもないと、世界的な資源にはならないだろう。私が知らなかったのは、相撲が国技になったのは「明治期に」国技館が建設されてからだという解答、戊辰戦争時多くの農民は戦争に巻き込まれた側であり、藩に思い入れもなく、むしろ重税に苦しんで恨んでいたという説を紹介し、会津の悲劇も嘘ではないが、それに対する認識が立場により少し違うということの解答、鳥取砂丘は植林により農地として利用され、戦時中は軍事教練の場としても利用されていたが、そのうちに農地化案への反発などから砂丘の保存への声が高まり観光地化していったという解答は、私にとっても大きな収穫であった。勿論この解答をした学生は、この部分では最高点を獲得している。
関連記事
-

-
伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-

-
『おクジラさま』佐々木芽生著 備忘録 伝統は古くはない
https://spice.eplus.jp/articles/137344 https:
-

-
2019年1月28日横浜私立大学期末試験 伝統、歴史は後からつくられている例を挙げさせた。その回答例の紹介
2019年1月28日横浜市立大学の観光振興論の期末テストを行った。問題は2問。下記のとおりである。
-
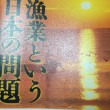
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は
-

-
混浴は伝統ではない 『温泉の日本史』『温泉の平和と戦争』を読んで メモ
書評に「論文等を査読・掲載する学会誌を年2回刊行、全国の温泉地で年2回開催している研究発表大会が基本
-

-
『銀座と資生堂』戸矢理衣奈
戸谷という珍しい苗字にひかれて本書を港図書館で借りた。現役時代、役所の先輩の息子さんが亡くなら
-

-
Quoraに見る観光資源 ジョージ・フロイドさんが実際に死亡する経緯が録画
地面に押し付けられる前から呼吸が苦しいと訴えているので実際に呼吸あるいは心臓停止が首部圧迫で起こっ
-

-
伝統は後から作られる例 関西は阪神フアンという伝統
これも学士會会報の記事、何時も面白い話をしてくれる井上章一氏の「ゆがめられた関西像」 戦後しば


