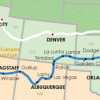2019年1月28日横浜私立大学期末試験 伝統、歴史は後からつくられている例を挙げさせた。その回答例の紹介
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
伝統・伝承(嘘も含めて)
2019年1月28日横浜市立大学の観光振興論の期末テストを行った。問題は2問。下記のとおりである。
問題2「観光資源として活用される伝統や歴史認識といわれるものの中には、予想よりも新しく、又は後でフィクションであったことが証明されたりするものがあります。その例を最低5個取り上げて論じてください。字数に制限はありませんが、配られた答案用紙(別紙)の範囲内とします。ネット等でよく知られているものの評価は低くします。」
◎ 宗教行事に関する回答が多かった。
① 神社の作法が意外と新しいという回答例が多かった。昭和23年の神社祭式行事作法改正が契機という回答。② 各地の古墳は天皇制との関連で明治期に定められたが、科学的根拠が不明確なものが多いという回答も、学生には新鮮だったのかもしれない。日本各地の名所になっているから。 ③ 出雲の縁結びの神さま そのような神様は祭られていない 江戸中期 御師の事業戦略であるという回答も改めて認識した。 ④盆踊りは、死者の供養のため空也上人が始めたものととされている。江戸時代に風紀が乱れることから一時衰退したが、大正末期から復活。⑤お遍路の大衆化はモータリゼーション後のことである
初詣は 電鉄会社の営業戦略により普及したもの、 除夜の鐘は昭和以降ラジオで取り上げられたから普及したので、お寺の経営する幼稚園と同じく、皆が真似をした。 先祖代々の墓も普及するまでは個人、夫婦の墓が普通であった。庶民も建墓が自由になったからである。
◎ 食生活に関するものの回答 伝統料理といわれているものの大半が歴史が新しい。その集大成が「和食」であるから、和食は現代のものである。
①お寿司は関東大震災後に全国に普及したもので、それまでは江戸地域限定の屋台でしか食べられなかった。(このことはよく知られているが学生には新鮮だったのかもしれない)②お茶の飲料は大正末期から始まったもの。重要な輸出品であり、庶民の生活に根付いたものではなかった。(私も考えたこともなかった。確かに輸出品であった。)③大阪のお好み焼きは1937年ころで、1931年ころに始まった東京のどんど焼きを工夫したもの④朝鮮半島の焼肉文化、プルコギも、朝鮮戦争時に始まったものである。(これも知らなかったが、ネットには出ている) ⑤おせち料理を一般的に食べるようになったのは戦後のこと 青森を含む東北や北海道ではでは大晦日におせちを食べるようである。⑥流しそうめんは昭和30年に高千穂峡にある千穂の店元
初詣は 電鉄会社の営業戦略により普及したもの、 除夜の鐘は昭和以降ラジオで取り上げられたから普及したので、お寺の経営する幼稚園と同じく、皆が真似をした。 先祖代々の墓も普及するまでは個人、夫婦の墓が普通であった。庶民も建墓が自由になったからである。 祖流しそうめんが始めたもの、⑦海鮮丼は函館で30年前に作られたものが普及した。⑧金沢おでんはつい最近できたという回答があったが、私にしてみるとそんなものがあるとはしらず、とても伝統料理とは思えないのであるが。
ちゃぶ台 作法では元来食事中の会話は禁止されていた。明治期に欧米化を家庭科(家事科)で教えるようになってからのことである。「いただきます」も明治期にはない習慣である。一日三食も明治からである。
そのほか、商業者の販売戦略により生まれたものが良く回答に挙がっていた。重箱によるおせち料理(デパート)、クリス
初詣は 電鉄会社の営業戦略により普及したもの、 除夜の鐘は昭和以降ラジオで取り上げられたから普及したので、お寺の経営する幼稚園と同じく、皆が真似をした。 先祖代々の墓も普及するまでは個人、夫婦の墓が普通であった。庶民も建墓が自由になったからである。 マスのチキン(ケンタッキーフライドチキンがNHKの取材に欧米ではクリスマスにチキンを食べると回答
◎イベント
チャグチャグ馬子は戦時中に拡大団体行進行事。 北海道のマリモ祭りアイヌには関係がない、むしろ漁の邪魔であった 。甲子園での校歌斉唱はもともとなかった。第8回の春の大会からはじまった。選手宣誓も簡単なものが1984年から変質した。野球がクーパーズタウンで発祥したという話も南北戦争の英雄が考案したという神話に基づくもの、英国のラウンダーズから始まっている。彦根城は文化庁の指示でオリジナルなものに平成8年改修した。しかし修繕前のほうが古色蒼然としていて市民にはなじんでいたのではないか。
川越は小江戸といわれるが、明治26年大火以前には、蔵作りの家並み風景はないという回答。川越市には不都合な真実であろう。琉球ガラスは米軍の駐留軍の需要に対応したもの
◎生活習慣等
正座は神聖な儀式のときだけだった。将軍神格化のため、殿中での大名にも正座を強要した 1941年道徳の中で教えられる 立派な日本人であるという証が必要であった。たたみは座布団、ベットの代用であった。庶民が利用できたのは明治期からである 。あや取りは日本固有のものではない
浴衣は文字通り下着。子供の頃は浴衣は着物とは思わなかった。キャミソールがファッションなのだからおかしくはない。
チマチョゴリ もともと一色。多色化したのは日韓併合後日本のセーラー服、袴の影響
小説等によるフィクション 巌流島
問題1 空白部分に字句を記入しなさい
日本の字句観光の語源が記述されているとされている中国の古典の名称を「1 」という。 「易経」 正答率が低かった。占いは知っていても易自体を知らない時代の学生である
人口減少は、田舎から大都会に直接移動するのではなく、田舎町から県庁所在地へ、ブロック都市から東京へと玉突き状態で移動する。この現象を「2 」の法則という。ラベンシュタイン 意外と正答率が高かった。授業に出てきている学生は、何度も説明したからで、知っていたのであろう
江戸時代は、江戸の衛生状態が悪く、多くの若者が死亡したから人口は100万人で頭打ちであった。この現象を「3 」という。江戸蟻地獄説 正答率が低い。教科書を持ってきていた学生は正解しやすかったであろう
戦前の観光政策は艦船建造等のための「4 」が目的であった。外貨獲得 正答率が高い
戦後、国内観光は勤労者の福利厚生を目的としたものとして考えられ、国民宿舎、国民休暇村等の整備を中心に厚生労働行政として行われた。この現象を「5 」という。ソーシャルツーリズム
1970年の大阪万博後の旅客需要の減少を心配して国鉄は大型キャンペーンを行った。このキャンペーンを「6 」と呼ぶ。ディスカバージャパン
1971年日本人海外旅行者数が訪日外国人客数を上回り、旅行あつ旋業法は旅行業法に全面改正された。現在旅行業法は旅行者の保護を目的として企画旅行につき、標準約款で旅行中に起きた事故についての規定を設けている。この制度のことを「7 」と呼ぶ。 特別補償制度
1986年外貨減らしを目的として、日本人の海外旅行を増加させる政策がとられた。この運動を推進する計画のことを「8 」と呼ぶ。テンミリオン計画
2007年観光基本法が全面改正され「9」となった。両者の最大の違いは「10 」の廃止である。観光立国推進基本法
文化財保護法により輸出が禁止されている文化財を「11 」という。重要文化財 国宝と書いた答えがあったが間違いにした
関連記事
-

-
QUORAに見る観光資源の嘘 「ラーメン王」「ミスターヌードル」として後世にも語り継がれる伝説の人となっていますが、驚くべきことに、実は発明なんてしていなかったということが明らかになっています。
今では社会的に高く評価されている人物の中で、とてつもなく社会的に評価が低かった黒歴史がある方はい
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-

-
混浴は伝統ではない 『温泉の日本史』『温泉の平和と戦争』を読んで メモ
書評に「論文等を査読・掲載する学会誌を年2回刊行、全国の温泉地で年2回開催している研究発表大会が基本
-

-
伝統論議 蓮池薫『私が見た「韓国歴史ドラマ」の舞台と今』
〇 蓮池氏の著作 「現代にも、脈打つ檀君の思想、古朝鮮の魂』などをよむと、南北共通の教育があること
-

-
Quoraに見る観光資源 タモリさんは何がすごくて芸能界で大御所扱いされているのですか?
回答 · 日本 · 関心がある可能性があるトピックタモ
-

-
試験問題1(歴史や伝統は後から作られるということを何度か述べました。その実例を自分で考えて3編以上紹介し、観光資源としての歴史、伝統の活用について、400字以内で論述せよ。)
この設問は、事前に講義中に出題しておいた。実例を自分で探してもらうためだ。出席していない学生は教科書
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-

-
Quoraに見る観光資源 漢字が日本に来た頃、日本に中国語を話す人はいたのでしょうか?漢字は書き言葉ですが、漢字すなわち古代中国語を話す必要性は日本にあったのでしょうか?蔡 鸟 (Cai Niao),
漢字が日本に来た頃、日本に中国語を話す人はいたのでしょうか?漢字は書き言葉ですが、漢字すなわち古代
-
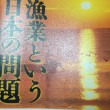
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は