満州事変(1931年)前の訪日中国人の割合は現在のインバウンド政策時代の割合と変わらない
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
人口、地域、
戦前鉄道省に国際観光局ができる前年の1929年の外客数は34755人であり、うち中華人16300人、米国人8527人、英国人4363人、露西亜人1587人であった。中華人の割合が47%にも上っている。当時は朝鮮、台湾居住者は国内扱いである。
2017年の訪日外客数は2869万人であるが、韓国714万人、台湾456万人以外の者は1699万人である。このうち中国本土が637万人、香港が184人で合計821万人と1699万人に対する割合は48%と1929年の割合と一致する。
国際観光局設立後、1932年の訪日外客数は20960人と大正5年以来最低の数字となってしまい、インバウンド観光政策の成果が疑われる結果となった。観光収支は1933年は130万ドルの赤字であったが、その後1934年270万ドル黒字、1935年380万ドル黒字、1936年510万ドル黒字となり外貨獲得政策の成果が発揮されるようになった。1936年の外客数は約4万2千人で、その消費額は1億7百万円と、当時の海運收入が約2億円であったから、観光収入は貿易外收入の重要な一項目であった。
関連記事
-

-
矢部 宏治氏の「なぜ日本はアメリカの「いいなり」なのか?知ってはいけないウラの掟」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52466 外務省がつ
-
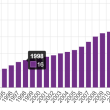
-
Is it true only 10% of Americans have passports?
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42586638
-
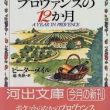
-
『プロヴァンスの村の終焉』上・下 ジャン=ピエール・ルゴフ著 2017年10月15日
市長時代にピーターメイルの「プロヴァンスの12か月」読み、観光地づくりの参考にしたいと孫を連れて南仏
-

-
Quora Covid-19の死亡者はアメリカが27.9万人、日本が2210人 (12/06現在) です。日本では医療崩壊の危険が差し迫っているとの報道がありますが、アメリカに比べて医療体制が貧弱なのでしょうか?
12月16日現在、アメリカでの死亡者数は約30万4千人、そして日本での死亡者数は2600名足らずで
-

-
『外国人労働者をどう受け入れるか』NHK取材班を読んで
日本とアジアの賃金格差は年々縮まり上海などの大都市は日本の田舎を凌駕している。そうした時代を読み違え
-

-
『「食べること」の進化史』石川伸一著 フードツーリズム研究者には必読の耳の痛い書
食べ物はメディアである 予測は難しい 無人オフィスもサイバー観光もリアルを凌駕できていない
-

-
🌍🎒2023夏 シニアバックパッカーの旅 2023年8月26日 マシュハド 年間2千万人のムスリムが訪問
FACEBOOK 投稿文 2023.8.26マシュハド マシュハド空港からメトロに
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
日経の記事「東京郊外への移住じわり」
これに対するコメントの紹介 データを扱うのであれば正確にお願いしたい。東京一


