『江戸のパスポート』柴田純著 吉川弘文館
公開日:
:
最終更新日:2023/10/01
出版・講義資料
コロナで、宿泊業者が宿泊引き受け義務の緩和に関する政治的要望を行い、与党も法改正を行うことを検討している報道がなされている。この報道が正しいとすれば、今の政権は、徳川幕府以下の旅行政策しか念頭にないことがわかる。
江戸時代の庶民の旅は18世紀後半から急増。19世紀前半にピークを迎える。新城常三「社寺参詣の社会経済史的研究」(塙書房)環境が整い、苦行的なものから遊楽的なものに変化、旅人の下層化は乞食巡礼の横行(現代でいえばワーキングホリディー)を招いた。この指摘はハード面であり、旅人の安心を保障するシステムともいえる体制が19世紀に前半に整った。往来手形であるが、新城は往来手形には否定的に言及。ポジティヴに評価するのは内藤二郎によって。往来手形を軸にする旅行難民救済システムという展開はその後。
1814年に成立した日本初の英語辞典「暗厄利亜(あんげりあ)語林大成」はpassportを「往来文(オオライテガタ)」「又赦書(ユルシヂャウ)」と表記。往来手形はパスポートと認識されていた。
18世紀半ばまでは、乞食か旅人かに関係なく、領主の役人が検死をし、埋葬した。
偽往来手形の横行
従来のパスポート研究でも、19世紀初頭のヨーロッパでは国内用が大半(『パスポートとビザの知識』春田哲吉 有斐閣選書)
元禄令が病牛馬の遺棄と並んで、病人の半強制的な「宿送り」を禁止、遺棄が禁止。意識を啓蒙する役割を果たした
幕府の明和令(宿継、村継規定と往来手形携帯規定)では、病人に療養を加えず、宿継、村継などで送り出したことが露呈した場合、罰則規定がもうけられた。幕令を元に、地域でのより具体的な対応策が講じられていた。
明和令は、五街道の旅籠屋だけでなく、村々で宿をとる旅人に対してでも、病人は医者に見せ、療養を加え、往来手形を携帯していれば、旅行費用のないものでも、希望すれば、村継で国元に送るように指示した
関連記事
-

-
QUORA 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック 米国は、日本の真珠湾攻撃の計画を実際には知っていて、戦争参入の口実を作るために敢えて日本の攻撃を防がなかった、というのは真実ですか?
回答 · 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック米国は、日本の
-

-
書評『人口の中国史』上田信
中国人口史通史の新書本。入門書でもある。概要〇序章 人口史に何を聴くのかマルサスの人口論著者の「合
-

-
保護中: 『中世を旅する人びと』 阿部 謹也著を読んで
西洋中世における遍歴職人の「旅」とは、糧を得るための苦行であり、親方の呪縛から解放される喜びでもあっ
-

-
Quora ヨーロッパ人による境界がなかった場合には、今日のアフリカには幾つくらいの国があったと思いますか? 欧州にはバスク語しか残らなかった
https://youtu.be/i28l-t4H1GM ヨーロッパ人による境界がなかっ
-
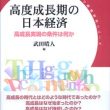
-
『高度経済成長期の日本経済』武田晴人編 有斐閣 訪日外客数の急増の分析に参考
キーワード 繰延需要の発現(家計ストック水準の回復) 家電モデル(世帯数の増加)自動車(見せびら
-

-
三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』なぜ日本に政党政治が成立したのか
1 なぜ日本に政党政治が成立したのか (これまではなぜ政党政治は短命に終わったかを論じてきた)
-
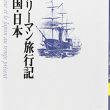
-
『シュリューマン旅行記』 清国・日本 日本人の宗教観
『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳 シュリューマンは1865年世界漫遊の旅に出か
-

-
ヒマラヤ登山とアクサイチン
〇ヒマラヤ登山 機内で読んだ中国の新聞記事。14日に、両足義足の、私と同年六十九歳の中国人登山
-

-
1932年12月16日『白木屋の大火始末記』
関東大震災の始末が終了したころ 地下三階地上七階建てデパートの4階から出火 クリスマスツリーの豆電
-

-
田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き

