歴史認識と書評『1945 予定された敗戦: ソ連進攻と冷戦の到来』小代有希子
「ユーラシア太平洋戦争」の末期、日本では敗戦を見込んで、帝国崩壊後の世界情勢をめぐる様々な分析が行われていた。ソ連の対日参戦が、中国での共産党の勝利が、朝鮮支配をめぐる米ソの対立が予測され、そしてアメリカへの降伏のタイミングが、戦後日本の生存を左右することも知られていた。アメリカ主導の「太平洋戦争史観」を超え、アジアにおける日ソ戦争の焦点化にまで取り組んだ野心作。
書評1
世間で広く信じられていることには、第二次世界大戦末期、日本の指導者達はソビエト連邦が中立条約を破って侵攻してくることを全く見抜けず、ソ連の和平仲介の望みが無様に絶たれたことで慌てて降伏したことになっている。
しかし、当時の日本の指導者たちはそれほどまでに愚かだったのだろうか?
筆者は大量の資料を活用することで、そのような説が誤りであったことを証明している。
従来から参照されていた指導者たちの会議記録や、軍や外務省の情報機関が集めていた世界各国の動向の研究、特高が調べていた朝鮮の反体制運動の調査資料、日本の市井の人々の発言記録まで、筆者があたった資料は多岐にわたる。特に陸軍が行っていた中国共産党の研究や、特高が行っていた朝鮮の反体制活動家の思想動向への言及は興味深い。そのような資料を通して浮かび上がってくる姿は、日本の指導者たちはソ連の参戦を、そしてアメリカとソ連の冷戦の萌芽を正確に見抜いてたということだ。国民も新聞や情報誌を通じてアメリカとソ連の対立を興味深く追っていた。
ところで筆者も論中で指摘していることだが、一般公開されている資料だけでも日本がソ連の参戦を予期していたことは簡単に分かることだ。
太平洋ではアメリカ軍に敗北し続け、頼りにしていた同盟国ドイツも敗戦、北方ではソ連が不穏な動向を見せている。しかし一方で、連合国内で米英とソ連の不協和音が聞こえ始めていた。日本の指導者たちは敗戦が確実の絶望的な状況の中、どのタイミングで降伏すれば、戦後日本が復活できる環境を作り出せるか冷徹に考えた。そして彼らの出した結論は…。
膨大な資料と優れた考察による、読み応えのある歴史研究である。多くの人に薦めたい。
書評2
通説が次々に覆されてゆく驚き。ある意味 快刀乱麻を断つ快感。そうだったのか、戦争。そして戦後。膨大な一次資料の渉猟と詳細な読み込みから見えてくる、異貌の戦争指導層と一般人。私が教えこまれてきた通説は何だったのか。
戦争史、戦後史に巨大な一石を投じた力作だ。波紋はどこまで広がるだろう。決して無視できない論考だ。
《 使用尽くされた感のある資料も、注意深く読み直すと見落としていた事実が見つかる。既成概念を持って 資料にあたると、探したいことしか目に入ってこず、なじみのない事項は無意識にその存在を拒絶してしまう 心理作用が原因だ。 》 16頁「序章 『ユーラシア太平洋戦争』と日本」
《 これまでの記録から見て、ソ連の対日参戦が東郷外務大臣をはじめとして最高戦争指導会議構成員にとって 「予期せぬ驚き」ということはありえない。しかし戦後に広まった神話では、ソ連の参戦は「驚愕の裏切り」 として受け止められたことになっている。 》 243頁「第6章 日本の降伏と植民地帝国の崩壊」
書評3
著者は米国の大学で教えたこともあるようで、本書はもともと英文で書かれたものを著者自身で日本語に書き直したものらしい。英語の方はそれだけ堪能なのだろうが、日本語能力はどうも疑問である。「邀撃」を「激撃」(209p)と間違えたりするなど、単純な誤植ではなく、「邀撃」という言葉自体知らないのであろう。「待つあるを恃む」の現代語訳を「『待つ』ということを頼みにして」としているところ(205p)など、噴飯ものである。
もちろん、これは『孫子』の「無恃其不来、恃吾有以待也、無恃其不攻、恃吾有所不可攻也(その来たらざるを恃(たの)むことなく、吾の以て待つあることを恃むなり。その攻めざるを恃むことなく、吾が攻むべからざる所あるを恃むなり=敵のやって来ないことを〔あてにして〕頼りとするのでなく、いつやって来てもよいような備えがこちらにあることを頼みとする。また敵の攻撃してこないことを〔あてにして〕頼りとするのでなく、攻撃できないような態勢がこちらにあることを頼みとするのである)」に由来する言葉である。
著者は漢文の素養もなしに、戦時中の軍人が書いた文書を読み解いているものと見える。
すでに公表されて誰でも読める歴史書からだらだらと引用してページを埋めているのにつき合わされるのはうんざりするが、本書で他の歴史書の「定説」をくつがえすと力こぶを入れているのはただ1点でしかない。すなわち、日本の終戦工作でソ連に調停を依頼したのは、従来日本のうかつさによるとされていたが、ソ連が参戦すれば、アメリカはソ連が極東で勢力を拡大するのを恐れて講和を急ぐことになるから、日本に有利な状況が生まれる、だから対ソ工作をするふりをしてソ連の参戦まで待ったのだというところである。これを言うだけだったら、370ページも必要はないであろう。
そんな計略を書き記した文書をアメリカの公文書館から発見したというなら、大発見と言ってもいい。だが、そんな証拠はどこにもないのである。著者は、ソ連軍が対日戦の準備をしていることがさまざまな情報機関から参謀本部に集まっていたことを書き記して、それなのに、ソ連のお情けにすがるような調停依頼を続けたのは、なぜなのか? と疑問を抱く。そして、どうしても理解できないあまり、推測に推測を重ね、憶測をたくましくしているだけでしかない。
関連記事
-

-
『サカナとヤクザ』鈴木智彦著 食と観光、フードツーリズム研究者に求められる視点
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ! アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大
-

-
【ゆっくり解説】【総集編】ガチで眠れなくなる「生物進化」の謎6選を解説/ミッシ ングリンク、収斂進化、系統樹、生命起源【作業用】【睡眠用】
https://youtu.be/ACEmkF1-g88
-

-
動画で考える人流観光学帝国ホテル等に見る「住と宿の相対化」
https://youtu.be/21llSPlP5eQ https://yo
-

-
塩野七生著『ルネサンスとは何であったのか』
後にキリスト教が一神教であることを明確にした段階で、他は邪教 犯した罪ごとに罰則を定める 一
-

-
『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.h
-

-
Quora 微分方程式とはなんですか?への回答 素人の私にもわかりやすかった
微分方程式とは、未来を予言するという人類の夢である占い術の一つであり、その中でも最も信頼のおける占
-

-
ドナルド・トランプが大統領になる5つの理由を教えよう
https://www.huffingtonpost.jp/michael-moore/5-rea
-

-
『ざっくりとわかる宇宙論』竹内薫
物理学的に宇宙を考察すればするほど、この宇宙がいかに特殊で奇妙なものかが明らかになる。マルチバー
-
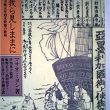
-
書評『我ら見しままに』万延元年遣米使節の旅路 マサオ・ミヨシ著
p.70 何人かの男たちは自分たちの訪れた妓楼に言及している。妓楼がどこよりも問題のおこしやすい場
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre

