『結婚のない国を歩く』モソ人の母系社会 金龍哲著
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
出版・講義資料
https://honz.jp/articles/-/4147
書によれば、「民族」という単語は1900年頃日本から中国に輸入された和製漢語らしい。清末民初の政治家の梁啓超が、亡命先の日本から送った文章にこの表現があり、ここから「中華民族」という概念に繋がった。孫文が「民族之統一」と言った当初は、漢・満・蒙・回・蔵の5族を1つにすることを意味したが、その後、全ての少数民族を含めた「中華民族論」となった。この「少数民族」の識別は、1949年から30年間をかけて行われ、現在までに55の少数民族が登録されている。
この中に雲南省の「ナシ族」があり、本書で記述される「モソ人」は、ここに含まれている。この民族識別は多くの困難を伴った。スターリンの定義である「共通言語、共通地域、共同の経済生活、共通の心理資質(民族意識)」の4要因を満たしている民族は、漢民族を含めても存在しなかったのだ。「モソ人」の人たちも、自分たちは「ナシ族」ではないと思っている。ナシ族とは異なる点の1つが、「走婚」という婚姻形態と、それをベースにした母系社会である。
「走婚」であるが、「妻問い婚」とも言われ、男性が女性の部屋を訪れる形の婚姻形式のことだ。でも、このように書いただけでは、まだ伝わらない。
男性は、夕食を済ませると、自分の家を出て彼女の部屋に向かう。夜になっても自宅にいる男性は「情けない奴」と見られる。男性がいつも住んでいる自宅には、自分のきょうだいと、母親と、そのきょうだいがいる。一家を支えるのは「ダブ」と呼ばれる女性家長で、経済を一手に引き受けている(家族は全員、収入をダブに渡す)。お付き合いしている彼女の家に着くと、あらかじめ決められた合図(犬や鶏の鳴き声など)をして、2階にある彼女の部屋(花楼)に入れてもらう。まだ家族に認められていない時は、塀を超え、壁をよじのぼり、花楼の窓から侵入する。そこまでしても、入れてもらえないことがある。他の男性が先にいるときだ。そういう時は、より「長期」のお付き合いをしている相手にその場を譲り、もう一人は静かに去るのがルールだ。男性のほうも、複数の彼女を持つことができる。朝になると、花楼を訪れた男性は、家族や村人に見られないよう、日が昇る前の6時くらいには自宅に帰らなければならない。他の村から徒歩で3時間往復して通っていた人もいる。最近はオートバイを利用するケースが増えてきて、「走婚範囲」が広まった。
このような活動を経て、お互いの家が公認すれば、走婚の関係ということで認められる。子供が産まれると、母親の家に所属することになる。きょうだいの父親が異なっているのは普通で、走婚の関係にあるのは、お互いに納得している期間だけだ。夜遅く来て朝になると帰ってしまうので、子供が父を見ることもあまりない。かわりに、母の兄弟(伯父)が威厳ある存在となる。「嫁入り」とか「婿入り」は(あまり)存在しない。つまり、基本的に、産まれた家にずっといるわけだ。人数が多くなった家は分家する。家の囲炉裏には火が絶えず点されていて、分家の際にはその火が引き継がれる。ちょっとオリンピックみたいだ。
子供が産まれた時には「満月酒」の儀式が行われる。これは父親側の家族が準備を行う。父親には養育義務がないが、このような儀式を通じ、子供が正式に認知され、母親側の家族に感謝の意が表されることになる。もう一つ、父親が登場する儀式がある。数えで13歳になるお正月に行われる「成人式」だ。家族ぐるみで長期間準備して行う一大イベントだが、この際、「無事成人しました」と、父親がいる家に挨拶に訪れる。
非常にかいつまんで書いたけれど、このような感じの文化である。今も大多数がこのような母系制度に属しているが、外の社会の影響を受けて変わってきた面もある。古くは文化大革命の頃、モソ族の名前に加えて「漢名」を使用するようになった。「工作隊」に何度も呼ばれて漢名をつけるように言われたモソ人の青年が、「どうしてもつけなければいけないというなら、“和沢東”と呼んでください」と答え、数年間の労働改造を強いられたりしたらしい。同じころに一夫一婦制を強制されたりもしたが、次の世代で母系に戻っている割合が多い。最近では、テレビ・携帯電話・インターネットの普及により、外の価値観がどんどん入ってくるようになった。ある老人の「テレビには参った!」というコメントがちょっとおかしい。若者は北京・上海などの大都市の生活に憧れている。しかし、一方で、「麗江古城」が世界遺産になり、瀘沽湖とモソ族の文化が有名になるにつれ、走婚に基づくモソ族の母系制度が、「進化すべき化石的なもの」ではなく、現代の社会問題を解決する優れたものだという自信をもった意見が出てきている。
関連記事
-

-
『金語楼の子宝騒動』(「あきれた娘たち」縮尺版)少子高齢化を想像できなかった時代の映画
1949年新東宝映画 私の生まれた年である。嫁入り道具に風呂敷で避妊薬を包むシーンがある。優生保護
-

-
『シベリア出兵』広岩近広
知られざるシベリア出兵の謎1918年、ロシア革命への干渉戦争として行われたシベリア出兵。実際に起
-

-
『財務省の近現代史』倉山満著 馬場鍈一が作成した恒久的増税案は、所得税の大衆課税化を軸とする昭和15年の税制改正で正式に恒久化されます・・・・・通行税、遊興飲食税、入場税等が制定されたのもこの時であり、戦費調達が理由となっていた 「日本人が汗水流して生み出した富は、中国大陸に消えてゆきました」と表現
p.98 「中国大陸での戦争に最も強く反対したのは、陸軍参謀本部 p.104 馬場
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
「食譜」という発想 学士會会報 2017-Ⅳ 「味を測る」 都甲潔
学士會会報はいつもながら素人の私には情報の宝庫である。観光資源の評価を感性を測定することで客観化しよ
-

-
「南洋游記」大宅壮一
都立図書館に行き、南洋遊記を検索し、[南方政策を現地に視る 南洋游記」 日本外事協会/編
-
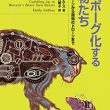
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
-

-
『金融資本市場のフロンティア 東京大学で学ぶFinTech、金融規制、資本市場』に学ぶべきMaaS
本書を読んで、アンバンドリングとリバンドリングという言葉に出会った。金融機能が、テクノロジーが導入
-

-
Quora 英語は文字通り発音しない単語が多い理由は、ペストの流行が原因?
Shiro Kawaiさんの名回答 1400年頃までの中英語(Middle English)
-

-
日本銀行「失敗の本質」原真人
黒田日銀はなぜ「誤算」の連続なのか?「異次元緩和」は真珠湾攻撃、「マイナス金利」はインパール作戦


