中国文明受入以前は、藤貞幹は日本に韓風文化があったとする。賀茂真淵は自然状態、本居宣長は日本文化があったとする。
中国文明受入以前は自然状態であったとする賀茂真淵、日本文化があったとする本居宣長に対して、藤貞幹は、韓風文化があったとする。平田篤胤は日本風が中国風に影響したとする
神武天皇の在位を600年繰り下げて神代文字の存在を否定した『衝口発』を著すが、これが国学者達の反感を買い、特に神武天皇や素戔嗚尊(その正体を新羅の国王であるとした)の問題については本居宣長が『鉗狂人』を著して貞幹の考証が杜撰であると主張し、逆に上田秋成が貞幹を擁護して宣長の姿勢を非難するなど激しい「日の神論争」等の論争を招いた。
国学は『古事記』や『日本書紀』が成立した当時の言葉で読むことを通じ、古代の日本人の心である古道をあきらかにしようとする学問である。本居宣長、上田秋成ともに国学者の学統に連なる。宣長は漢意(からごころ)を否定し、日本人の心を明らかとし、人間解放への道を拓き、国民的倫理の確立を真面目に希求した。同時に粗雑な皇国思想を主張したため都市のブルジョワ文化サロンの一人であった秋成が「臭み」として批判、ここから論争に至った。
日の神論争は両者の応酬を宣長が論点ごとにアレンジして成った『珂刈葭(かがいか)』に収録されている。『珂刈葭』前編は古代日本語に「ん」の撥音があったか、なかったかをめぐる論争が、後編は『鉗狂人』に対する秋成の評と宣長の弁がある
古書も人の書いた書であり筆者の取捨選択、知識の有無、好悪の感情が入り込む。『記紀』に異同があればおかしいというべき。その点を問うた秋成に対し、宣長は古書に疑いがあるからといってすべてを否定すべきではない。異同があるのは自然なことという返事をした。小林秀雄は『本居宣長』のなかで宣長の逃げ口上ととられても仕方なかったとした。
日本は海内無比の上国であり、唐、天竺、西欧などの諸国は下国である。『古事記』に登場する日本の神は世界万国共通のものであるという本居宣長の神話論を展開した『馭戎慨言』(1778)に対し、上田秋成が『往々笑解(おうおうしょうかい、と読む説あり。現存せず)』という本を書いて批判した出来事があった。
関連記事
-

-
『結婚のない国を歩く』モソ人の母系社会 金龍哲著
https://honz.jp/articles/-/4147 書によれば、「民族」という単
-

-
書評 三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』日本何故いかにして植民地帝国となったのか ビルマの竪琴のラストはスコットランド民謡 共通の歌曲がない 欧州文化と同じ意味でのアジア文化の存在に疑念
植民地帝国へと踏み出す日本 三国干渉が契機 非公式帝国主義 コストをかけなくてすむ方式 不平
-
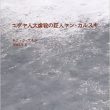
-
歴史認識と書評『ユダヤ人大虐殺の証人』河出書房新社
ユダヤ人虐殺の証人として映画『ショアー』にも出演したポーランド人カルスキの苦悩を描く衝撃の作品。
-
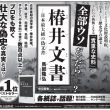
-
有名なピカソの贋作現象 椿井文書(日本最大級偽文書)青木栄一『鉄道忌避伝説の謎』ピルトダウン原人
下記写真は、英国イースト・サセックス州アックフィールド(Uckfield)近郊のピルトダウンにある
-

-
「戦争を拡大したのは「海軍」だった」 『日本人はなぜ戦争へと向かったのか戦中編』NHKブックス 歴史は後から作られる例
https://www.j-cast.com/bookwatch/2018/12/09008354
-

-
戦後70年の価値観が揺らいでいる」歴史家の加藤陽子氏、太平洋戦争からTPPとトランプ現象を紐解く 真珠湾攻撃から75年、歴史家・加藤陽子氏は語る「太平洋戦争を回避する選択肢はたくさんあった」 三国同盟の見方 歴史は後から作られる例
/https://www.huffingtonpost.jp/2016/12/0
-

-
世界の運営を米国でなく中露に任せる 2023年6月7日 田中 宇
https://tanakanews.com/230607armenia.htm 5月25日、
-

-
非言語情報の「痛み」
言語を持たない赤ん坊でも痛みを感じ、母親はその訴えを聞き分けられる。Pain-o-Meter Sc
-

-
動画で考える人流観光学 リーマン予想 素数
ゲーテルの不確定性原理 https://youtu.be/hEG1cWJD
-
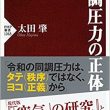
-
地域観光が個性を失う理由ー太田肇著『同調圧力の正体』を読んでわかったこと
本書で、社会学者G・ジンメルの言説を知った。「集団は小さければ小さいほど個性的になるが、その集団


