歴史は後から作られる 『「維新革命」への道』『キャスターという仕事』『明治維新という過ち』を読んで
公開日:
:
観光資源
国谷裕子の岩波新書「キャスターという仕事」をようやく、図書館で借りることができた。人気があるのであろう。
テレビ報道の危うさを三つにまとめているが、テレビに限らない。もっと時間の長い歴史も同じで、報道の積み重ねの上に歴史が成り立っているからだ。
①事実の豊かさをそぎ落としてしまう
②視聴者に感情の共有化、一体化を促してしまう
③視聴者の情緒や人々の風向きに、テレビの側が寄り添ってしまう
以上の三つの危うさは、歴史も全く同じで、ある。
「明治維新」字句自体が後から作られている。鎌倉幕府という歴史用語は明治になって作られたというから、これよりはましではあるが。
事件を後から正当化するための用語であることは使用される字句から理解されるが、当初は「朝政一新」「天下一新」「百事一新」など「(御)一新」が主流であったようだ。公文書等では明治7,8年ころが初出という記事がネットに出ているが、新聞等では明治半ばからということのようだ。産業革命が50年くらいの期間のことを指すと考えれば、時間的には短く、革命といってもいいのかもしれない。
明治維新の評価である。歴史家ではなく作家の原田伊織が書いた『明治維新という過ち』も定説を覆す書物の一つであり、面白く説得力はある。その主張の根拠や出典がほぼ示されていないため、完全に納得というよりは「そういう見方もあるんだな〜」で終わってしまうところはあるが、完全に否定もできず、受け入れる自分が、日本が元気な時代と、力を失ってゆく時代では受け止め方も違ってくるということを感じるだけである。キャスターという仕事の3の危うさである。
江戸時代再評価は一般化して来ているが、その裏返しの明治維新を過ちとする説は少ない。が、これもいずれ変わるかもしれない。
副題がテロリスト吉田松陰になっている。私も松蔭大学の客員教授をしていたので、まったく無関係ではないが、松下村塾は伯父の玉木文之進が開いていたもので、吉田松陰は教師ではなかったということ。松下村塾を有名にしたのは山形有朋ということ。このことは事実を調べればある程度分かるのようだが、その理由は、原田によれば山形自身の名声を高めるためであったという解釈になっている。松陰の獄死にあたっては幕府は長州藩に相談しているという事実があり、長州藩も持て余し気味であったという解釈。いずれにしろ、暗殺を先導していたことはまちがいがなく、それは吉田松陰に限らず長州藩に多くみられることで、現代用語でいえばテロTリスト集団であろう。ロシア革命と同じく、成功したということである。
坂本龍馬についても、グラバー商会の代理人であったということ、その利益(武器販売)のために行動していたということ、グラバー商会は中国にアヘンを売っている英国会社の子会社であったということは事実を確認すればわかることだが、イメージが変わることも間違いはない。
同書の書評に(司馬氏は自身も従軍した太平洋戦争で苦渋を味わった反動で、明治維新及びそれに携わった若者達に光を見るという”愚”を犯した。ちなみに、その若者達を描いた作品が「”竜馬”がゆく」であって、竜馬(若者達の表象)と坂本龍馬なる人物とは無関係)という記事があり面白いと思った。
新選組についての書評も紹介しておく
「1新撰組は基本的に、取り締まり集団であり、捕縛した者は奉行所へ引き渡していた。よって、拷問だのを日常的にすることはなく、そのイメージは、池田屋の時の古高への土方によるものが大きいと思われる。しかしあのときは、古高があまりにも多量の武器弾薬および会津藩の印が入った品が見つかり(会津の仕業と思わせるため)、テロ決行が迫っているとの危機感から、例外的に行われたことである。それから、明治以降のネガティブキャンペーンのせいで新撰組が随分大量殺戮を行ったように思われているが、最近の研究では、実際に殺した人数は、内部粛清のほうがその他より多い位と考えられている。
2 京都人が新撰組や会津が狼藉をしたから嫌われていて、長州は好かれていたという件についてそもそも京都の人が長州贔屓だったのは、金払いよく、上客だったから。長州が狼藉しなかったからではない。
3 会津が薩摩、長州にひどい目に合わされたのは、負けるとわかってても戦争を止めなかったからで、それは太平洋戦争時に似ているという件についてこれはそもそも会津が何回も恭順の意を示したのに無視した、徹底的に叩かなければ気がすまない(何故なら江戸は明け渡されちゃったから)薩摩と長州のせいである。そもそも長州が幕府の要人等を天誅などといって、殺しまくらなければ、新撰組が結成されることはなかった。新撰組に自分達の仲間が殺されたなどと恨むのは筋違い。更に、池田屋で新撰組が止めていなければ、風の強い日を選んで京都に火をつけて、天皇を誘拐し、京都守護職であり天皇の信頼厚い松平容保公とその弟を暗殺するという前代未聞のテロが決行されていたのであり、日本人、特に京都の人は、これを命懸けで止めてくれた新撰組をもっと評価すべきではないだろうか。」
いずれにしても、明治維新あるいは明治維新ではなく幕府改革(原田氏はこの方法が成功していれば、日本は太平洋戦争も行わず、北欧の国のようになっていたのではとしている)であっても、欧米列強の植民地にならずに、独立国家として開国できていたであろうし、欧米列強が帝国主義から変質する時期に対応できたことは運がよかったのであろう。その運は、隣の巨大な中国の存在があったのかもしれない。その分、運が悪かったのは韓国・朝鮮であったのだろう。
最後に苅部直の『「維新革命」への道』を読む。たぶんこの考え方がいずれ通説になり、大きく明治維新観が変わるのであろう。
同書では、「福沢諭吉の「文明論之概略」には「維新」という言葉は一カ所しか出てこない。むしろ「王政一新」と「廃藩置県」を別々の事件として論じている。福沢諭吉は尊王攘夷運動が、公家と諸藩の志士たちを動かして日本全体の「維新」へと導いたと今も流布している俗論を徹底して退けている。」「江戸時代の社会は同時代の中国や朝鮮とは異なり厳格な身分制によって規律されていた」「そうした感情が次第に社会に蓄積してゆき、それが尊王攘夷運動をきっかけにして爆発した」、福沢諭吉は「廃藩置県を通じて身分制が解体された転換の方に大きな意義を見出している」とする。
「江戸時代の遅くとも後半から、ゆっくりとした社会の変化が続いており、その影響が蓄積した結果として「御一新」の政治変化が可能となった」「江戸時代と明治時代を通観する「19世紀」という時代の長い範囲で思想史を作り直してみよう」として苅部氏は書かれたとある。
大阪維新の会は明治維新の維新とイメージを重ね合わせて字句を使用したのであろうが、そのおかげで維新の持つつきもの落ち、維新が安っぽくなった効果があった。司馬遼太郎の歴史小説の効果がようやく薄れる作用が始まったのだ。
観光研究からすると、「明治維新」は第一級の観光資源である。私は同意しないが観光文化資源だと研究者の大半は思っているのであろう。我々が「南北戦争」を知っているように、中国人や韓国人も「明治維新」を知っているのである。源平合戦や関ヶ原の合戦はもちろん知らないが、明治維新は聞いたことがあるから、日本に来ても関係するところに足を運ぶのである。鹿児島県、山口県、高知県、福島県、函館市から明治維新を取り除いてしまっては、観光客は激減するに違いない。従って、史実や歴史観とは別に、観光資源としての歴史認識の評価を研究したいと思っているのである。
関連記事
-

-
童謡「赤とんぼ」から躾を考える
村のしつけが対象とするのは正規メンバーだけで、共同体からはみ出た子供たちは、アウトサイダーとして
-

-
観光資源・歴史は後から作られるの例
http://www.asahi.com/articles/ASKB05T40KB0ULZU015.
-
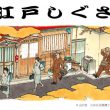
-
伝統は後から創られる 『江戸しぐさの正体』 原田実著
本書の紹介は次のとおりである。 「「江戸しぐさ」とは、現実逃避から生まれた架空の伝統である。本書は
-

-
小川剛生著『兼好法師』中公新書 安藤雄一郎著『幕末維新消された歴史』日本経済新聞社
『兼好法師』 現在広く知られている兼好法師の出自や経歴は、没後に捏造されたもの。 一世紀を経
-

-
AI に書かせた裸婦とダリ
AIに描かせたという裸婦の絵がネットで紹介され、ダリが描いたようだと注釈。 正確にいえば、AIが描
-

-
マルティニーク生まれのクレオール。 ついでに字句「伝統」が使われる始めたのは昭和初期からということ
北澤憲昭の『<列島>の絵画』を読み、日本画がクレオールのようだというたとえ話は、私の意見に近く、理解
-

-
伝統は古くない 『大清帝国への道』石橋嵩雄著を読んで
北京語 旗人官僚が用いていた言語 山東方言に基づく独自の旗人漢語を北京官話に発展させた チャイナド
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源論 宇宙旅行
https://youtu.be/KpGnwLiTYj8 https://youtu.be/a
-

-
「地消地産」も「アメリカファースト」も同じ
『地元経済を創りなおす』枝廣淳子著 岩波新書を読んだ。ちょうど教科書原稿を書いているときだったので参
