『日本人のためのアフリカ入門』『アフリカを見る アフリカから見る』白戸圭一
公開日:
:
最終更新日:2023/05/19
人口、地域、
アフリカ旅行にあたって、白戸圭一氏(毎日新聞OB)の「日本人のためのアメリカ入門」(2011年)「アフリカを見る アフリカから見る」(2019)をみなと区立図書館から借りて読む。「貧しくてかわいそう」「部族対立が深刻」「発展が遅れている」というアフリカの印象、御多分に漏れず私にもアフリカに対する漠然とした負のイメージがあるが、この「日本人の歪んだアフリカ観をそろそろ見直そう」というのがこの本のテーマであった。アマゾンの本書の紹介文書にあったように、「平成」の三十年間で、日本とアフリカを取り巻く状況は激変した。経済成長が止まり、国力が低下する日本に対して、国連加盟国54か国のアフリカは、多くの国で経済成長が持続し、二〇五〇年に世界人口の四人に一人を占め、政治的な力も増大すると記述している。
◎「貧しくはない」
筆者の白戸氏は、アフリカ諸国は独立時から世界最貧であったわけではないと解説する。むしろ中国よりも豊かであったようだ。先進国の「援助」は経済危機の始まった1980年代からであり、その後二十年間、成長しなかったから、貧しさのイメージが出来てしまったのだとする。21世紀にはいり、 急成長している。確かにCNNのコマーシャルなどでもラゴスなどの繁栄ぶりを目にすることがある。その発展は、援助ではなく、 直接投資が増えたからであり、その中心にいるのが中国であるようだ。従って、欧米メディアの報道とはことなり、アフリカ諸国民への調査では、中国には好意的であるようだ。 「アフリカのイメージと言うと、「ピラミッドやサファリは見たいけど、内戦・テロが多くてエボラもあって・・・・・」だった。しかし、アフリカは広大で、高度経済成長中の地域では、もはや援助でなく投資を必要としている。しかし、多くの日本人のアフリカ観は、援助対象国のままで固まってしまっている。
◎反応的国家とメディア
日本のメディアは、欧米と関わりがないアフリカ関係のニュースは報道しない。また、内戦や紛争が起きても、その理由を権力闘争や経済格差ではなく「部族対立」のせいにする。スーダンのダルフールの紛争やジンバブエの紛争について、英国やアメリカの同国に対する態度を見据えてから報道し始めるのが日本のメディア。このような日本の反応を、「反応的国家」といい、白戸氏によればケントカルダーという人が日本に命名したようだ。この「反応的国家」姿勢、つまり 他国(欧米諸国)の様子を見ながら自国の政策を変化させて行く姿勢を白戸氏は批判する。例として「ジンバブエ問題」がわかりやすい。英国ブレア労働党政権は、保守党政権がそれまで一応認めてきた大英帝国のつけを認めずに、ムガベ大統領が要求した土地収用のための資金援助を拒んだ。逆にブレア英国首相は問題をすり替え、ムガベ政権を打倒するため、人権問題を利用してアメリカを中心とする国際世論を動かした。「反応的国家」姿勢の日本のメディアは、ジンバブエ報道には、必ず、米国政府から圧政の批判を受けているという枕言葉を記事につけて記事にしていた。欧米メディアに応じた、ウクライナ報道の日本メディアの大合唱を見れば、このことはよくわかるような気がする。その結果、日本政府が夢見てきた国連安全保障常任理事国入りが、日本の常任理事国入りに反対する中国の意を受けたムガベの働きかけにより、国連加盟国数が54か国にも上るアフリカ諸国のコンセンサスを得ることができなかったことにより、夢とついえたと白戸氏は解説する。
「部族対立」という罠
白戸氏は、アフリカ各地のほぼ全ての紛争が現代政治における失政によるものであるにもかかわらず、部族対立と言う言葉を使うがために、読者に昔ながらの野蛮人の伝統的戦いを思い起こさせている、と述べる。 例えばケニア・キベラスラムの虐殺(2007年)は選挙不正にかこつけて、反政権派が計画的に政権派住民を殺害を実施しており、民族対立といったものではないと記述する。 アフリカの国々や人々をどのように「味方につける」かという戦略も全然無い。「アフリカで嫌われている中国」という「願望」にはしがみつくが、その中国に対抗して日本がアフリカでプレゼンスを高めていくための動きも人材も全く足りない。
関連記事
-

-
「太平洋戦争末期の娯楽政策 興行取締りの緩和を中心に」 史学雑誌/125 巻 (2016) 12 号 金子 龍司
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発
-
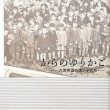
-
『からのゆりかご』マーガレット・ハンフリーズ 第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっと恥ずべき秘密
第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっ
-
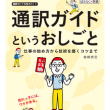
-
規制改革会議 無償運送、謝礼に関心 東京交通新聞2017年3月27日
標記の記事が東京交通新聞に出ていた。 規制改革会議が、3月23日現行の基準を緩和できるかヒアリング
-

-
日経の記事「東京郊外への移住じわり」
これに対するコメントの紹介 データを扱うのであれば正確にお願いしたい。東京一
-
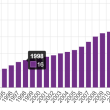
-
Is it true only 10% of Americans have passports?
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42586638
-

-
『物語 ナイジェリアの歴史』島田周平著 中公新書
アマゾン書評 歴史家トインビー曰く、アフリカはサハラ砂漠南縁を境に、北のアラブ主義
-

-
観光学を考える 『脳科学の教科書 神経編・こころ編』岩波書店 理化学研究所脳科学総合研究センター編 をよんで
図書館でこの二冊を借りてきて一気に読む。岩波ジュニア選書だから、子供が読む本だけれど私にはちょうどい
-

-
2016年3月1日朝日新聞8面民泊関連記事でのコメント
東京都大田区が、国の特区制度を活用して自宅の空き部屋などを旅行者に有料で貸し出す「民泊」を解禁
-

-
ホテルアセッセトマネジメントとAirbnb 人の移動の自由・労働者の囲い込みと専門職大学の在り方
これも機能分化である。運送機能の分化を考えてきたが、宿泊機能も分化している。オーナーとオペレーターへ

