橋本健二 『格差と階級の戦後史』
公開日:
:
最終更新日:2023/05/20
出版・講義資料
この社会はどのようにして、現在のようなかたちになったのか?
敗戦、ヤミ市、復興、高度成長、「一億総中流」、
バブル景気、日本経済の再編成、アンダークラスの出現……
「格差」から見えてくる戦後日本のすがたとは――
根拠なき格差論議に終止符を打った名著『「格差」の戦後史』を、
10年の時を経て、新データも加えながら大幅に増補改訂。
日本社会を論じるならこの一冊から。
格差と貧困から見えてくる、この社会の自画像
貧しさからの出発――敗戦から1950年まで
「もはや戦後ではない」――1950年代
青春時代の格差社会――1960年代
「一億総中流」のなかの格差――1970年代
格差拡大の始まり――1980年代
日本社会の再編成――1990年代
新しい階級社会の形成――2000年代
アンダークラスの時代――2010年代
日本の階級社会に未来はあるのか――!?
書評1
豊富なデータを基に階級と格差の形成過程を分析している。本書334頁では、「階級別にみた政党支持率の変化」が掲載されている。いずれの階級も、2000年以後は自民党支持率が下がっており、「支持なし」が増えている。
①法人税減税など企業優遇策を採用してきた政府自民党に対し、資本家階級は強い不満を表明していることが分かる。この自民党への不満が野党最大勢力(政権も獲得)である民主党には向かわず、いずれの政党も支持しない「支持なし」側に回り、無党派層を形成しているのが興味深い。民主党政権崩壊の理由は、東日本大震災への対応の不手際によるものである。旧中間階級のみが、民主党支持を微増させている。
②しかし、総選挙では明らかに与党民主党が勝利しているところを見ると、「支持なし」としながらも、とりあえず、他にユウリョクナ政党もないので、あるいは自民党に代わる政党もないので、安倍政権支持に回っている無党派層も多いのではないか?
③どの階級においても「支持なし」が50%前後を占めながら結果的には選挙で自民党が圧勝している構図が面白い。
④バブル崩壊後の低所得者層の増加と少子高齢化による深刻な労働力不足が日本経済が直面している最大の課題であるである。人件費を上げても働く人は集まらない。それゆえ倒産・閉店する企業が続出している。人件費の高騰は確実に企業の経営を圧迫するので、上げるにも限界があるのである。
⑤外国人投資家労働者は都市部であれば、小用することも可能であるが、地方都市ではそれも集まらない。AI導入はまだまだ先の話である。
⑥「格差」は、政治家・医師・経営者・大學教員・公務員等で二世が多いことを見れば拡がっていることがわかる。政治家の大半は二世議員であり、医師も親が医師である者が多い。親が富裕でなければなれない職業が増えた。質の高い教育を受けるためには家庭の豊かな経済力が必要である。私大医学部に入学するには貧困階級、中間階級はでは不可能である。政治家も親の選挙基盤を受け継がなければ、当選は難しい。
⑦「格差」を埋める政府の政策が必要だ。子育て支援、中等教育・高等教育の無償化が必要だ。 「階級」をなくすには「ベーシックインカム」の導入が必要だ。高齢化は社会の活力を低下させる。高齢者の雇用の拡大が必要だ。
書評2
私も戦後すぐから話が始まっているのが面白いと感じました。
戦後、農民層から世代間移動が始まって、高度経済成長にのっかっていくダイナミックさが、社会の活力だったのでしょう。私の夫の父も農家から労働者階級に移動しました。
しかし、バブル期に資本家階級と新中間階級が勢力を伸ばし、その後バブル崩壊を経て、やや固定化しました。富裕層が再生産されるようになったのは、このためです。
就職氷河期世代が非正規雇用に多く流れたために、従来の階級の下にアンダークラスが生まれ、格差が拡大し、反転が困難になりました。
資本家階級は自分の子を自分の階級で働かせることができましたが、新中間階級は、正規雇用に成功する家庭と、非正規雇用に甘んじた家庭とに別れ、必ずしも再生産されているとは限りません。私の兄弟の家庭でも、有名大学を出て一流企業の正社員になった子と、大学を中退してフリーターに甘んじている子が、1つの家庭にいます。そういう例は少なくないのではないかと思います。
私自身は明治時代から新中間階級の家系という、やや特殊な出身です。私で4代目になります。
でも今感じるのは、これからは新中間層で生き抜くのは難しいということです。農林水産業が復活するのではないでしょうか。私の子は地方公務員2人と看護師で、まあ2人は20代で結婚して子供も2人いて、中古ですがマイホームも手にいれようかとしています。その子供が、息子(私の孫ですね)はいざとなれば水産高校に進めばいいと言い、また地方公務員の1人は林業職公務員です。
食糧生産と環境問題が、今後注目されるようになると思います。若いアンダークラスはそちらに移動すればいいのでは?
まあこの予測は外れるかもしれませんが。(それでもいいんです。競争が少なくなるでしょ笑)
全てが農業からの移動が発端だったと知った時、農業に帰る時代がきたと思いました。
関連記事
-

-
ゆっくり解説】突然変異5選:新遺伝子はどうやって生まれるのか?【 進化 / 遺伝 子 / 科学 】
https://youtu.be/bGthe_Aw1gQ ミトコンドリアと真核生物の起源:生物進化
-

-
Quora 日本が西洋諸国の植民地にならなかったのは何故だと思いますか?
https://jp.quora.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8C%
-
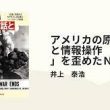
-
アメリカの原爆神話と情報操作 「広島」を歪めたNYタイムズ記者とハーヴァード学長 (朝日選書) とその書評
広島・長崎に投下された原爆について、いまなお多数のアメリカ国民が5つの神話・・・========
-

-
QUARA コロナ対処にあたってWHO非難の理由にWHOの渡航制限反対が挙げられていますが、これをどう思いますか?
渡航制限反対は主に「中国寄りだから」という文脈で語られています。しかし調べてみれば、今回のコロナウ
-

-
保護中: 学士会報No.946 全卓樹「シミュレーション仮説と無限連鎖世界」
海外旅行に行けないものだから、ヴァーチャル旅行を楽しんでいる。リアルとヴァーチャルの違いは分かっ
-

-
DNAで語る日本人起源論 篠田謙一 をよんで(めも)
篠田氏は、義務教育の教科書で、人類の初期拡散の様子を重要事項として取り上げるべきとする。 私も大賛
-
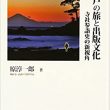
-
『江戸の旅と出版文化』原淳一郎
中世宗教史と異なり近世宗教史の大きな特徴に寺社参詣の大衆化がある。新城常三の「社寺参詣の社会経済史
-

-
ヨーロッパを見る視角 阿部謹也 岩波 1996 日本にキリスト教が普及しなかった理由の解説もある。
キリスト教の信仰では現世の富を以て暮らす死後の世界はあ
-

-
『日本が好きすぎる中国人女子』桜井孝昌
内容紹介 雪解けの気配がみえない日中関係。しかし「反日」という一般的なイメージと、中国の若者
-

-
「米中関係の行方と日本に及ぼす影響」高原明生 学士會会報No.939 pp26-37
金日成も金正日も金正恩も「朝鮮半島統一後も在韓米軍はいてもよい」と述べたこと 中国支配を恐れてい
