Quora 物語などによくあるように、中世ヨーロッパの貴族たちは国民から搾取してすごく贅沢な暮らしをしていたのですか?
中世に今日と同じ意味での「国民」はまだ存在しません。領主が農民を支配し、領主同士に主従関係があり、領地の関係・主従の関係が入り乱れていて、飛び地があったり、相続争いがあったり、複雑怪奇な様相を呈しているというのが中世です。現在のフランスもドイツもイタリアもイギリスもまだ存在しません。言葉が似ていてある程度通じたりはしたでしょうが、「同じ国民」という意識は何一つなく、例えば「シャンパーニュの生まれ」「ザクセン人」「バイエルン人」など、地方の方にアイデンティティを持っていたはずですし、そもそも農民たちには基本的に移動の自由がなく、ほかの地域の人間と出会うことすらまれだったはずです(商人や吟遊詩人が諸国を旅していたり、領主の宮廷が支配地を移動したりはしていたので、ゼロではなかったはずです)。
また、中世ヨーロッパの「貴族」は誤訳という話があります。中世の身分制度は「祈る人」「戦う人」「耕す人」であり、貴族は「戦う人」、つまり騎士階級で領主層ということになりますが、日本でいう平安貴族のイメージではなく、むしろ武士に近いわけです。本来は「武士」と訳すべきだったのでは、といっている人がいるくらいです。
中世の城は無骨な軍事拠点でしかなく、居住性は低く、生活は質素だったことでしょう。そもそも、元々たいしたことがない生産物をいくら搾取したところで、贅沢な生活ができるはずもありません。大航海時代になってもまだ、ヴァスコ・ダ・ガマがインドの王に贈り物をしたら、みすぼらしすぎてあきれられたというエピソードが残っています。一応国がまとまって、きちんと船を建造して、対外遠征をできるくらいになった時期であり、中世の領主などよりも遙かに経済力はつけた後での段階の話ですよ。
ウィキペディア「ヴァスコ・ダ・ガマより」
王宮に到着したヴァスコは来訪の目的を廷臣に伝えるように要求されたにもかかわらず、自らはポルトガル王の大使であるから王に直接話すと主張して聞かなかった[28]。翌日宮殿で謁見したヴァスコはカレクト国王に親書を渡し、目的のひとつを達成した[30]。しかし用意した贈り物を見た王の役人やイスラム教徒の商人は笑い出した。贈り物は布地、一ダースの外套、帽子6個、珊瑚、水盤6個、砂糖1樽、バターと蜂蜜2樽に過ぎなかった[28]。「これは王への贈り物ではない。この街にやってくる一番みすぼらしい商人でももう少しましなものを用意している」と言われ、ヴァスコは「私は商人ではなくて大使なのだ。これはポルトガル王からではなく、私の贈り物なのだ。王が贈り物をするならもっと豪華なものになるはずだ」と苦しい言い訳をした[28]。30日になった2度目の謁見でイスラム教徒への不信を国王に述べながらも、積み荷の交易許可を得た[31]。このとき王に「そんなに豊かな王国からやってきたならなぜ何も持ってこなかったのか」と聞かれている[28]。
つまり、王権が強くなってきて、中世よりもだいぶ豊かになったであろう15世紀の段階に至っても、まだヨーロッパの宮廷はアジアの宮廷よりも遙かに貧しかったということがわかります。いわんや中世です。日本の武家と同じく、庶民より多少ましではあるものの、質的にそれほど違った暮らしはできなかったことでしょう。
豊かだったのは、ヴェネツィアやフィレンツェなどルネサンスを牽引したイタリア諸都市、そして古くから交易で栄えていたネーデルラントの商人たちであり、そこの宮廷で育まれていた豊かな文化が、フランスにはカトリーヌ・ド・メディシスによって、ウィーンにはおそらくマクシミリアン1世(ネーデルラントを領有していたマリー・ド・ブルゴーニュと結婚し、そこで生活し、宮廷文化に衝撃を受けてウィーンにそれを持ち帰り、ウィーン少年合唱団を設立したり、宮廷楽団を整備したり、ハプスブルクの文化行政の走りでもあります)によって伝えられ、広がっていくことで、我々がイメージするようなヨーロッパの華やかな宮廷文化がやっと誕生してくるのです。
宮廷といえば
こんな感じをイメージするでしょうが、これはフランス絶対王政最盛期以降の様子であり、中世の宮廷といえば、いいところ
こんな感じです。これは1460年の写本だそうですから、もうすでにルネサンスに突入した後の話です。もっと前だと、せいぜい
こんなですよね。「すごく贅沢な暮らし」といえるでしょうか?
実際のところ、フォークが食器として使われるようになるのもこうした流れの中でテーブルマナーが確立されて以降の話であり、それ以前はスープはスプーンで飲み、ナイフで肉を切り分け、手づかみで食事をしていました。
ウィキペディア「フォーク (食器) – Wikipedia」より
16世紀後半の戦国時代・安土桃山時代の日本でキリスト教の布教を行った、イエズス会の宣教師であるルイス・フロイスは、著書の『日欧文化比較』の中で、16世紀当時、日本人が箸で食事していた一方で、ヨーロッパ人が手づかみで食事していたことを、記録している。
キリンビールのページに中世ヨーロッパの各階層の食事の再現が載せられています。
肉や魚はあるものの、調理は洗練などされておらず、ただやたらに貴重な香辛料をかける、という性質の調理で、こうした食事を基本手づかみで食べていたわけです。
これは、農民からみたら「すごく贅沢な暮らし」かもしれませんが、現代的に見ると「農民よりは若干ましだが、当時のアジアの宮廷などと比べるべくもないみすぼらしい暮らし」と言えるでしょう。どう見るかはどこに視点を置くかだと思います。
関連記事
-

-
『時間は存在しない』カルロ・ロヴェッリ
『時間は存在しない』は、35か国で刊行決定の世界的ベストセラー。挫折するかもしれないので、港区図書
-
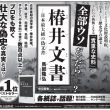
-
有名なピカソの贋作現象 椿井文書(日本最大級偽文書)青木栄一『鉄道忌避伝説の謎』ピルトダウン原人
下記写真は、英国イースト・サセックス州アックフィールド(Uckfield)近郊のピルトダウンにある
-

-
QUORAにみる歴史認識 不平等条約答えは長州藩と明治政府のせいです。今回に限って言えば、長州藩と明治政府が不平等になるように改悪した原因なのです。
日本人があまり知らない、日本の歴史といえば何が思いつきますか? 日米和親条約と日米修好通商条
-
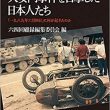
-
『天安門事件を目撃した日本人たち』
天安門事件に関する「藪の中」の一部。日本人だけの見方。中国人や米国人等が作成した同じような書籍があ
-

-
日本人が海外旅行ができず、韓国人が海外旅行ができる理由 『from 911/USAレポート』第747回 「働き方改革を考える」冷泉彰彦 を読んで、
勤労者一人当たり所得では、日本も韓国も同じレベル 時間当たりの所得では、日本は途上国並み これで
-
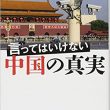
-
『言ってはいけない中国の真実』橘玲2018年 新潮文庫
コロナ禍で海外旅行に行けないので、ブログにヴァーチャルを書いている。その一つである中国旅行記を
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進
-

-
QUORA 日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか?
日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか? 近衛文麿でしょう。彼は首相在任中に国運を左右する二
-

-
「北朝鮮の話」 平岩俊二 21世紀を考える会 10月13日 での講演
平岩氏の話である。 日本で語られる金ジョンウンのイメージは韓国発のイメージが強い。そのことは私も北
-

-
歴史は後からの例「殖産興業」
武田晴人『日本経済史』p.68に紹介されている小岩信竹「政策用語としての「殖産興業」について」『社

